
本日2月10日は「2(ふ)10(るーと)」にかけて「フルートの日」だそうですが、日本人はフリーダイヤル、車のナンバー、日付や年号などの数字と言葉の「語呂」を合せること(駄洒落)が大好きな民族です。「語呂」の語源は、雅楽で楽曲の調子(「律呂」)が合わないことを「呂律(ろれつ)が回らない」と言ったことから、それに倣って言葉の調子を「語呂」、また、言葉の調子が合わずにはっきりとしないことを「ろれつが回らない」と言うようになったと言われています。調子(音階)は音律(音高)で構成されていますが、世界最古の音律は、紀元前582年頃に古代ギリシャで考案されたピタゴラス音律ではなく、紀元前2697年頃に中国の黄帝が楽人・伶倫に命じて作らせた音律であり(「呂氏春秋」より)、後に、それが日本へと伝来しています。なお、日本には、数字の読み方として、日本古来の倭語(大和言葉)である「ひ、ふ、み、よ、い、な、や、こ、と」(訓読み)と中国から伝来した漢語である「いち、に、さん、し(「よん」は訓読み)、ご、ろく、しち(「なな」は訓読み)、はち、きゅう、じゅう」(音読み)の2種類がありますが、最近では前者の数字の読み方は廃れ、僅かに語呂合わせのために使用されています。因みに、数字の「0」(ゼロ、零)という概念は仏教思想の「空」を意味するものとして7世紀にインドで発明されますが、後に、それがヨーロッパへと伝わり、コンピュータで使用されるデジタル信号(「0」「1」)など現代の科学技術の発展にとって「0」は必要不可欠な概念になっています。厳密には同じ「0」でも、「ゼロ」は完全に無いこと、「零(れい)」は極僅かしか無いことを意味しており、必ず、気象予報士は「0%」を「ゼロパーセント」ではなく「れいパーセント」と言うそうです。ところで、語呂合わせは日本だけのお家芸という訳ではなく外国でも使われているものですが、例えば、アメリカのフリーダイヤル番号「1-800-278-478」を覚えるために「1-800-artist」という語呂合わせが考えられます。これはスマホのテンキーに表示されているアルファベットに対応し、このアルファベットのとおりにスマホのテンキーを押すと上記のフリーダイヤルへつながるという仕組みです。また、南北戦争が終結した年として1865年を覚えるために「I captured south’s flags.」(南部の旗を奪い取った)という語呂合わせが考えられますが、この文を構成している各単語の文字数(I(1文字) captured(8文字) south’s(6文字) flags(5文字))を並べると1865年になるという仕組みです。アメリカにも日本のような駄洒落はありますが(例えば、「A bicycle can’t stand on its own, because it is too tired(⇔two tyres).」)、英語は日本語のような単音節言語ではなく多音節言語なので、日本語のように音を活かした語呂合わせを作ることは非常に難しく、上記のようなアイディアが生まれたのだろうと思います。
【題名】映画「ミュジコフィリア」
【監督】谷口正晃
【原作】さそうあきら
【脚本】大野裕之
【撮影】上野彰吾
【美術】金勝浩一
【衣装】宮本茉莉
【録音】小川武
【演奏】<Con.>粟辻聡
<Orc.>京都市立芸術大学音楽学部・大学院管弦楽団
【出演】<漆原朔>井之脇海(非嫡出子・異母弟)
<漆原君江>神野三鈴(妾親)
<貴志野大成>山崎育三郎(嫡出子・異母兄)
<貴志野龍>石丸幹二(父親)
<浪花凪>松本穂香(学友)
<谷崎小夜>川添野愛(学友)
<青田完一>阿部進之介(学友)
<椋本美也子>濱田マリ(准教授)
【感想】ネタバレ注意!

先日、架空の国立大学・京都文化芸術大学(これは実在の公立大学・京都市立芸術大学がモデル)を舞台に現代音楽の魅力紹介をテーマにした漫画「ミュジコフィリア」を実写化した映画を観てきましたので、その感想を簡単に残したいと思います。なお、現在、京都市立芸術大学では、校舎の老朽化等に伴う大学移転のための寄付金を募っています。「伝統と革新」が息衝く京都にある芸大だけあって、新しいものを生み出すことに熱心な校風の大学なので、芸術の未来に投資してみてはいかがでしょうか。さて、原作は、上述のとおり現代音楽の魅力紹介をテーマにした読み応えのある内容になっていますが、この映画は興行収入を意識して幅広い客層を取り込むことを狙った為なのか、ヒューマンドラマに主眼が置かれ、現代音楽の魅力紹介という意味では若干焦点がぼけてしまっている印象を否めず、原作を読んだ者にとっては些か物足りなさのようなものを感じてしまいます。個人的には、原作のように現代音楽の魅力紹介に主眼を置いた映画作りに徹した方がユニークな映画として話題性を呼んだのではないかと感じています。そうは言っても、この映画では京都市立芸術大学の学生及び卒業生が作曲した現代音楽が使用され(京都文化芸術大学の進級審査会の場面など)、現代音楽の魅力を音として感じることができますので、この映画を観る意義は大きいのではないかと思います。そこで、以下では、映画だけではなく原作も踏まえての感想を残します。原作及び映画は、京都の街の音(日本に独特な音を含む)を音楽で表現したいという想いで貫かれ、音という観点から京都の街の魅力も紹介されています。冒頭の場面では数多くの和歌に詠まれている鴨川(伝統)の上流域を流れる賀茂川(賀茂大橋を境にして上流域を賀茂川、下流域を鴨川と書きますが、京都市立芸術大学は鴨川河畔へ移転予定です)をショパンの練習曲変イ長調(作品25-1)の副題になっている楽器「エオリアン・ハープ」(自然に吹く風によって音を奏でる楽器)に仕立て賀茂川を渉る風が奏でる音に乗せて、ヴァイオリン、ピアノ、ハーモニック・パイプや民族楽器などが即興演奏する(偶然性の音楽)(革新)という印象的なシーンから始まります。母親がピアニスト、叔父がフルート奏者という音楽一家で育った俳優の井之脇海が演じる漆原朔は、その天賦の才能(共感覚を含む)から京都の街(とりわけ京都の自然)の音を音楽として表現する能力に優れ、京都の池泉廻遊式庭園「無鄰菴」が表現している音の世界(コスモロジー)からインスピレーションを受けてピアノ曲を創作しますが、漆原朔がその曲を演奏しているピアノ(井之脇海の実演)の下から浪花凪が「その場所、知ってるぅ~!」と顔を出す場面で、その非凡な才能が印象的に描かれています。池泉廻遊式庭園「無鄰菴」は、1890年に庭師の七代目小川治兵衛(植治)が作庭した庭園で、琵琶湖疏水を利用して瀬落ちする水音を多彩にデザインし、それまでの「鑑賞する庭園」(静的な芸術体験)から「体感する庭園」(動的な芸術体験)へと庭作りを「革新」します。このような芸術体験の在り方を根本から革新しようとする創作姿勢は、近年の技術革新などを背景として現代の芸術表現の1つの潮流になっているように感じます。原作及び映画では、ジョン・ケージが作曲した「4’33””」が採り上げられていますが、この曲も芸術体験の在り方を根本から革新したものと言えます。ジョン・ケージは、「誠実さをもって何か悲しいものを作曲したにも拘らず、聴衆や批評家がしばしば笑うことに気づいた」という辛い経験を通して「音楽の目的をコミュニケーションだ」とするアカデミックな考え方に疑問を抱くようになり、「音楽の目的とは、分別を持たせ心を落ち着かさえることで、神聖な影響を敏感に受け入れられるようになること」(タブラー奏者のギタ・サラバイ)であって、「芸術家の責任は己の手法でもって自然を模倣すること」(哲学者のアナンダ・クーマラスワミ)であるという考え方に共感し、そこに音楽(作曲)の意義を見い出します(「ジョン・ケージ 作曲家の告白」より)。このような考え方は東洋思想(禅)に影響されたものですが、外から与えられるもの(例えば、神の言葉を通して神と自分とのコミュニケーションにより救いを求めるキリスト教的な考え方など)に依拠するのではなく、内から生じるもの(例えば、自然に身を委ねて自ら悟る禅的な考え方など)に依拠するものであり、静寂に耳を澄まして自らの中に音楽を聴くという意味で(西洋音楽における)芸術体験の在り方を根本から革新する考え方だと思われます。「4’33””」は、「絶対零度(-273.15度)」(物質の熱運動(原子の振動)が完全になくなることはありませんので、上述のとおり「ゼロ」ではなく「零」)を表現しているもの(全てが凍り付いた静寂の世界を黙示するもの)という解説を見かけますが、「科学」(俗)と「宗教」(聖)の境界が曖昧になっている現代の時代性を捉えている曲とも言えそうです。この点、音楽表現において「0」(TACET)の意義を認めないという立場をとれば、「4’33””」は音楽なのかという疑問を惹起し易いと考えられますが、現実世界(現代物理学を含む)と同様に、音楽表現においても「0」(TACET)の意義を認めるという立場をとれば、「4’33””」はTACET(音を出さないこと)という音楽表現を通して聴衆が感じ取る全てものが芸術体験であると捉えることが可能であり、原作及び映画でも同様の考え方に立ってこの曲を採り上げていると思われます。あくまでも、芸術鑑賞は個人的な体験であって「4’33””」を聴いて何を感じるのか否かは人それぞれですが、少なくとも僕はこの曲を聴いてニヤケ笑いしたくなるような感興を生じることはありません。この映画では省略されてしまっていますが、原作では漆原朔が秋吉台現代音楽セミナーに参加する重要な場面があり、ワーグナーのトリスタン和声からシェーンベルクの十二音技法(セリエリズム)へと至る過程で調性の呪縛から音楽が解放され、その後、メシアン、ブーレーズ、ショトックハウゼンのトータルセリエリズム、リゲティのミクロポリフォニー、ケージの偶然性の音楽、クセナスキの確率音楽、ミュライユのスペクトル音楽など調性システムに依拠しない作曲技法を模索するために生み出された新しいシステムの変遷について概観したうえで、調性システムを使うと「既聴感」のある音楽しか創作できず、如何に「未聴感」のある音楽を創作するのかが現代音楽の課題であることを学びます。この点、過去のブログ記事でも触れているとおり、クラシック音楽(調性音楽)の表現可能性の限界が認識されるなか、第一次世界大戦で中世的な社会体制や価値感などが崩壊し、「昨日までの世界」を表現するためのクラシック音楽(調性音楽)が過去の遺産(伝統)と認識されるようになりますが、リスト、ドビュッシー、ワーグナーやシェーンベルクは音楽表現の可能性を拡げるために調性の呪縛から音楽を解放して、「今日の世界」を表現するための多様な音楽表現が可能となる新しい作曲技法(革新)を模索するようになります。しかし、芸術家に比べてシナプス可塑性の劣る聴衆は新しい音楽表現を理解できず、近代的な商業主義の仕掛けに乗ってクラシック音楽(調性音楽)を演奏する現代の指揮者や演奏者は注目される一方で、現代の作曲家及びその作品は殆ど顧みられないという不幸な状態が続いてきました。過去の偉大な作曲家が残した傑作群が時代の風雪に耐え得る普遍的な価値を有するものであるとしても、いつまでも過去の遺産のみを受容し、新しく生み出される芸術表現を顧みない状態(即ち、過去の遺産だけではシナプス可塑性の活発化が促され難く、脳が十分な報酬を得られない結果として、いずれ脳が過去の遺産に注意を向けなくなる虞がある状態)が続くとすれば、将来に亘ってクラシック音楽界が持続可能なものであり得るのか危惧を覚えます。現在は、映画、TVドラマやゲームなどサブカルチャーの力を借りて聴衆が現代音楽に慣れてきている状況があり、その限りで現代音楽に過剰なアレルギー反応を示す聴衆は少なくなってきているのではないかと思いますので、今こそ、このような不幸な状態を抜け出すための意欲的な取組みに期待したいと思います。なお、現代音楽を採り上げるフェスティバルとして、上述の秋吉台現代音楽セミナーの他にも、ペガサス・コンサート、武生国際音楽祭、三島現代音楽祭、TAma Music and Arts Festival、両国アートフェスティバル(両国門天ホール)、ミュージック・フロム・ジャパン(於NY)、ボンクリ・フェス等が注目を集めています。また、21世紀音楽の会、New Chamber Music、ensemble Nostos、全音現代音楽シリーズ、アンサンブル・ノマド、アンサンブル・コンテンポラリーα、東京シンフォニエッタ、いずみシンフォニエッタ大阪、オーケストラ・ニッポニカ、現代奏造Tokyo、東京現音計画、JFC等の精力的な活動も注目されています。因みに、今月は、2024年の引退を表明し「自分の心が求めるものしか演奏しない」と宣言している指揮者・井上道義がクセナキス生誕100年を記念してピアニスト・大井浩明及び東京フィルハーモニー交響楽団との共演によりクセナキス「ピアノ協奏曲第3番(ケクロプス)」(1986)を日本初演しますので、これは聴き逃せません!
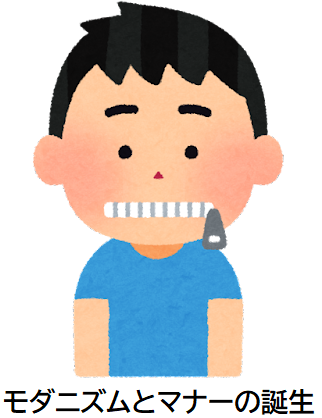
映画では、山崎育三郎がニヒルに演じる貴志野大成が音大オケを指揮する中で「音楽を汚すな」とオケメンを叱責し、楽譜に忠実な演奏を求める場面が印象的に描かれています。過去のブログ記事でも触れていますが、音楽教育を効率的に行うために楽譜(記譜法)が発明されて後世に音楽を正しく伝えることや第三者が音楽を正しく演奏することが容易になり(作曲家の誕生)、それによって人類は多大な恩恵を享受してきました。この点、古代ギリシャ時代には、未だ楽譜(記譜法)が発明されておらず、音楽は基本的に即興で演奏されていましたが(パロール的文化)、音楽は人間の心を鎮め道徳に働きかける力があると考えられており宗教儀式等でも利用されていたことから神聖視されるようになり、リベラルアーツの自由7科にも挙げられています。その伝統から楽譜が発明されてからは楽譜に記録された音楽が神聖視され(エクリチュール的文化)、やがて楽譜に忠実な演奏のみが真実を語り得るという楽譜至上主義へと先鋭化して行きます。中世には、王侯貴族(上流階級)が社交のためのサロンで音楽をBGM(アソビエント)として利用していましたが、市民革命を経て近代を迎えるとブルジョアジー(市民)が音楽を鑑賞するためのコンサートホールで音楽の聴取に専念するようになり、当時の美学的な潮流等から、娯楽性が高い技巧的で壮麗、華美に彩られたヴィルトゥオーゾ音楽(アドルノの「聴取の類型論」に基づく聴衆7類型のうち、「教養消費者」「情緒的聴取者」「復讐型聴取者」「娯楽型聴取者」が行う「感性的聴取」)ではなく、崇高な理念により構築された偉大な音楽を統一的又は体系的に捉えてその表現意図を解釈する芸術受容の在り方(アドルノの「聴取の類型論」に基づく聴衆7類型のうち、「エキスパート」「良き聴取者」が行う「構造的聴取」)が重視されるようになります。この点、「美学」(英語:Aesthetics)という言葉は「感性」(ギリシャ語:Aisthesis)という言葉を語源としていますが、これは芸術の本質が美(物事の真理を体現する、完全に調和された状態)にあり、その美は感性的に認識されるという考え方が背景にあったと言われています。しかし、西洋では、キリスト教の影響から物事の「本質」(真理、真実)は「知性」(理性)が司る精神的な営みによって捉えられるものであり、それと比べると「感性」(本能)が司る感覚的な営みは劣っているという価値観があり、芸術は美を表現するものであるという近代的な考え方を前提として、その美の本質を理解するためには単に芸術を感覚的に捉える感性だけでは足りず、芸術を統一的又は体系的に捉える知性(精神性)が必要であるという考え方(モダニズム)が生まれます。キリスト教は、二元論的世界観から自然は人間が支配するものであるという人間中心主義的な価値観があり、それを前提として人間が創り出す芸術的な美は自然が創り出す自然的な美よりも優れているという考え方が生まれ(例えば、西洋庭園の幾何学的な人工美など)、美の本質の理解にあたっては感覚的に認識される自然(人間の外界)ではなく、知性的に理解される精神(人間の内面)を重視するようになります。その後、21世紀になると、このような人間中心主義的な芸術観(モダニズム)は限界を迎えて、上述のとおりジョン・ケージが自然尊重主義的な仏教思想に感化されて芸術観を一変したことに象徴されますが、現代のSDGsの取組みのように人間中心主義への反省を背景とした価値観の変化(ポスト・モダニズム)はいち早く芸術表現に表れているのではないかと思います。

1980年代頃からポータブル・メディアの登場やインターネットの商用化等を背景として、聴衆が同じ空間で同じ音楽を共有していた音楽受容の在り方が大きく変化します。この点、大量生産という経済モデルが有効に機能していた1980年代頃までは、人々は皆と同じ人生を生きることを余儀なくされる没個性(大衆)的な時代(社会に敷かれたレールを走るエリートと、そこから脱線する不良の2極化を生む規格化された社会)でしたが、社会経済の高度化に伴って人々は皆とは異なる人生を選択できる個性(分衆)的な時代へとシフトします。それまで聴衆はコンサートホール等の非日常的な空間やラジオ等のマスメディアを利用して皆と同じ音楽を聴いてきましたが、カーステレオやウォークマン等のポータブル・メディアの普及によって日常的な空間で皆とは異なる個人の嗜好に合った音楽を聴くようになり(音楽受容のパーソナル化)、大型レコード店等では膨大な商品の中から個人の嗜好に合った商品を選び易くする必要性に迫られてファインダビリティを向上するための音楽ジャンルの細分化が進みます(音楽受容のカタログ化)。さらに、2000年代頃からは、動画配信サービス(YouTubeなど)や音楽配信サービス(iTuneなど)のオンラインサービスの開始及びPCやiPod等のデジタル・メディアの普及によって音楽がインターネットのバーチャル空間を流通するようになりますが(音楽受容のデジタル化)、これにより近代に確立された様々な「境界」が曖昧になって以下に挙げるとおり音楽受容の在り方にも革新的な変化をもたらします。前回のブログ記事で触れたとおり、芸能は神との交信を試みるシャーマニズムから発展し、「聖」(彼岸)と「俗」(此岸)の境界を超えるという神聖な機能を担ってきましたが(例えば、能舞台は彼岸と此岸を越境するための装置として機能するなど)、もともと芸術体験には「境界」を超えるという性質があるのではないかと思われます。
①クロスオーバーの潮流(ジャンルの越境)大型レコード店等のように音楽ジャンルによって売り場が物理的に区分けされるのではなく、動画配信サービス等のように異なるジャンルの音楽に触れ易い環境になるなど音楽受容の在り方が「所有」から「検索」へと変化し、これまで細分化されていた音楽ジャンルの境界(ハイカルチャーとサブカルチャーの境界を含む。)を超えてジャンルレスに作品の良し悪しで音楽を受容する傾向が顕著になっています(ジャンルからの解放)。これによりジャンルを越境するクロスオーバーの潮流が生まれ、ジャンルの帰属を判断するための音楽の歴史性や様式性等の要素は重要な意義を失い、音楽受容の多様化を背景として、音楽の目的性や性格性等の要素が重要な意義を持ち始めており、それは現代音楽(現代オペラを含む)を含む全てのジャンルの音楽に当て嵌まることではないかと思います。②クロスオーバーの潮流(メディアの越境)音楽がデジタル化したことにより、他のメディアとのコラボレーションが容易になったこと及びアナログ・メディア(コンサートホールやラジオ等)の片方向的な音楽受容からデジタル・メディア(インターネット等)の双方向的な音楽受容が可能となったことで、「音楽」(聴取)➟「音楽+映像」(視聴)➟「音楽+映像+ α」(参加)へと音楽受容のスタイルが多様化します(メディアからの解放)。これによりクラシック音楽に象徴されるような「作曲」-「演奏」-「聴取」が完全に分離されている音楽受容のスタイルばかりではなく、聴衆の自己承認要求を満たすような多様な音楽受容のスタイルを許容するミュージキング(例えば、聴衆が音楽を加工すること、聴衆が音楽を演奏すること、聴衆が音楽を演奏する振りをすることや聴衆が音楽付きの動画を制作することなど)等が増加しています。このような潮流は、音楽だけではなく演劇にも見られ、舞台と客席、フィクションとノンフィクション、役者と観客などの境界を曖昧にしたイマーシブシアターという演劇受容のスタイルが注目されており、芸術体験の在り方が根本的に革新されようとしています。③クロスオーバーの潮流(次元の越境)

原作及び映画では、漆原朔が秋吉台現代音楽セミナーに参加して、調性システムを使うと「既聴感」のある音楽(即ち、音の組合せパターン等が限られているので、シナプス可塑性の劣る聴衆にも理解し易いもの)しか創作できず、如何に「未聴感」のある音楽を創作するのかが現代音楽の課題であることを学びますが、現代の作曲家が現代の時代性を表現するための多様な音楽表現が可能となる新しい作曲技法(即ち、音の組合せパターン等が複雑になるので、シナプス可塑性の劣る聴衆には理解し難いもの)を求めるようになった結果、演奏会で採り上げられる曲のうち、存命中の音楽家の曲が占める割合は1918年時点で77%でしたが、1949年時点で18%まで激減し、現在では(クラシック音楽界に限った特徴的な現象として)存命中の音楽家の曲が全く採り上げられない演奏会が珍しくないという異常な状況に陥っています。これまで歴史的な名演、様々な改訂版や秘曲の発掘、ピリオド楽器及び奏法の復活、他のジャンルとのコラボレーションなど聴衆のシナプス可塑性の活発化を促すための様々な工夫が試みられてきましたが、現代の時代性を表現するための新しい芸術表現を次々に生み出すサブカルチャーの台頭に押され、歴史上の偉大な作曲家が残した傑作群のみを対象としている構造的聴取という音楽受容のスタイルだけでは行き詰まりを見せつつあると感じます。この点、上述のとおり音楽受容のスタイルが多様化するのに伴って感性的聴取も見直されるようになり、ジャンルの境界等を越えるクロスオーバーの潮流が本格化するにつれ、2000年代頃からポスト・ロック、ミニマル・ミュージックやアソビエントの影響等を受けてクラシックのアコースティックな音楽とエレクトロニカ(電子音楽)の手法を融合した「ポスト・クラシカル」が誕生し、映像との親和性が高いビジュアルな音楽はヒーリング音楽や映画音楽のような聴き易さもあって、幅広い聴衆から支持されています。このようにポスト・クラシカルは様々なジャンルや潮流を採り入れたブリコラージュ的な性格を持つ音楽であることからクラシック音楽のパンク革命と言われ、注目されています。
ポスト・クラシカルの特徴①聴きやすさ:日常的な空間で聴くための音楽性②エレクトロニカ:電子音を採り入れて拡がりのある音響性③クロスオーバー:他のジャンルとの融合による多様性
<黒衣、緑衣>中村蝶一郎、中村光
【演出】春虹(中村壱太郎)、西澤千恵、株式会社HERE
【脚本】横手美智子
【振付】我妻徳陽
【音楽】中井智弥(作曲 二十五絃筝)
大畑理博(挿入歌「源氏の歌」の歌)
大迫杏子(テーマ曲「光の花」の作曲)
【衣裳】前神光太
【撮影】諸橋和希、松島翔平、江口佑、三好宏弥、岩田将昌
【音響】藤本和徳
【バーチャルプロダクションスタジオ技術】
高松倫芳、大木遼太、Konstantin Yanchev、稲田明徳、尾崎大輝
【テクニカルディレクター】土井昌徳
【3D背景制作】Sankaku△
【バーチャルセット開発】BASSDRUM
【BGセットアップ】渡邉渉太郎、長澤知宏、佐藤裕将
【CG・システムエンジニア/オペレーター】原田康(huez)
【BG制作進行】吉田華佳
【制作総指揮】井上貴弘、青木崇行
【制作】ミエクル株式会社、松竹株式会社
【感想】ネタバレ注意!

昨年10月、Facebookが社名をMeta Platformsに変更すると発表しましたが、今後、メタバース(仮想空間)の構築に社運をかけるという意気込みが伝わってきます。松竹もライブビューイングやイマーシブシアターなど新しい芸術体験を提供する試みに意欲的に取り組んでいますが、史上初のメタバースを使った歌舞伎公演「META歌舞伎 Genji Memories」がオンライン配信されたので、心躍る気持ちで視聴することにしました。歌舞伎俳優の演技(現実空間)とCGを使った舞台措置(仮想空間)をリアルタイムで合成して配信することにより、平安時代にタイムスリップしたような没入感のある舞台を楽しむことができます。この作品では、中村隼人が光源氏を、また、中村壱太郎が葵の上、六条御息所、夕顔、藤壺(声のみ)、玉鬘(声のみ)の五役を演じ、四季折々の情景に合わせて男女の「出会い」(春)、「恋」(夏)、「衝突」(秋)、「別れ」(冬)をテーマに書き下ろされた台本を使用して台詞劇と歌舞劇から構成された幻想的な舞台です。本番当日の撮影は代官山メタバーススタジオで行われ、CGを使った映画撮影でもお馴染みのグリーンバックを使用し、歌舞伎俳優はCGを使った舞台装置(仮想空間)をモニターで確認しながらグリーンバックで演技する形で進められました。歌舞伎は、日本画の特徴と同じく、三次元の空間を二次元的に見せる舞台に特徴(独特の美意識)がありますが、メタバースを使った歌舞伎公演では逆に奥行きを有効に使うことにより没入感のある舞台、即ち、舞台と客席を隔てるのではなく、その境界を超えて観客が現場で目撃しているような舞台ならではの臨場感のある演出が行われています。2点ほど気になったのはCGを使った舞台措置(仮想空間)が十分に写実的とは言えなかった点(但し、これは上述のとおり歌舞伎の舞台特徴を意識したものである可能性がありますので失当な感想かもしれません。)及び歌舞伎俳優の演技(現実空間)とCGを使った舞台措置(仮想空間)をリアルタイムで合成していたことからその輪郭処理が甘くなってしまった点は今後の課題ではないかと思います。しかし、六条御息所の女の情念が文字として仮想空間に漂う視覚的な演出はメタバースならではの劇的な効果であり、これまでの観劇にはなかった芸術体験として非常に興味深く、今後のメタバースによる舞台表現の深化に期待したいです。なお、メタバースではなく朗読劇(音声のみ)ですが、「META歌舞伎 Genji Memories」の序章・藤壺の章が公開されています。
◆おまけ
無調の荒野を彷徨うクラヲタを約束の地へと導く西村朗「現代の音楽」(NHK-FM)に肖って、ラジオ、演奏会や雑誌等で採り上げられた20世紀後半から21世紀前半までの現代音楽のうち、現代音楽の入門に適していると思われる聴き易い曲を紹介します。
ミニマル・ミュージックやトーン・クラスター等の影響を受けながらロマン派的な作風に仕上げられた比較的に聴き易い音楽で、全英ヒットチャートで6位にラインクインした異例の経歴を持つ20世紀を代表する交響曲です。クロスボーダーの潮流を受けて、ペンデレツキ@ポーランド国立放送交響楽団がソプラノ独唱に代えて英ロックバンド「ポーティスヘッド」のヴォーカリスト、ベス・ギボンズをソリストに迎え、そのソウルフルな歌唱によって祈りの歌詞に新たな生命を吹き込み新境地を開いた名盤をお聴き下さい。
★シュニトケ「合奏協奏曲第2番」(1982年)
今年最初の「現代の音楽」の放送で採り上げられていたシュニトケ。シュニトケはショスタコーヴィチを影響を受け、その作品を親友のクレーメルらが積極的に録音したことなどにより日本でも広く認知されています。当初、シュニトケは映画音楽の分野で活躍していましたが、その後、芸術音楽(メインカルチャー)と軽音楽(サブカルチャー)の融合を目指して「多様式主義」を確立します。上述のとおりジャンルが細分化していた時代に、今日的なジャンルレスの潮流を先取りしています。
★ベリオ「レンダリング」(1990年)
ベリオの「シュマン」(ケルン西ドイツ放送交響楽団)が2021年度レコードアカデミー賞(現代曲部門)を受賞しましたが、ベリオは既成曲の補筆等にも力を入れます。第29回渡邉曉雄音楽基金音楽賞を受賞した鈴木優人が2020年11月の読響定期でベリオの「レンダリング(修復)」を採り上げて話題になりましたが、シューベルトの交響曲第10番ニ長調(D.936a)の断章にシューベルトの音楽(19Cの響き)を補筆するのではなく自らの音楽(20Cの響き)を繋ぎ合わせてコラージュ風に修復(レンダリング)しています。
★アデス「イン・セブン・デイズ」(2008年)
ラトル@BPOがアデスの作品を積極的に採り上げて注目されるようになり、2018年にMETライブビューイングでアデス「皆殺しの天使」が上演されたことで一気に知名度がアップします。日本では「現代の音楽」のテーマ曲として知られる曲ですが、第29回渡邉曉雄音楽基金音楽賞を受賞した鈴木優人が2021年10月の読響定期で日本初演しています。この曲は音楽に加えて映像で聖書の天地創造の物語を描いた作品ですが、上述のとおり21世紀年以降の技術革新で音楽は「聴取」するものから「視聴」するものへと変化してきています。
★リヒター「November」(2019年)
ポスト・クラシカルの第一人者であるマックス・リヒターは、ベリオの弟子でピアノアンサンブル「Piano Circus」のメンバーとしても知られています。ポスト・ロックの影響を受け、クラシックのアコースティックな音楽とエレクトロニカ(電子音楽)の手法を融合した「BLUE NOTEBOOK」でポスト・クラシカルという言葉を最初に使用した現代作曲家です。ミニマル・ミュージックやアソビエントの要素等を採り入れ、映像との親和性が高く、心象風景を想起させるようなビジュアルな音楽です。


