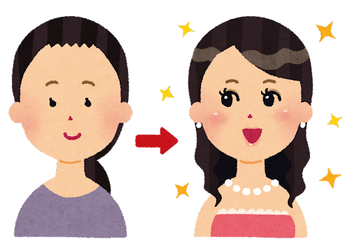
▼カオスとコスモスの狭間で生まれる美(ブログの枕前半)
7月を意味する英語「July」(ジュライ)は、古代ローマの英雄的な将軍「ユリウス・カエサル」(英語名:ジュリアス・シーザー)の誕生日が7月であることから「lulius」(ユリウス)に因んで命名されたと言われています。ユリウスは、古代エジプトの女王・クレオパトラの愛人だったと言われていますが、パスカルが著書「パンセ」で「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、世界の歴史も変わっていたであろう」と評するほどの絶世の美女であったというのが定説で、楊貴妃及びヘレネ―(日本では小野小町)と並ぶ世界三大美人に挙げられています。しかし、古代エジプトの建物は日照や砂埃を避けるために窓が小さく造られており屋内は薄暗く顔の造形がはっきり見えなかったと言われていますので、薄暗がりでも目立つ化粧や美声、教養で男性を虜にしていたという説もあります。クレオパトラの化粧法は、マラカイト(孔雀石)やラピスラズリ(青金石)などの宝石を砕いた粉を目の周りに塗布するもので、魔除けや目の感染症の予防の意味もあったそうですが、薄暗がりでも目が大きく見えて自分の美しさを際立たせるものとして世界で最初にアイラインやアイシャドウを利用したのがクレオパトラと言えるかもしれません。その意味では「クレオパトラの化粧がもう少し下手だったら、世界の歴史も変わっていたであろう」というのが実際だったかもしれません。現代でも、歌手や俳優が遠くからでも目、鼻や口など顔の造形がはっきりと見えるように行う舞台化粧は同じような機能を果たしています。しかし、キリスト教が国教化された中世ローマでは、化粧することは「七つの大罪」のうち「傲慢」にあたると考えられ、一時、化粧は行われなくなりました。この点、コロナ禍に伴うマスク着用で日本人の化粧の頻度が40%以上も減少したそうですが、化粧を身嗜みと考える現代的な価値観に照らせば、化粧をしないことは「七つの大罪」のうち「怠惰」にあたると言えるかもしれません。なお、「cosmetic」(コスメティック、省略してコスメ:化粧品)という言葉は、元々は「kosmos」(コスモス:宇宙が生まれた後の調和された秩序ある状態)を語源とし、「chaos」(カオス:宇宙が生まれる前の混沌として乱れた状態)を「kosmos」に戻すものという語感が含まれています。その意味で「to apply cosmetics」(化粧する)という表現は、年齢と共に「chaos」になって行く容姿を化粧を施して何とか「kosmos」に戻そうとする試みをイメージさせるものであり、その化粧のノリに歳月と共に移ろう「chaos」と「kosmos」の鬩ぎ合いの様子が現れる小宇宙と言って良いかもしれません。個人的な理解では、本当の「美しさ」(kosmos)とは、単に容姿に優れ、化粧が巧みであるという表面的な美しさだけを言うのではなく、その人の生き様が仕草、表情や心根等になって現れる美しさ(調和のとれた生き方)のことを言い、ワックスで装った表面の光沢ではなく軽石で磨き上げた内面から滲み出てくる艶のようなもの(老木の花、枯淡の美)ではないかと考えます。故・黒沢明監督の遺稿を元にした映画「雨あがる」(第56回ヴェネチア国際映画祭緑の獅子賞を受賞)に「真実な人々」という台詞が出てきますが、本当に美しい人々を見分けられる心の審美眼のようなものを備えた人間になるべく心掛けていますが、人生は侭なりません。
▼ヘンデル作曲のオペラ「ジュリオ・チェーザレ(英語名:ジュリアス・シーザ)」(1724年)1711年、オペラ「リナルド」で華々しくロンドン・デビューを果たしたヘンデル(英語名:ハンデル)は、ロンドンでオペラ作曲家として活動しますが、1724年にドイツからイギリスへ帰化し、この年にオペラ「ジュリオ・チェーザレ(英語名:ジュリアス・シーザー)」を初演します。2020年4月に新国立劇場で上演される予定であったオペラ「ジュリオ・チェーザレ(英語名:ジュリアス・シーザー)」はコロナ禍の影響で上演延期されていましたが、満を持して2022年10月に上演することが決定されています。

▼隠すと彩るの狭間で生まれる美(ブログの枕後半)
日本の化粧は、宗教儀式や戦闘等において顔や身体に施した装飾が起源と言われており、日本最古の物語である竹取物語(五.火鼠の皮衣)に「化粧」(けさう)という言葉が登場することから平安時代には身嗜みとしての化粧も行われていたと考えられます。化粧の「化」(かする)は「イ」(人の形)+「ヒ」(人の形を反転させたもの)から「別のものになる」という語義を持ち、例えば、「花」(草が別のものになる)、「靴」(革が別のものになる)、「訛」(言が別のものになる)等の言葉としても使われています。また、化粧の「粧」(よそおう)は「米」(白粉)+「庄」(神の依代となる柱)から「無垢を装って神を迎え入れる」という語義を持ち、神や敵を誑かすというニュアンスが含まれています。当初、身嗜みとしての化粧は女性のみが行っていましたが、平安時代末期になると虫歯で歯が黒かった後鳥羽上皇に配慮した公家(男性)が女性を真似てお歯黒をつけるようになり、やがて昇殿(上皇や天皇への拝謁)を許される五位以上の官位の者のみがお歯黒をつけることを許され、昇殿を許されない六位以下の官位の者はお歯黒をつけることを許されずに「白歯者」と呼ばれて身分の低い者と見做されるようになりました。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公・北条義時の三男・北条重時が遺した「北条重時家訓」に化粧(けはふ)という言葉が登場しますが、人前に出るときは化粧をして身嗜みに気を配らなければ人から侮られるという教訓を伝えており、公家(男性)と同様に武家(男性)も化粧する習慣があったことが窺がえます。この点、前回のブログ記事で触れましたが、平安時代から鎌倉時代、室町時代は王朝文化から武家文化へ移行する時代の過渡期にあたりますが、武家も王朝文化を採り入れてお歯黒をつけるようになり、とりわけ戦場に屍を晒すことになっても身分の低い者と侮られたくないという武家の意地から身嗜みに気を配りお歯黒をつけて出陣したと言われています。さらに、映画「関ケ原」でも描かれていますが、武家の子女は敵の首級を洗い、お歯黒をつけて首化粧を施すなど首実検で敵将らしく立派に見えるように整えたと言われており、現代でも「首を洗って待っていろ」と啖呵を切ったり、また、ご遺体に死化粧を施すのは、その名残りと言われています。因みに、過去のブログ記事でも触れましたが、日本のお歯黒と同様に、16~18世紀頃のヨーロッパの王侯貴族や裕福層の間ではペスト菌を媒介するノミやシラミの予防のために短髪にしてカツラをかぶる習慣が生まれ、その後、梅毒に罹患すると発症する円形脱毛症を隠すためにカツラが流行します。また、天然痘の傷跡等を隠すためのツケボクロをつける習慣や白髪隠しのために頭髪やカツラに小麦粉や米粉を混ぜ合わせた白い髪粉を降り掛ける習慣等も流行し、やがてこれらが上流階級であることを示すステータスシンボルと見做されるようになりますが、化粧には「隠す」(自己隠蔽)と「彩る」(自己解放)という一見矛盾する2つの要請を同時に叶える魔力のようなものがあると言えそうです。因みに、ヨーロッパの社交界で女性が着飾るイブニングドレス(バックレスドレス)の背中が大きく開いている理由は、梅毒に罹患すると発症するバラ疹がないことを示すために始まったと言われており、「隠す」(自己隠避)という実用的な機能と共に「彩る」(自己解放)という創造的な機能を持っている化粧やファッションは自己実現を図るための重要な自己表現の1つであると言えます。この点、コスメ業界と並んで、現代を表現し、未来を創造するアパレル業界で活躍するデザイナーには、その思想や生き様等を含めて共感、刺激される人が多く存在していますので、この機会にファッションがどのように時代をデザイン(革新)してきたのか、また、その時代を音楽がどのように表現してきたのかを簡単に触れてみたいと思います。なお、現在も営業を継続している化粧品メーカーのうち、ヨーロッパでは、1221年にサンタ・マリア・ノヴェッラ(伊)、1709年にファリナハウス(独)、1790年にディー・アール・ハリス(英)、1798年にゲラン(仏)が創業し、その後、1910年にシャネル(仏)や1946年にディオール(仏)などが創業していますが、これらの化粧品メーカーが提供する化粧品は非常に長い歴史の中で人々を魅了し続け、人々から愛され続けています。また、日本では、1615年に創業した柳屋本店が最古ですが、その後、1790年に伊勢半、1872年に資生堂が創業しており、ヨーロッパの化粧品メーカーと比べても遜色のない歴史と伝統を誇っています。この点、コロナ禍前までは上述のとおり長い歴史と伝統を誇り品質に優れた日本の化粧品が中国人観光客のお土産として持て囃されていましたが(日本人は月平均5000円前後を化粧品に費やしているそうですが、中国人は美容に関心が高く月平均1万5000円前後を化粧品に費やしていると言われています。)、最近では価格に優れた韓国の化粧品に人気を奪われており、コロナ禍や円安を契機として化粧品だけではなく各分野で日本経済のプレゼンス低下が懸念され始めています。
| ①女化稲荷神社(茨城県龍ケ崎市馴馬町5387) ②牛久大仏(茨城県牛久市久野町2083) ③蚕影山神社(蠶影神社)(茨城県つくば市神郡1998) ④富岡製紙場(群馬県富岡市富岡1-1) ⑤化粧坂切通し(神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-14-7) |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
| ①女化稲荷神社/女化神社には男に助命された狐が美しい女に化けて妻になり3人の子供を設けますが(お稲荷さんの3匹の子狐)、やがて正体を知られて姿を消したという狐の恩返し伝説があり、奥の院は狐が姿を隠した場所と伝わっています。美しい女に化けたという伝承から江戸の芸者衆が参詣し、化粧が上手くなるコスメの神様として女性の信仰を集めています。 | ②牛久大仏/女化稲荷神社の近くには三千世界を見守る牛久大仏(地上高120m)が安置されていますが、銅像としては日本第1位及び世界第4位の大きさを誇っています。昔から人間は大きいもの、強いもの、美しいものへの変身願望がありますが、それが民間伝承、銅像、アニメーション、映画やファッションなどのメディアを使って表現されています。 | ③蚕影山神社(蠶影神社)/牛久大仏の近くにある筑波山の山麓には、養蚕、製糸及び機織技術が日本に伝来した地として筑波国造が創建した蚕影山神社(蠶影神社)があり、全国の蚕影神社の総本社となっています。インドの金色姫が乗る船が常陸国豊浦へ漂着し、これらを伝承したとする伝説が残されており、ファッションの神様として信仰を集めています。 | ④富岡製紙場/19世紀半、ヨーロッパでは養蚕の疫病が蔓延して絹産業が壊滅的な被害を受けますが、その疫病に対する耐性を持ってた日本の蚕と生糸を輸入してヨーロッパの絹産業は復活し、その後のオートクチュール文化が華開きます。この頃、1872年にフランスの技術を導入し、当時世界最大級の規模の器械製糸工場として 富岡製糸場が設立されます。 | ⑤化粧坂切通し/大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」でも紹介されていた鎌倉七切通しの1つで、平氏の武将に死化粧して首実検した場所であることが名前の由来。後年、鎌倉幕府(執権・北条氏)を滅亡させた新田義貞は化粧坂切通しから鎌倉へ攻め入ろうとしますが失敗し、引潮を利用して稲村ケ崎から迂回して鎌倉へ攻め入ったと言われるほどの要衝です。 |

▼人類の移動が生んだファッションと芸術
昔から「衣食足りて礼節を知る」と言いますが、この言葉の出典(中国春秋時代の思想書「管子」(牧民)にある「倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。」という言葉)を紐解けば、生活の三大要素「衣食住」のうち、「食」が満ちれば礼儀や節度を弁える理性が生まれ、「衣」が満ちれば栄誉(ファッションの「彩る」(自己解放)の機能)や恥辱(ファッションの「隠す」(自己隠蔽)の機能)を感じる感性に目覚めるという趣旨だと解されます。生活の三大要素に「衣」が含まれている理由は、人間の生命維持に最も重要なものが「衣」であると考えられているためです。過去のブログ記事で触れましたが、約5億年前に生細胞が植物と動物に分化する際、植物は移動せずに太陽光を利用して自らエネルギーを作り出すことを選択したのに対し、動物は移動して他の生物を捕食しエネルギーを摂取することを選択します。さらに、動物は、恒温動物と変温動物に分化しますが、恒温動物は他の生物をより多く捕食するために広い範囲を移動する必要から体温が外気温の変化に左右されず活動を継続できる生理機能を持つようになり、また、変温動物は体温が外気温の変化に左右されるために狭い範囲しか移動(例えば、ナマケモノは気温が安定する熱帯地域にしか生息できず、体温調整のために日向と日陰の僅かな範囲を移動)できない代わりに他の生物を僅かな量(例えば、ナマケモノは植物を10g/日)しか摂取しなくても生命維持できる生理機能を持つようになります。この点、人間が世界中の様々な場所で活動できるのは恒温動物であることの恩恵ですが、それに伴う外気温の急激な変化に対しては体温を一定に保つことが難しく生命維持が困難になる可能性があることから、約20万年前頃から防寒対策のための「衣」(人間の体温調整を補うための毛皮や植物など)を着用し始めたと言われています。このことから「食」(他の生物をより多く捕食すること)のための「衣」(広い範囲の移動を可能にするもの)とも言え、人間の生命維持にとって「食」と「衣」は密接不可分な関係にあると考えることができますが、それが戦闘のための防護服や宗教儀式のための化粧(ボディーペイント)の延長としての装飾服として発展します。なお、生活の三大要素の「住」も寒暖や外敵などから人間を守るという重要な役割を担っています。今年は熱中症対策として適度なエアコンの使用が奨励されていますが、エアコン(冷房)は人間の発汗作用(液体の気化により熱を吸収する性質)を応用し、液体から気体に変化し易く熱を効率的に吸収する性質を持つ冷媒ガスを使って部屋の空気から熱を急速に吸収することで冷房しますが、これも「住」が実現した発明と言えます。高齢者が熱中症を発症し易いのは若者と比べて発汗作用が衰えているためですが、その衰えをエアコンが補っており、益々「住」の重要性が増していると言えそうです。
▼オネゲル作曲の交響的断章第1番「パシフィック231」(1923年)鉄道オタクだったオネゲルが蒸気機関車を音楽的に描写したメカニカルな曲です。上述のとおり人間は他の動物を捕食するために広い範囲を移動する必要がありましたが、過去のブログ記事でも触れたとおり、約7万年前の認知革命(脳の突然変異)によって人間は想像力を手に入れ、それに伴う好奇心や気候変動、縄張争い等を契機として大移動を開始します。天気予報と同じですが、人間の脳は生存確率を高めるために「知覚」(現在の情報を収集)+「記憶」(過去の情報を記録)=認知(現在の情報と過去の情報を照合して未来を予測)しますが、移動による新しい知覚や学習による新しい記憶が組み合わさると(シナプス可塑性が活発化)、これまでにない認知が生まれ易くなり(俗に世界が広がる)、それが豊かな創造性を育むようになります。人間の脳は生存確率を高める必要性から、新しい知覚や新しい記憶が不足すると「飽きる」という状態の陥り、旅行に出たり、新曲を聴いたり、お稽古事を始めたり、新しい知覚や新しい記憶を求めるようになります。
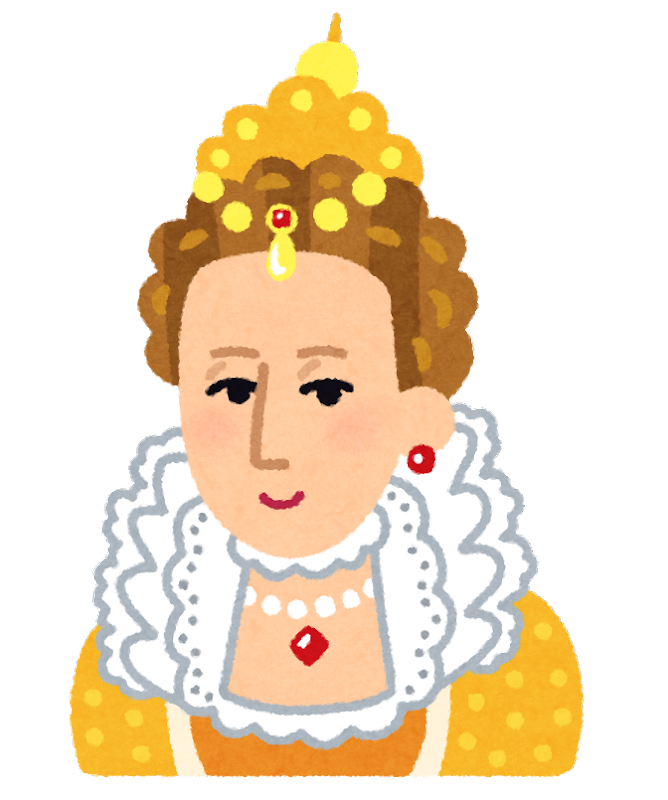
▼ファッションの誕生(ルネサンス)
上述のとおり中世のキリスト教社会では神が自らの姿に似せて造ったという人間の身体を化粧やファッションで着飾ること(虚飾)は傲慢の罪にあたると考えられていましたが、十字軍の遠征失敗や宗教改革によってキリスト教権威が失墜してキリスト教的な価値観から解放されると(過去のブログ記事)、人間性を再発見するルネサンスが勃興して、神(キリスト教権威)が支配する時代から人間(絶対王政)が支配する時代へと転換します。これに伴って科学が宗教の足枷から解放されてキリスト教が禁じていた解剖学が盛んになり(過去のブログ記事)、人間の身体が三次元的に把握されるようになると、人間の身体の構造や骨格の動き(人間工学)に配慮した立体的なデザインの服が作られるようになり(1951年、デザイナー・森英恵は米軍関係者の夫人が着用している服から、平面的(二次元的)にデザインされている日本の着物に対し、洋服は立体的(三次元的)にデザインされていることに気付き、その後、国際的に飛躍するキッカケとなります。)、これに伴って人間の身体に合わせて裁縫し服を作るための仕立屋が誕生し(ファッションの誕生)、やがて神ではなく自分を着飾るという感性が目覚めて、ファッションがイタリアからドイツ、イギリス、そしてフランスへと広がり、これに伴って化粧品メーカーも創業します。14~16世紀のルネサンス期は、未だ中世のキリスト教的な価値観が残り理性や協和を重んじるシンメトリーな世界観を維持していましたが、17世紀のバロック期になると時代に変化を求めるようになって感性や不協和を重んじるアシンメトリーな世界観を嗜好するようになり、他人と異なる個性的なファッション(左右が非対称となるデザインや豪華な宝飾品など)が目立つようになります。このような時代を背景として、イタリアで活躍していた作曲家・モンテベルディは、それまで音楽で重視されてきたキリスト教の教義(理性)を明確に伝えることよりも、人間の情感(感性)を豊かに表現することを重視して、当時、社会的に許容されていなかった不協和の使用に踏み切ります。また、複雑なポリフォニー(キリスト教権威が体現していた中世的な世界観である三人称の「I」(私)+「You」(教会)+「He」(神))による均整のとれたルネサンス音楽(教会旋法)から、人間性に富むドラマチックな表現が可能なモノフォニー(ルターの宗教改革を経て改められたバロック的な世界観である二人称の「I」(私)+「He」(神))を採用するバロック音楽(和声法)へと移行する契機となります。
▼モンテヴェルディ―作曲の「マドリガーレ集第5巻」(1605年)から第1曲「つれないアマリッリ」14世紀から16世紀のルネサンス期は未だ中世的なキリスト教的な価値観を残してシンメトリーな美(神が体現する完全な調和)を重んじる時代でしたが、やがて科学革命の影響等から、17世紀のバロック期はアシンメトリーな美(自然が体現する多様な変化)を重んじる時代になり、中世(~13世紀)が神を発見した時代であるとすれば、14世紀~17世紀は人間を発見した時代と言えそうです。このような美のパラダイムシフトが生じる17世紀、モンテべルディはマドリガーレ集第5巻第1曲「つれないアマリッリ」の第13楽章において不協和音程である属七の和音(ドミナント・セブン)を使用し、「不協和音程の予備の法則」を破り、突然、その不協和音程を響かせて人々に動揺を与え、理性を搔き乱すという当時の禁じ手を使用することで、これまでにない情感豊かな表現を可能にしました(過去のブログ記事)。その後、20世紀、シェーンベルクが「不協和音程の解決の法則」を破って調性システムの呪縛から音楽を解放します。後述するとおりファッションの歴史も色々なものから人間を解放して自由にして来た歴史と言えます。
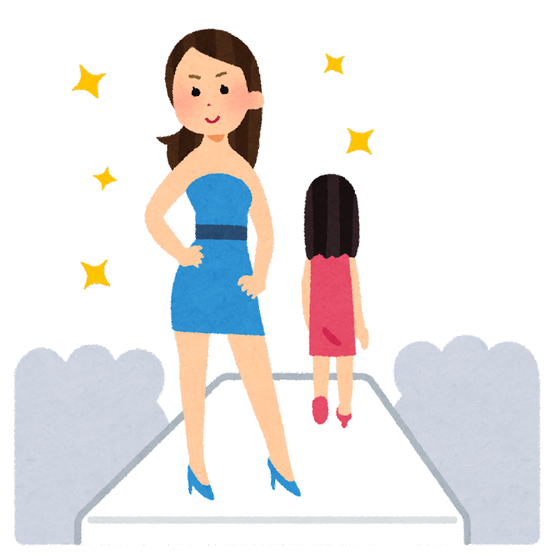
▼時代を定義するファッション(市民革命・産業革命)
上述のとおりルネサンス(14~17世紀)の勃興によりヨーロッパに啓蒙思想(キリスト教的な世界観に対して科学革命を背景とした合理主義的な世界観を説いてキリスト教会や絶対王政等の伝統的な権威を批判し、人間性を解放するために人間の理性により社会を革新する考え方)が広がって市民革命が勃発し、人間(絶対王政)が支配する時代から法律(プルジョアジー)が支配する時代へと転換します。これに伴って王侯貴族のもとで発展したファッションやその他の文化芸術はブルジョアへ受け継がれて大衆文化として華開くことになります。市民社会では、産業革命を背景として社会階級(ブルジョアジーとプロレタリアート)など色々なものがカテゴライズされるようになりますが、ジェンダーの社会的な役割についても男性は外で働く者として機能性を重視した規格化されたスーツを着用し、女性は家を守る者として装飾性を重視した変化に富む多彩なドレスを着用するという時代感覚が生まれます。丁度、この時代にピンク=女性らしい色というジェンダー意識も定着します(過去のブログ記事)。これまでのキリスト教会や絶対王政が体現する伝統的な価値観は永遠なものであり不変であるという世界観(古典主義)から、やがて市民社会が体現する革新的な価値観は常に移ろいながら変化するという世界観(ロマン主義)へと移行し(18~19世紀)、時代感覚の微妙な変化を捉えて着こなしやセンスの違いにこだわる繊細な美意識に彩られたファッションが流行します。このような時代を背景として、王侯貴族が愛好したオペラ・セリアから市民が親しみ易い喜劇性のあるオペラ・ブッファやオペレッタなどが誕生し(過去のブログ記事)、また、絶対王政の社会秩序が保たれていた時代を反映するように音楽の形式が重んじられ、近親調への転調等を使った明快な和声による調和的な響きを好んだ古典派音楽から、やがて自由主義や個人主義(近代的な世界観である一人称の「I」(私))を尊重する市民社会が形成されて行った時代を反映して人間の感情をより豊かに表現するために音楽の形式に縛られず、巧みな作曲技法による遠隔調への転調等を使った複雑な和声による個性的な響きに彩られたロマン派音楽が好まれるようになります。
▼ベートーヴェン作曲の交響曲第3番「英雄」(1804年)から第2楽章18世紀、ベートーヴェンはフランス革命を主導したナポレオンへのオマージュとして交響曲第3番「ボナパルト」を作曲しナポレオンに献呈する予定でしたが、ナポレオンが皇帝に即位した失意から献呈を取り止めて「エロイカ」と改題したという逸話が残されています。その一方で、ナポレオンは、ナポレオン法典を制定し、法の下の平等(封建制の否定)、所有権の絶対(絶対王政の基盤崩壊)や信仰の自由(宗教権威の基盤崩壊)などを規定し、その後の人の支配から法の支配への流れを作る一方で、この時代を象徴するジェンダーギャップ(男尊女卑)を規定して現代に大きな課題を残しています。これはベートーヴェンの「音楽とは、男の心から炎を打ち出すものでなければならない。そして女の目から涙を引き出すものでなければならない。」という認知バイアスに彩られた言葉にも色濃く影を落としており、現代とは大きく時代感覚が異なっていることを感じさせます。なお、この曲は、当時としては曲の長さ、構成やオーケストレーションなど非常に革新的な曲と言えますが、現代に置き換えて考えると、のだめカンタービレが流行した10年前と比べても時代は大きく変化しており(まだ10年前は伝統や権威に夢を見れた時代でしたが、最近のスタートアップ企業という言葉に象徴されるように時代の価値や興味は伝統や権威を上書きし、新しく時代を塗り替えて行けるものに確実にシフトしてきており)、もはや数百年前に作曲された古典派やロマン派の音楽を有難がって聴く時代感覚にはないという印象を否めません(過去のブログ記事)。この点、年末のイヴェントを含めて、いつまでもベートーヴェン頼みでは辛いものがあります。

▼時代を解放するファション(帝国主義・世界大戦)
上述のとおり市民革命及び産業革命(18~19世紀)を経て人間(絶対王政)が支配する時代から法律(ブルジョアジー)が支配する時代へと移行しますが、ブルジョアジーとプロレタリアートの社会格差が拡大し、プロレタリアートが過酷な労働条件下で搾取されるという社会の歪みが深刻化するなど自由で平等な市民社会の理想が破綻を来します。これに伴って世紀末思想に基づく退廃的・厭世的なムードが社会に広まり、これまで社会階級(ブルジョアジーとプロレタリアート)や性別(外で働く男性と家を守る女性)などをカテゴライズしてきた時代の価値観が揺らぎ始めます。このような時代を背景として、1858年、チャールズ・フレデリック・ワースは世界で初めて生地の選定からデザイン、仕上げまでをデザイナーが一貫して行うオートクチュール(高級仕立服)の仕組みを考案し、自らがデザインした服に自らのブランドエンブレムを縫い付けることで差別化を図るブランドビジネスを確立すると共に、自らのブランド服をモデルに着せて顧客に披露することを開始します(ファッションモデルの誕生)。これに伴ってデザイナーが上流階級の客の屋敷を訪ねて採寸を行っていたビジネススタイルを改め、上流階級の客にも自らの店舗(メゾン:オートクチュールの店、ブティック:プレタポルテ(高級既製服)及びこれとコーディネートする宝飾品等を販売する店)まで足を運ぶように求めたことにより自らのブランド価値を高めることに成功します(階級を誇示するためのファッションから個性を表現するためのファッションへ。但し、現代でもイギリスは階級意識が根強く残っています。)。また、この時期にはヨーロッパ各国で万国博覧会が開催され、その影響からヨーロッパ各国でジャポニズムが流行していますが、1893年、御木本幸吉が世界で初めて真珠の養殖に成功し、1913年、ヨーロッパやアメリカに事業展開したことにより、これまで上流階級しか身に着けることができなかった真珠(宝飾品)を中流階級も身に着けることができるようになりました(階級を誇示するための宝飾品から個性を表現するための宝飾品へ)。御木本幸吉は、エジソンから「私の研究所で作れなかったものが2つあります。その1つはダイヤモンド、もう1つは真珠です。あなたが生物学で不可能と考えられてきた真珠の養殖を発明したことは世界の脅威です。」という手紙を送られていますが、2012年、「World's Top 100 Most Valuable Luxury Brands」(世界ラグジュアリー協会)に日本から唯一「MIKIMOTO」が選ばれており、ファッション(宝飾品)を通してヨーロッパの社会に多大な影響を与えてきたことが窺えます。さらに、ジャポニズムの流行を受けてコミック・オペラ「ミカド」やオペラ「蝶々夫人」などが上演され、マダム貞奴(川上貞奴)が着ていた着物が異国情緒を湛える魅力的なファッションとして注目されました。ポール・ポワレは、日本の武士の妻が着用していた小袖から、女性はコルセットを使わなくても美しく装うことができることを発見し、1906年、コルセットを使わない部屋着「キモノドレス」、1909年、コルセットを使わない外出着「キモノコート」を発表して、かつてキリスト教が女性の胸の谷間を悪魔の隠れ家と呼び、女性の胸の膨らみをハシタナイと考えていたことにより開発されたコルセットから女性を解放します(過去のブログ記事)。しかし、ポワレは女性の上半身は自由にしましたが、その一方で「ホブルスカート」を考案して女性の下半身を拘束します。その後、各国が大量生産する商品の消費市場とそれを支えるための生産資源を確保するために植民地政策(帝国主義)を拡大したことで各国の利害が衝突して二度の世界大戦が勃発します。この世界大戦によって過去の社会秩序(キリスト教権威や絶対王政等の封建体制や、ブルジョアジーや男尊女卑等の格差社会を含む。)が崩壊すると共に、男性の労働力が不足したことにより女性の社会進出が進みます。1913年、ガブリエル・ココ・シャネルはブティックを開店して、コルセットを使わず、かつ、ホブルスカートのように女性の下半身も拘束しないスカートを販売して女性の上半身だけではなく女性の下半身も解放します。また、1916年、当時はチープな素材と考えられていたジャージーやトリコットの生地をハイファッションに使用して階級を誇示するためのファッションから機能性とファッション性を両立するファッションへ革新し、カジュアル・シックな服装やスポーティーな服装が女性の標準的なファッションとして確立します。さらに、1919年、それまで香水は単一の香料を使った型に嵌った香り(家を守る女性像のメタファー)でしたが、自由な精神を持つ女性の心に訴えかける型に嵌らない複雑で優雅な香りがする革新的な香水「Chanel N°5」を販売し、女性から圧倒的な支持を受けています。また、1920年、フェイクパール(天然真珠や養殖真珠とは異なり、プラスティックなどを使って作られたイミテーションの真珠)などを使ったコスチュームジュエリー(偽物)とファインジュエリー(本物)を組み合せた新しい宝飾品を販売してフェイクパール・ネックレスが流行し、本物志向の上流階級の価値観(階級を誇示するためのファッション)を時代遅れなものとして葬り去ります。さらに、活動的な女性に相応しいファッションとして両手を自由に使えるようにするために、ショルダーチェーンを付けた女性用のハンドバックを開発するなど女性の身体を解放するためにファッションを通して時代を革新しています。なお、1999年、雑誌「TIME」が公表した「Time100: The Most Important People of the Century」ではファッションデザイナーから唯一シャネルがエントリーされ、シャネルと親交があったストラヴィンスキーやピカソ等の名前も挙げられています。1937年、エリザ・スキャパレリは、香水「ショッキング」でショッキングピンクという新色を使用しますが、それまで女性らしい色(ジェンダーバイアス)として定着していたパステルピンクとは異なり、自己主張の強い華やかなショッキングピンクは女性のイメージを革新するものとして衝撃を与えました。なお、その香水瓶は女優のメイ・ウェストのボディーラインを象ったトルソー型をしていますが、後年、マドンナのコスチューム・デザインを手掛けたジャン=ポール・ゴルチエはスキャパレリへのマージュとしてその香水瓶を使用しています。また、サルバトール・ダリやジャン・コクトー等との協働によりシュールレアリズムや前衛芸術等のアートな要素をファッションに採り込んだ斬新で個性的なデザインの服を発表して話題となります。さらに、当時は工業品と認識されていたファスナーをファッションに採り入れた斬新なアイディアなどで時代の寵児となります。シャネルが女性の身体を解放したのに対し、エリザ・スキャパレリは女性の感性を解放します。1947年、クリスチャン・ディオールは、細く絞ったウェストとゆったりしたフレアスカートを特徴とする8の字型のフェミニンなライン(ニューライン)を発表してエレガントなファッション(女性の身体を解放するために切り捨てられたものを見直す試み)という新しい流行を作り、約半年毎に新しいラインのファッションを発表することでパリのモードサイクルを確立しパリのオートクチュール界の頂点に君臨します。因みに、1959年、美智子上皇后がご成婚時に着用したローブ・デコルテはディオールのデザインです。このような時代を背景として、これまでの主音(ブルジョアジー、男性、宗主国のメタファー)とこれによって規律される属音(プロレタリアート、女性、従属国のメタファー)から構成される調性音楽が行き詰まりを見せるようになり、この行き詰まりを打開するために主音からの解放を目指してリスト、ワーグナーやドビュッシー等が新しい世界観を表現するための新しい音楽を模索するようになります(過去のブログ記事)。やがてアルノルト・シェーンベルクが主音を設けずに1オクターブの中に含まれる12の音を1回づつ均等に使った音列(セリー)を組み合わせて作曲する十二音技法(無調音楽)を発明して調性システム(音楽のコルセット)から音楽を解放します。また、イーゴリ・ストラヴィンスキーは、シャネルと深い関係にあり多大な影響を与えますが(映画「シャネル&ストラヴィンスキー」)、民族音楽の本能的・野性的なリズム(バーバリズム)を作曲に採り入れて、これまで理性を重視して本能的な興奮を惹起するリズムの使用を避けてきたキリスト教的な価値観(音楽のホブルスカート)から音楽を解放します。さらに、ルイージ・ルッソロは、これまで理性によってコントロールできない響き(周期的な振動ではなく非周期的な振動からなる響き)の使用を避けてきたキリスト教的な価値観を見直して、機械文明や戦争等が発するノイズ(音楽のショッキングピンク)を音楽の素材として採り入れて人々の感性を解放します。なお、1950年代になると、ヤニス・クセナキス等は、十二音技法が複雑化して演奏や鑑賞が困難になっている状況を踏まえて、12音の全部が使用されていなくても一度使用した音譜を反復して使用することや音列に調性感を持ち込むことなど十二音技法を緩和して自由に作曲できるポスト・セリエリズム(音楽のエレガンス)への移行を図り、これに伴って無調音楽と調性音楽がボーダレスになり、ゲームソフト、アニメや映画等の商業音楽に幅広く現代音楽が使用されるようになります。
▼シェーンベルク作曲のピアノ組曲(1921年)シェーンベルクは、リスト、ワーグナーやドビュッシー等が新しい世界観を表現するための新しい音楽を模索した流れを汲んで試行錯誤を重ねますが、やがて「相互の関係のみに依存する十二の音による作曲法」として十二音技法を完成します。この十二音技法を使って最初に書かれた曲が「ピアノ組曲」(Op.25)になりますが、この曲はバロック舞曲の形式(方法)を借りながら12音技法を使って作曲することでバロック音楽とは全く異なる20世紀の時代性(世界観)を表現する音楽を作ることに成功しています。この曲は100年前の音楽であり、また、十二音技法は映画音楽、ゲーム音楽やポップス音楽等に採り入れられてきたことなどにより既に現代人の耳には斬新な響きには聞こえなくなっていますが、調性システムから音楽を解放して音楽の可能性を広げた功績は非常に大きいと思われます。20世紀がクラシック音楽不毛の時代と言われる状況になってしまった原因は、新しいものを受容できる教養力に恵まれなかった聴衆の質(僕を含む)と、その聴衆の質を高めて来れなかったクラシック音楽界の保守的な体質にあるのではないかという歴史認識が芽生えつつあります。

上述のとおり世界大戦は過去の社会秩序を崩壊し、女性の社会進出の足掛りとなりますが、世界大戦によって世界経済及び世界秩序の中心がイギリス(ヨーロッパ)からアメリカへ移行すると、アメリカのフォードシステムに象徴される大量生産・大量消費型の経済モデルが世界中に広がり、これを支える社会インフラと共にマス・メディアが発達して、1人1人の市民(個性)に着目するのではなく市民を没個性的な大衆(マス)として捉える大衆社会が到来します。とりわけ、アメリカはイギリス(ヨーロッパ)のように王侯貴族が存在せず階級社会ではないことから本格的な大衆社会が発展しますが、(産業革命による労働力不足を解消するためにアフリカ大陸で奴隷売買が行われた歴史的な経緯を経て、奴隷解放運動及び南北戦争等による奴隷解放後も)レイシズムという社会の歪みが生じます。その後、社会経済が高度に構造化すると、都市には無機質に反復する機械音や電子音が溢れ、ルーティンな日常が続いて人々は文脈や背景のない人生を送るようになります。このようななか、1962年、イヴ・サン=ローランは、クリスチャン・ディオールに才能を見出されて頭角を現し、自らのブランドを立ち上げて目新しいデザインを次々と発表したことで「モードの帝王」と呼ばれます。この時代は女性が社交の場でパンツスーツを着るのはタブー視されていましたが、男性が着るタキシードを女性用に仕立てたパンツスーツを発表したことで一気に普及します。イヴは「シャネルは女性に自由を与えたが、僕は女性にパワーを与えた。」と語っていますが、ファッションで女性の社会進出を後押しします。また、イヴは有色人種の美しさを讃えて初めて有色人種のモデルを起用し、男女平等だけではなく多文化主義も後押ししています。イヴの名言の1つに「ファッションは廃れても、スタイルは廃れない。」という言葉がありますが、最先端の流行がモードであり、それが社会に広く受け入れられてファッションとなり、やがてファッションが生き方として定着してスタイルになるということであり、ファッションは単に時代を解放するだけではなく社会を革新して時代を更新する力があることを示した偉大なデザイナーと言えます。1958年、マリー・クヮントは、ストリートファッションからヒントを得てミニスカートを販売して大流行し、また、ウォータープルーフ(涙でも落ちない防水仕様)のマスカラを開発したことで女性の感情を解放します。また、1963年、ヴィダル・サスーンは、ミニスカートとの相性がよくセットが不要なボブカットを開発し、女性が気軽に外泊できるようになったことで女性の性を解放します。これらによって女性の意識や活動は変革され、また、上流階級から発信されるファッションではなくストリートから発信されるファッションという革新的な社会現象を巻き起こします。なお、1967年10月18日、ミニスカートのファッションアイコンとしてモデルのツイッギー・ローソンが来日したことから、以後、日本では10月18日はミニスカートの日とされています。さらに、1975年、ヴィヴィアン・ウェストウッドは、パンク・ロックバンド「セックス・ピストルズ」(自らのブティック店「SEX」の従業員や常連客からなるバンド)をプロデュースし、挑発的・攻撃的なパンクスタイルを流行させて「パンクの女王」と呼ばれるようになります(映画「ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス」)。1980年代前後からデザイナーは服よりも時代が求める人間像(コンセプト)をデザインする傾向を強めています。1975年、ジョルジオ・アルマーニは、男性用スーツを従来の堅い生地ではなく柔らかい生地で作ってセクシーに見えるように改良することで男性に遊びや艶のある人生(コンセプト)を提案し、また、女性用スーツを従来のワンピーススタイルだけではなく上質な生地で作る高級テイラーメイドスタイルのものを追加することで女性に高い社会的なステースで活躍する人生(コンセプト)を提案します。さらに、1987年、ジル・サンダーは、人生の虚飾を排して本質を浮き彫りにするファッションというコンセプトを掲げ、装飾の少ないシンプルなデザインでありながら素材や裁縫のクオリティと機能性を両立した服を作って「ミニマリストの女王」と呼ばれ、一時期、「UNIQLO」の商品等も手掛けていました。現代のように「夢」を持たなくなった時代に、文脈や背景を持たない人間が人生で大切なものを見極めて「楽しむ」という肩肘張らないライフスタイルを送るうえで求められるファッションと言えるかもしれません。21世紀になると、インターネットやSNSなどのナノメディアが普及し、市民を没個性的な大衆(マス)として捉える大衆社会ではなく、1人1人の市民の個性に着目してその多様性(ダイバシティー)を尊重する市民社会へと成熟して行きます。このような時代の潮流を先取りするかのように、1980年、カルバン・クラインは、ブルックシールズをモデルに起用して宣伝したデザイナーズ・ジーンズが流行して、ユニセックスなファッションを先取りしてジェンダーを解放します。また、ジャン=ポール・ゴルチェは、1980年代にメンズコレクションで「男性にはスカートをはく自由がある」と公言して男性のスカートファッションを提案して、ファッションモデルに老人、肥満、タトゥー、ピアスなど個性的な人間を揃えるなど多様な人間像を先取りしてマイノリティーを解放します(来年、ゴルチェの半生を描いたミュージカル「ファッション・フリーク・ショー」が公演予定)。やがてファッション業界では複数のブランドを束ねるコングロマリットが台頭し、ファストファッションという商品サイクルが短いジャンルが登場します。ファッション業界に限りませんが、世界中の都市はコングロマリットのフランチャイズで埋め尽くされ、その結果、世界中の都市はその特色を失ってどこでも同じように見える都市が出現します。この背景には、情報化社会の進展によって価値観が多様化し、時代を仕掛けるビジネスではなく、時代を捉えるビジネスへと変容してきていることが挙げられるのではないかと思います。ファッションブランド「ZARA」を率いるアマンシオ・オルテガは、カリスマデザイナーを立てずに程よく流行を採り入れた手頃な価格帯の服を店頭に並べて、売れない服は直ぐに店頭から引き揚げるなど客の反応をいち早くフィードバックする「ファストファッション」で世界のファッション市場を席捲していますが、最近は地球環境破壊の温床として槍玉にあげられるなどその勢いに陰りが見え始めています。また、ラグジュアリーブランド「ケリング」を率いるフランソワ=アンリ・ピノーは、ミレニアルズ世代の若い客は伝統や職人技術といった重みよりも感情に訴える創造的な表現を求めていると考えて、仮に一部の顧客を失っても本物の創造性を発揮する「クリエイティブ・リスク」をテイクする戦略に切り替えています。さらに、2015年、ケリングの傘下にあるファッションブランド「GUCCI」を率いるアレッサンドロ・ミケーレは、ファッションは生きづらい世界を少しでも生きやすくするためのアイディアであるとして、ジェンダー・フルイディティ(ジェンダーの流動性)のコンセプトを掲げ、ジェンダーの境界線を感じさせないファッションを発表して注目を集めており、ファッションによってジャンダーを解放しています。なお、日本は1872年に服制改革により洋装が採り入れられ、和装と融合しながら日本独自の服飾文化を形成します。1965年、森英恵(モデルの森泉は孫)は、蝶をモチーフにしたエレガントなドレスでニューヨーク・コレクションに参加して「マダム・バタフライ」の異名で話題になり、1977年、パリのオートクチュール組合からアジア人として初めて会員に認められています。また、1973年、三宅一生は、服の原点である一枚の布で身体を包むというコンセプトのもと、西洋や東洋に捕らわれない世界服のデザインでパリ・コレックションに参加し、フランスの芸術文化勲章最高位コマンド―ル等を受賞しています。故スティーブ・ジョブズは、iPhoneの意匠に通じるシンプルなデザインが持つ機能美に魅せられていましたが、三宅一生の黒いセーターを愛して彼のトレードマークとしていたことは有名です。さらに、舘鼻則孝は、花魁が履いていた高下駄に着想を得て踵のないヒールレスシューズを考案し、2010年からレディー・ガガの専属シューメーカーとなりました。このような時代を背景として、1960年代になると大衆社会を反映するように、ヘンリー・カウエルが考案したトーンクラスター(十二音技法のように1つ1つの音の音程関係を重視するのではなく、1つの音塊(サウンド・マス)として捉えて、ある2つの音の間を響きで埋め尽くす密集音群による音楽)やジェルジ・リゲティが考案したミクロポリフォニー(細かく分割された楽器パートが各々異なった動き(分業)を行いながら、それらが1つのまとまった雰囲気(社会、集団)を織り成す音楽)など新しい作曲技法が注目を集めました。また、アメリカでは、歴史的に王侯貴族が存在しなかったこと(大衆文化)や、大航海時代及び植民地政策(帝国主義)によってもたらされた異文化接触の増加とこれを背景とするレイシズムという社会の歪みを生んだこと(黒人文化)などを契機として多様な文化芸術が育まれ、様々なポピュラー音楽(ミュージカル、ジャズ音楽、ロック音楽、ラップ音楽等)が発展します(過去のブログ記事)。さらに、様々なイノベーションを背景として、ミュージックコンクレート(既存の音の発生原因や意味等を省みず物語性や目的性を持たない響きのみを重視し、最初に出てくる既存の音を主題として様々なリズムで展開する音楽)、電子音楽(ロック、ポップス、ゲームや映画等の商業音楽に幅広く採り入れられ、大衆消費社会を背景として騒音問題に配慮して消音機能を備えた電子楽器として一般人にも普及)、スペクトル音楽(レコード芸術が普及したことにより音楽の受容シーンが多様化し、五線譜上の音程で表すことが困難な多様な微分音(半音以下の音)等の周波数を解析して音程に置き換える音楽:ジャン=ポール・ゴルチェの考え方と親和性)、コンセプチャリズム(音楽を社会との関係性の中で捉え直そうという試み)など多様な音楽表現が生まれると共に、サウンドデザイン(騒音対策として日常の音をコーディネートする音楽)、サウンドマップ(バリアフリーとして視覚障害者のための音楽:アレッサンドロ・ミケーレの考え方と親和性)、サウンドスケープ(防犯等を企図して音をアレンジするなどユニバーサルデザインを行う音楽:三宅一生の考え方と親和性)やウェルビーングミュージック(ウェルビーイングにアプローチする音楽:アレッサンドロ・ミケーレの考え方と親和性)など多様な音楽受容も生まれます(過去のブログ記事)。また、社会経済の構造化に伴って日常がルーチン化するようになった1960年代には、ラ・モンテ・ヤングらが最小単位のモチーフ(日常、機械音)を反復するミニマルミュージックを考案して注目を集め、また、社会経済が成熟して誰でも豊かさを享受できるようになった1970年代には、ブライアン・イーノらが日常に音楽が溢れるようになったことを踏まえて「聴く」という行為を強要しないアソビエント(環境音楽)を考案して注目を集めます。2006年、マックス・リヒターは、ポスト・ロック、ミニマル・ミュージックやアソビエントの影響等を受けて、クラシックのアコースティックな音楽とエレクトロニカ(電子音楽)の手法を融合したポスト・クラシカルを考案し、映像との親和性が高いビジュアルな音楽はヒーリング音楽や映画音楽のような聴き易さも手伝って幅広い聴衆から支持されています。このようにポスト・クラシカルは様々なジャンルを採り入れたブリコラージュ的な性格を持つダイバシティな音楽とも言えそうです。このように見てくると、宗教権威に抗ったモンテヴェルディ、絶対王政に抗ったベートーヴェン、中近世的な価値観に抗ったシェーンベルクと、本来、クラシック音楽はファッションと同様に時代に挑戦し、時代を更新してきた革新的な芸術のはずですが(クラシック音楽の前衛性)、第一次世界大戦終結後の1918年から第二次世界大戦終結後の1949年までの間にクラシック音楽の演奏会で採り上げられる存命中の音楽家の曲が占める割合は77%から18%まで激減し、現在では存命中の音楽家の曲が全く採り上げられない演奏会も珍しくなく、数百年前の音楽ばかりが演奏されているという異常な状況に陥っています(クラシック音楽の時代劇化)。また、クラシック音楽の演奏会場に目を向ければ、未だに演奏家は社交界のドレスコードであるフォーマルウェア又はこれに準ずる衣裳を着用している姿が一般的ですが、ビジネス界では世界的にビジネスカジュアルや私服が当たり前になっている時代にあって、果たしてフォーマルウェア又はこれに準じる衣裳を着用しなければ失礼なのか?そのような大袈裟な衣装を着用しなければ受容できない音楽なのか?という違和感を覚えます。既にオペラでは現代的な演出が主流になってきている状況を踏まえると、そろそろ器楽や声楽の舞台も「チョンマゲ鬘」のような浮世離れした衣装から解放されても良いのではないかと感じます。今後も「時代劇ばかりのクラシック音楽」というマーケットが成立し得るのか個人的には疑問に思いますが(以下のシリーズ「現代を聴く」を始めた動機)、少なくとも過去に支持されてきた「水戸黄門の印籠」のような定番にカタルシスを感じる時代ではなくなってきているように感じます。なお、残念ながら僕は聴きに行くことができませんが、今年も7月15、16日に「ボンクリ・フェス2022」が開催されますので、是非、お運び下さい。
「革新とは、単なる方法ではなく、新しい世界観を意味する」(ピーター・ドラッカー)
◆シリーズ「現代を聴く」Vol.2
1980年代以降に生まれたミレニアル世代からZ世代にかけての若手の現代音楽家で、現在、最も注目されている俊英を期待を込めてご紹介します。
▼ 林佳瑩「弦楽四重奏曲」(2015年)
林佳瑩(1990年~)は、これまで数々の国際的な作曲賞を受賞しており、この曲でピエロ・ファルッリ国際作曲コンクール(2015年)を優勝しているなど世界的に高い評価を受けている期待の俊英です。2018年にはロイヤル・フィルハーモニック協会から「音楽芸術における最高水準の才能とその卓越性」を認められて作曲大賞を受賞しています。因みに、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱」は、1817年にロイヤル・フィルハーモニック協会の委嘱により作曲されています。▼ ミーシャ・ムローヴァ=アバド「CircleSong」(2015年)
ミーシャ・ムローヴァ=アバド(1990年~)は、その名前からも分かるとおり、ヴァイオリニストのヴィクトリア・ムローヴァと指揮者のクラウディオ・アバドの間に生まれ、現代音楽家&ジャズ・ベーシストとしてロンドンを中心に活動するサラブレッドです。この曲はアルバム「New Ansonia」に収録され、クラシック、ジャズやポップスなど幅広いジャンルをフィールドとする豊かな才能を感じさせます。昨年、アルバム「Dream Circle」をリリースするなど精力的に活動しています。
▼ テッド・ハーン「Entr’ acte」(2019年)
テッド・ハーン(1982年~)は、2013年にバロック舞曲の形式を借りて斬新なボーカル効果を採り入れたアカペラ作品「8声のためのパルティータ」でピュリッツァー音楽賞を最年少受賞して注目されます。この曲は2020年に第62回グラミ賞(最優秀室内音楽/小編成パフォーマンス部門)を受賞したアルバム「Orange」に収録されていますが、再び、2022年に「Narrow Sea」で第64回グラミー賞(最優秀コンテンポラリー・クラシック・コンポジション部門)を受賞し、現在、最も注目されている現代音楽家です。