
▼酔い給え(ブログの枕前編)
前回のブログ記事で近代能楽集「卒塔婆小町」について簡単に触れましたが、三島由紀夫は現実の空虚さを冷静に見詰めて生き長らえる老婆の生き方を志向することが芸術家の道であると説いていますが、フランスの詩人C.ボードレールが散文詩集「パリの憂鬱」に収録している「酔い給え」(以下の囲み記事で一部抜粋)で高らかに歌い上げているように、その芸術を受容する聴衆は動もすると陶酔のうちに死を夢見る詩人の生き方に堕落して行く傾向があると言えるかもしれません。この点、H.カラヤンは「指揮者もオーケストラも陶酔するのは三流、指揮者が冷静でオーケストラが陶酔するのは二流、指揮者もオーケストラも冷静で聴衆が陶酔するのが一流」という有名な名言を残していますが、美の本質を志向して芸術表現を究める永遠の闘いに身を投じる芸術家の生き方と芸術表現の一回性に萌え尽きる刹那な陶酔に身を溺れさせる聴衆の生き方は対照的であるように思われ、上述のような芸術家の矜持(プロフェッショナリズム)があるからこそ聴衆を陶酔沼に沈めてしまう老婆の呪力を授けられると言えるかもしれません。過去のブログ記事で触れたとおり、人類は起元前500年頃の精神革命により芸術を発明しますが、遥か昔、約1000万年前の突然変異によりアルコールを分解する代謝能力を獲得してアルコール(果樹や蜂蜜が発酵して自然に生まれたお酒)を摂取するようになったと言われていますので、最初に人類を陶酔沼に沈めたのはお酒だったのではないかと推測されます。紀元前8000年頃の中近東でワイン、ビールやパンが発明され、その原料となる穀物を栽培するために狩猟採集(旧石器時代の移動生活)から農耕牧畜(新石器時代の定住生活)へ移行したと言われており、紀元前3000年頃のエジプトでは世界最古のビール工房が建設され、ピラミッド建設に従事する労働者に報酬として毎日5リットル/人のビールが支給されていたと言われています。時代は下って、1989年のフランス革命はパリ市内に運び込まれるワイン等に対する関税を徴収するために設置された税関所を市民が襲撃したことが直接の端緒になったと言われており(ワインの値段が関税で4倍になり、「3スーのワイン万歳!12スーのワインを打倒せよ!」が革命のスローガンになったと言われています)、お酒が人類のモチベーションを発酵し、フランス革命を醸造したと言えるかもしれません。なお、西洋の酒神「バッカス」は豊饒と陶酔をもたらす神として崇められ、その酒神を祀るデュオニソス祭は神の狂気がダンサー達に憑依する放蕩な祭りとして有名で(演劇の誕生)、その酒神の宴「バッカナール」は西洋音楽(例えば、C.サン=サーンスのオペラ「サムソンとデリラ」、R.ワーグナーのオペラ「タンホイザー」、J.イベールの管弦楽のためのスケルツォ「バッカナール」、A.グラズノフのバレエ音楽「四季」、A.ルーセルのバレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」、R.シュトラウスのオペラ「ナクソス島のアリアドネ」、J.ケージのプリペアドピアノのための「バッカナール」や黛敏郎の管弦楽のための「バッカナール(饗宴)」など)の題材として好んで使われています。しかし、キリスト教の影響等もあり、西洋では人前で酔うこと(理性を失って本能に支配される酒狂)を非社会的(病、悪魔)な行為として恥辱と捉える傾向が強いと言われています。その一方で、日本では三大酒神(松尾大社、梅宮神社、大神神社)に代表される各地の酒神や酒飲みの神「布袋尊」等が崇敬され、また、千葉県酒々井町の酒の井伝説等が酒神の奇蹟として信奉されるなど、神と人がお酒を酌み交わして一体になる神人共食の伝統が育まれ、酔うという行為が神との結び付きを強めると考えられてきたことから、日本では人前で酔うこと(神の依り代である肉体を精神から解放する酒興)を社会的な行為として栄誉と捉える傾向が強いと言われています。この点、お酒は脳の神経伝達物質「ドーパミン」(快楽物質)の分泌を促してハイな状態(ほろ酔い)にしますが、お酒を過ごすと運動を司る小脳や記憶を司る海馬を麻痺させる泥酔状態(呂律が回らない、千鳥足や記憶喪失)になり、これが習慣化するとドーパミン中毒(アルコール依存症)を発症するリスクが指摘されています。立川談志が「酒が人間をダメにするんじゃない。人間はもともとダメだということを教えてくれるものだ。」という酩言を残していますが、お酒は自分を映す縁であり、お酒に飲まれて神との結び付きを失ってしまうようなダメな人間なのか、酒神は試されています。
Enivrez-vousIl faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. ~ C. Baudelaire ~【意訳】酔い給え絶えず酔っていなければならない。そのことに尽きる。時間という重荷に翼を折られ、地上に引き摺り降ろされる恐怖を感じないためには酔い続けなければならない。どうやって酔うか?酒、詩、美徳、好きなもので構わない。とにかく酔い給え。(C.ボードレール)

▼ドーパ民革命(ブログの枕後編)
前回のブログ記事で神経伝達物質の分泌量は脳の報酬量に比例して増えるのではなく、予測していた脳の報酬量と結果的に得られた脳の報酬量の「差分」に比例して増えることに簡単に触れましたが、人間は同じ刺激を繰り返し受けると慣れが生じて「差分」を感じなくなり、それに伴って「ドーパミン」(快楽物質)の分泌量も減少するために、「ドーパミン」(快楽物質)の分泌を促すべく新しい「差分」を求めるようになります。これが過剰に働くとドーパミン中毒(アルコール依存症、スマホ依存症などの原因)と揶揄される状態に陥りますが、その一方で、これが人類を進化させてきた原動力でもあり、その適度な活性は幸福な人生を送るうえで欠かせないものの1つと言えるかもしれません。マンガ「ミュジコフィリア」では、調性システムを使うと「既聴感」のある音楽しか創作できず、如何に「未聴感」のある音楽を創作するのかが現代音楽の課題であることに触れていますが、この「未聴感」が「差分」を生んで「ドーパミン」(快楽物質)の分泌を促す可能性があります。この点、既存の音楽を巧みに演奏し又はその解釈に工夫を尽くしても、その「差分」は些少なものでしかなく、未聴感のある音楽等による新しい芸術体験が求められるようになってきているのが最近の初演ブームとも言える状況ではないかと思います。ドーパミンを生成する細胞は脳細胞全体の僅か0.0005%を占めるに過ぎませんが、最新の研究成果では、ドーパミンは生存と生殖につながる行動を促して生存可能性を高めるという重要な働きを担っており、「快楽」だけではなく未だ実現していないことに関する「未来予測」「達成」等に関係する未来志向型の神経伝達物質であることが分かっています。これに対し、セロトニン(心のバランス)、オキシトシン(愛情ホルモン)、エンドルフィン(脳内モルヒネ)、エンドガンナビノイド(脳内マリファナ)は既に実現していることに関する「現状維持」「満足」等に関係する現在志向型の神経伝達物質であることが分かっており、現在志向型の神経伝達物質(セロトニン等)の働きが活性されると未来志向型の神経伝達物質(ドーパミン)の働きが抑制され、未来志向型の神経伝達物質(ドーパミン)の働きが活性されると現在志向型の神経伝達物質(セロトニン等)の働きが抑制されるという仕組みで脳内のバランスが保たれています。この点、現状に対する不満は新しい快楽を求めて新しい挑戦を促すためのドーパミンが分泌される契機になり、ワイドショーの格好のネタになっている芸能人の不倫騒動は、このようなドーパミンの働きが引き起こしている現象と考えられます。一般に、セロトニン等の活性が高い人は現状を維持する保守的な思考が強く(ex.伝統的な家族観の尊重)、ドーパミンの活性が高い人は現在よりも良い未来を想像するリベラルな思考が強い(ex.ジェンダー平等の実現)と言われています(ベンチャー企業やエンタメ業界に多いタイプ)。過去のブログ記事でも触れたとおり「創造」と「狂気」は紙一重ですが、例えば、「ADHD」はドーパミンの分泌量が増加して注意欠如、多動性や衝動性等の症状を発症する精神疾患ですが、J.ガーシュウィンは「ADHD」の症状があり、それが斬新なリズムや多彩なハーモニー等の魅力的な音楽の創作に寄与したと言われています。また、「総合失調症」はドーパミンの分泌量が異常に増加して幻想や幻覚が発生する精神疾患(潜在抑制機能障害)ですが、(映画「ター」でも描かれているとおり)芸術作品の創作過程で脳の潜在抑制機能が低下することが分かっています。この点、「創造」とは過去に存在していなかった真実や美を創作し、表現することを意味しますが、芸術家は認知モデル(従来の世界観)を解体して全く新しい視点で世界を捉え直すために常識に囚われない自由に飛躍する思考が求められ、そのためにドーパミンの活性が重要になります。但し、芸術家は聴衆の認知世界(共有世界)に対する共感力(セトロニン等の活性)も備わっていて聴衆の認知世界とは隔絶されていない点が精神疾患者と異なっており、また、聴衆は芸術家の認知世界(非共有世界)に対する想像力(ドーパミンの活性)を育むことで自らの認知世界を芸術家の認知世界(非共有世界)へと拡張することが可能になります。認知モデルは、脳が世界を認知し易くするために様々な対象を抽象化して一般的な概念に昇華したものですが、その一方で、一定の視点からしか世界を捉えられなくなり多様に変化する世界に柔軟に適応して生存可能性を高めることが難しくなるという欠点を内包しています。そこで、ドーパミンは、認知モデルを創造する一方で、それを解体して新しい認知モデルを再創造する働きにも寄与しています。一般に、ドーパミンの活性が高い人間は人間関係を苦手とする傾向が強いと言われていますが、これはドーパミンの働きが活性されるとセロトニン等の働きが抑制され、人間への共感力が弱くなるためではないかと考えられています。この点、A.アインシュタインは「私の燃えるような社会正義感と社会責任感は、他の人間達との直接的な触れ合いを求める気持ちの明らかな欠如と、常に奇妙な対照をなしていた。」「私は人類を愛しているが、人間を憎んでいる。」と語っており(小説家のF.ドストエフスキーや詩人のE.ミレイなど著名な芸術家も同様の趣旨のことを語っています)、また、アインシュタインは妻以外の複数の女性との不倫関係で浮名を流しましたが、相対性理論を創発するためには多量のドーパミンが必要であったと考えられ、それによりセロトニン等が抑制されたために、妻を含む特定の女性を愛し続けることが難しく次々と新しい恋愛へ駆り立てられていったものと考えられます。全世界で約1/5の選ばれた人間だけがドーパミンの活性を強める遺伝子(7Rアレル)を持ち、創造的な発想が行う能力を備えて新しいものや珍しいものを見い出す傾向が強いと言われています。最近の研究では、このドーパミンの活性を強める遺伝子(7Rアレル)を持つ人間は、現世人類の世界拡散(様々なルートが指摘されていますが、アフリカ大陸→ユーラシア大陸→ベーリング海峡→アメリカ大陸)でより長い距離を移動した集団に属していた可能性(ドーパミンの分泌量が多いほど遠くへ移動する傾向)が高いことが指摘されています。この点、ドーパミンの過剰な活性によって引き起こされる双極性躁症状の有病率は、移民が多いアメリカは4.4%(世界最高)なのに対し、殆ど移民がいない日本は僅か0.7%(世界中でも極めて低い)に留まっており、また、アメリカでは20歳までに発症する患者は2/3に上ると言われているのに対し、ヨーロッパでは20歳までに発症する患者は1/4に満たないと言われており、現代のアメリカの経済的及び技術的な発展はドーパミンの活性が高いアメリカの遺伝子プールに理由の1つがあると言えるかもしれません。時代の変革期に日本が取り残されている理由の1つは、日本人のドーパミンが相対的に不活性であることが原因しているのかもしれず、(仮に、将来も日本が大国の地位に留まり続けたいと考えるのであれば)ドーパミンの活性が高いドーパ民への体質改善、意識改革が求められていると言えるかもしれません。人間の脳内ホルモンは約3ケ月前後で置き換わると言われていますので、この夏はサントリービールにしたたかに酔いながらサントリーサマーフェスバル2023年に参加して新しい芸術作品が描き出す新しい世界観に心酔することでドーパミンの活性を促したいと目論んでいます。
▼サントリーホールサマーフェスティバル2023①
【演題】作曲ワークショップ✕トークセッション
【演目】①オルガ・ノイヴィルト✕細川俊夫 トークセッション
②若手作曲家からの公募作品クリニック(実演付き)
・内垣亜優「チェロ・チュロス・チョリソー」
<Vc>下島万乃
・室元拓人「トカラ・イヴォーク」
<Fl>齋藤志野
<Va>甲斐史子
<Vc>下島万乃
・山田奈直「鯨」
<Cl>田中香織
【講師】オルガ・ノイヴィルト、細川俊夫
【場所】サントリーホール
【日時】2023年8月23日(水)19:00~
【一言感想】

◆オルガ・ノイヴィルトさんの紹介
今年のサントリーホール国際作曲委嘱シリーズのテーマ作曲家はオーストリア人のオルガ・ノイヴィルトさんです。オペラの伝統の象徴であるウィーン国立歌劇場が史上初めて女性作曲家のO.ノイヴィルトさんに新作オペラを委嘱し、2019年にウィーン国立歌劇場の創立150周年を記念してオペラ「オルランド」を初演して話題になりましたが(コム・デ・ギャルソンの川久保玲さんが衣装を担当)、先日、他界されたカイヤ・サーリアホさんと共に、世界をリードする女性作曲家の1人として注目されています。因みに、ウィーン国立歌劇場はイオアン・ホレンダーさん(伝統音楽の聖地・オーストリア産)が総監督を勤められていた時代(当時の音楽監督は小澤征爾さん)までは保守的な体質でしたが、2010年にドミニク・マイヤーさん(前衛音楽の聖地・フランス産)に総監督が交代すると、T.アデスさんやP.エトヴェシュさん(三島由紀夫さんの切腹を契機としてオペラ「ハラキリ」を作曲したことでも知られている作曲家)などの現代オペラや現代的な演出によるプロダクションの上演を積極的に行うなどウィーン国立歌劇場の一大改革に着手し、そのような文脈の中でウィーン国立歌劇場が史上初めて女性作曲家へ新作オペラを委嘱し、その体質が革新的に改まったことを強く印象付けることになりました。O.ノイヴィルトさんのご祖父は作曲家・音楽学者、ご尊父はジャズ・トランぺッターという音楽一家で育ち、当初はジャズ・トランぺッターを目指していたそうですが、交通事故で顎を負傷したことを契機として作曲家に転向して、実験音楽・大衆音楽の聖地・アメリカのサンフランシスコ音楽院で作曲、映画及び絵画、また、ウィーン音楽大学で作曲及び電子音楽を学び、作曲家L.ノーノの薫陶も受けているらしく、それがO.ノイヴィルトさんのジャンルに囚われない懐の広い音楽性になって現れており、時代の申し子と言うべき豊かなキャリアと稀有な才能に恵まれています。O.ノイヴィルトさんはクラシック音楽の歴史を育んできたウィーンの伝統に押しつぶされそうになりながら、男性社会であるクラシック音楽界の中で時代の価値観を先取りする自分の音楽を追求するために格闘して来たそうですが、漸く時代はO.ノイヴィルトさんをキャッチアップしつつあると言えるかもしれません。なお、O.ノイヴィルトさんは作曲家に転向した10代後半に5週間ほど日本に滞在した経験があるそうですが、日本に対する印象として演劇形式(能?)の抽象性に魅了され、また、「侘び」の美意識が浸透している社会の中に息衝く「衒い」(反語、当て擦り、皮肉、嫌味など)が面白く感じられ、高尚と低俗や素朴と外連など両極端な価値観が共存している点に興味を惹かれたそうです。
◆内垣亜優「チェロ・チュロス・チョリソー」
子音+母音で構成される日本語の発音の特性を生かして、チェロの「チェ」(特殊音)という発音から「チュ」(拗音)でチュロス、「チョ」(拗音)でチョリソーと連想し、それらの言葉のリズムやイントネーションなどから着想を得て作曲したそうです。さながら俳諧の連歌のように2・3・4の定型文を基調(モチーフ)とし、これをミニマル・ミュージック風というよりも変奏曲風に繰り返し変化させながら音楽が紡がれて行きました。O.ノイヴィルトさんからアイロニーを伝統的なスキームに収める手法で作曲されているが、例えば、ノイズや特殊奏法などチェロという楽器が持っている表現可能性を十分に活かしながら、もう少しアイロニーをワイルドに表現しても面白かったのではないかという趣旨のアドヴァイスがありました。自分の音楽を追求してウィーンの伝統に挑戦してきたO.ノイヴィルトさんらしいアドヴァイスに感じられました。なお、内垣亜優さんは、第8回日本国際合唱作曲コンクール第3位を受賞しているようですが(女性としては初の受賞者)、その受賞作品「ナンセンス・アルファベット」を聴くと、この曲と同様に言葉の意味ではなくその音(響き、リズム、イントネーションなど)を重視して作曲されているように感じます。この点、世阿弥の詞章を読むと、言葉の意味よりもその音に配慮して慎重に言葉を選んでいる印象を受けますが(和歌は目で理解する「読む」ものではなく耳で感じる「詠む」もの)、現代では日本語から失われつつある音の魅力に聴衆の意識を向ける面白い着想だと思います。
◆室元拓人「トカラ・イヴォーク」
シリーズ「現代を聴く」でもご紹介していますが、2022年に武満徹作曲賞第1位を受賞されている最も注目される若手作曲家ですが、その期待を裏切らない非常に面白い曲を聴くことができました。ブラヴォー!神の音連れ(訪れ)を音楽的に表現した物語性のある作品で、振れ幅の大きいノイズ(無秩序)で自然界に宿る神の気配、なだらかな楽音(秩序)で自然界から顕在する神を表現し、再び、振れ幅の大きいノイズ(無秩序)で自然界へと消え失せて鎮まる神の気配を表現するもので、此岸と彼岸の境界が曖昧な一元論的な世界観が精妙に描かれていました。先日、日本初演された細川俊夫さんのヴァイオリン協奏曲「祈る人」でも同じような世界観が描かれていて感動を禁じ得ませんでしたが、世界各地の異常気象とそれに伴う深刻な被害状況が報告されるなかで、改めて自然と人間の関係を捉え直す音楽には現代及び未来に込められたメッセージ性(ヒューマニズムに対する懐疑的な眼差しと対称性の回復に向けた意識的な変革)があるように感じられ、これまでのクラシック音楽では扱われていなかった、しかし現代人にとって非常に重要な価値観が表現されている現代人にとって必要な芸術であると感じ入りました。O.ノイヴィルトさんから室元さんがどのような着想を得て作曲した作品なのかプレゼンテーションがあったことで音楽的なイメージを共有できたことは非常に有益であった旨の総評が示されたうえで、更に楽器の使い方を工夫して表現のバリエーションを増やすことも考えられる旨のアドバイスがありました。
◆山田奈直「鯨」
深海を遊泳する鯨の声(仲間とのコミュニケーションを行うための「鯨の歌」、障害物を探知するための「エコーロケーション」(クリック音)、魚を狩猟するための「フィーディングコール」など)から着想を得て、鯨の雄大なイメージや深海の暗く静寂な世界を表現したそうです。クラリネット奏者が特殊奏法を駆使して鯨の声をイメージさせる音響を生み出しながら、舞台の四方向に設えられた譜面台を文字とおり回遊しながら演奏していきましたが、遠くに響く音、近くで響く音、線的に伸びる音、面的に広がる音などのバリエーションを使って深海の広大さや鯨の勇壮な遊泳を感じさせる立体的で動きのある音響空間を演出する工夫が非常に面白く効果的であったと思います。流石はVR世代の発想です。深海や鯨の世界を疑似体験することで、自然は人間の知覚能力が及ばない広大で深遠な世界が調和して成立しており、人間の知覚能力が及ぶ範囲を世界の全てであると勘違いして浅はかに振る舞ってきたヒューマニズムに対する警鐘を鳴らす現代的なメッセージを含んだ作品であるように感じられました。O.ノイヴィルトさんはオペラ「追放された者」で白鯨を題材にした作品を作曲した際に鯨の生態を研究したそうですが、鯨のクリック音は等間隔ではなく対象物に近付くと間隔を狭めて行くので、そのようなリアルな表現を採り入れて音楽表現に迫真を生む工夫が考えられるという趣旨の実践的なアドバイスや、鯨の獰猛な面も表現できればドラマが生まれて更に豊かな世界が広がるのではないかという趣旨のアドバイスもありました。
▼サントリーホールサマーフェスティバル2023②
【演題】オーケストラ・ポートレート(委嘱新作初演演奏会)
【演目】①ヤコブ・ミュールラッド「REMS」(短縮版・世界初演)
②オルガ・ノイヴィルト「オルランド・ワールド」(世界初演)
③オルガ・ノイヴィルト「旅/針のない時計」(2013年)
④アレクサンドル・スクリャービン 交響曲第4番「法悦の詩」
【演奏】<Mes>ヴィルピ・ライサネン
<Con>マティアス・ピンチャー
<Orc>東京都交響楽団
【場所】サントリーホール
【日時】2023年8月24日(木)19:00~
【一言感想】

◆ヨーロッパの音楽事情
近年、ヨーロッパの現代音楽祭は「現代の音楽」という切り口よりも「アクチュアルな音楽」という切り口で特集が組まれる傾向が強いそうですが、美術界でもソーシャルエンゲージメント・アートが注目されているように、現在、我々が直面している様々な社会問題(政治、環境破壊、ジェンダー、人種差別、テクノロジーなど)を題材として、それらの社会問題と正面から向き合い、新しい世界観を表現できる芸術表現が求められているそうです。映画「ター」にも描かれていますが、例えば、現代は「音楽とは、男の心から炎を打ち出すものでなければならない。そして女の目から涙を引き出すものでなければならない。」(ベートーヴェン)という認知バイアスが違和感なく受け入れられていた一昔前とは時代状況や時代感覚が大きく異なっており、もはや歴史上の偉大な芸術遺産だけでは現代人の教養(学問、知識、経験や芸術受容等を通して養われる心の豊かさ)を育むことは難しくなっているように感じます。再び、時代は大きな変革期に入っていますので、メトロポリタン歌劇場総監督のP.ゲルブさんも仰っているとおり、いつまでも懐古趣味に閉じ籠っているばかりではなく、現代人にも共感でき、現代人の教養を育み得る新しい芸術表現とその柔軟な受容が必要になっていると痛感します。さて、本日の演目はテーマ作曲家O.ノイヴィルトさんのチクルスではありませんでしたが、人間が生み出す様々なボーダー(時間、性別、意識など)を越える芸術体験というテーマ性に基づいた選曲であったのではないかと感じられます。
◆ヤコブ・ミュールラッド「REMS」(短縮版・世界初演)
スウェーデン人現代作曲家のヤコブ・ミュールラッドさん(1991年〜)は、ウォール財団特別賞(2018年)、TCO文化賞(2018年)、エル・ガラ賞(2019年)などを受賞し、また、ホーリー・ミニマリズムの特徴を持った曲が収録されているアルバム「TIME」がスウェーデンのグラミー賞(2019年)にノミネートされるなど、現在最も注目されている若手作曲家です。この曲は、夢と睡眠が持つ「謎めいた、心震わせる」ような体験に着目し、世界の子守歌やインドのラーガなどを参照しながら自らが体験した夢と睡眠を音楽的に表現したものだそうですが、本日は原曲(約26分)を1/4の長さに編曲したものが演奏されました。冒頭は寝入り端の無意識の世界を表現したものか静かなロングトーンが演奏されますが、やがて打楽器が時を刻み出すと、夢の抽象的なイメージを表現したものか弦楽器や管楽器がポルタメントやグリサンドを繰り返しながら、やがて夢の具象的なイメージを表現したものか何度かクライマックスを築いた後に、再び無意識の世界へ戻って静かに終曲するという夢の世界を疑似体験するような面白い作品でした。過去のブログ記事でもご紹介しましたが過去に夢をテーマにしたクラシック音楽は多く、後述するO.ノイヴィルトさんの「旅/針のない時計」でも夢のイメージが表現されていますが、夢のイメージ(認知パターン)とそれを表現するための音楽的な手法に相似している部分があり、夢と音の共感覚は世界で共通する要素があるかもしれません。
◆オルガ・ノイヴィルト「オルランド・ワールド」(世界初演)
本日は、上述のオペラ「オルランド」(原曲)からオルランドの歌唱パートの一部とその前後のオーケストラパートの一部で構成された組曲版が世界初演されました。このオペラの台本はイギリス人女性作家で女性解放運動のパイオニア的な存在としても著名なヴァージニア・ウルフさんのメタ小説「オーランドー」(1928年)が使用されていますが、1598年のエリザベス1世の治世下から物語が始まり、オルランドが昏睡状態の末に男性から女性に変身し、第二次世界大戦(ナチズム、原爆投下)を経て1928年(2019年(このオペラの台本ではオペラの世界初演日である2019年)まで約4世紀に亘って女性作家として男性社会の歴史に疑問を感じ、女性に対する偏見と闘いながら生きてきたという内容(O.ノイヴィルトさんの生き方とも重なる部分があるかもしれませんが)になっており、ジェンダーをはじめとして児童虐待、人種差別、ポピュリズムなど現代的な社会問題を先取りする内容が盛り込まれている作品として現在注目を集めています。このオペラではO.ノイヴィルトさんの多彩なキャリアと才能を反映してルネサンス音楽から現代音楽(エレクトロニクス、ミニマルミュージックなど)、ポップス、ロック、ジャズなど時代やジャンルのボーダーを感じさせない実に多彩な音楽が混然と調和しており、これがオルランドのノン・バイナリーな生き方を音楽的に体現する形にもなっていると思います。冒頭はタイムトリップを演出したものなのか霞がかったような微弱音から徐々にはっきりとした音像が浮かび上がってきましたが、さながら映画のトランジション効果を音楽的に演出したような劇的な効果が感じられました。また、チェンバロ、打楽器、エレキギターなど多種多様な楽器が使用され、それらが様々なジャンルの音楽を混然と演奏する様子(何か1つの表現にまとめられたり、線が引かれて区分けされたりしない様子)は、さながら多様な価値観を持った人間が息衝く現代社会の縮図を見ているようで、それゆえに真実味のある説得力のある音楽として心に響きました。これだけアグレッシブな音楽でありながら破綻を来さないのはO.ノイヴィルトさんの多彩なキャリアと才能の裏付けによるものだと思われ、決して他の作曲者には真似ができない個性的な作風ではないかと思われます。メゾ・ソプラノのV.ライサネンさんが男性から女性に変身する場面では、歌舞伎の早替りよろしく舞台上で一瞬で衣装替えを行って、その声域も低音域(男性)から高音域(女性)に変えて歌われるなどの演出上の工夫が大きな見所になっています。映画「ター」にも描かれていますが、オルランドの「慣習など僕にとっては無意味だ」という台詞は、過去の慣習や常識、伝統などに囚われ、それらの鋳型に若者の多様な才能を嵌め込もうとしがちな権威主義的な態度を戒めているようで心に刺ります。なお、組曲版では重唱パートや合唱パートなどが大幅にカットされた関係で、DVD(原曲)と聴き比べると音楽的な魅力のある聴きどころが減ってしまっていますので、是非、オペラ公演(原曲)も生演奏で聴いてみたい衝動に駆られます。この点、新国立劇場は握りキンタマ(財政難?)になっているのか来シーズンの演目はクラシック一色に逆戻りして物足りなさを否めませんので、是非とも、再来シーズンではO.ノイヴィルトさんのオペラ「オルランド」やオペラ「追放された者」など新しいオペラ作品の上演(新製作だけではなく日本初演)も積極的に考えて貰いたいと切望しています。
◆オルガ・ノイヴィルト「旅/針のない時計」(2013年)
この曲は、ウィーン国立歌劇場総監督がドミニク・マイヤーさんに交代した2010年にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団からグスタフ・マーラー没後100周年記念のために委嘱されたものだそうですが、当時、O.ノイヴィルトさんはオペラ「アメリカ人ルル」などの作曲に取り掛かっていたことから2015年まで委嘱が延期されることになったそうです。O.ノイヴィルトさんは他界したご祖父がドナウ川の河畔で人生を歌う夢を見たそうですが、その夢から着想を得てこの曲を作曲したそうです。この曲では時計の秒針を思わせるビート音が過去又は異次元への旅を想起させるように印象的に使用され、グリサンドやポルタメントなどの特殊奏法を挟んでマーチ、舞曲、ジャズやポップスなどのどこかで聴いたことがあるような懐かしい様々な曲調の音楽が奏でられ、再び、時計の秒針を思わせるビート音が刻まれることを繰り返しながら音楽が様々な時空を旅して行きます。おそらくマーチ、舞曲、ジャズやポップスなどのどこかで聴いたことがあるような懐かしい様々な曲調の音楽は、夢に現れたご祖父の人生のフラグメントであり、ご祖父へのオマージュであるように感じられ、親から子へ、子から孫へと受け継がれて行く人間の命の営みを思い起こさせてくれる含蓄の深い音楽に感じられました。日本はお盆(盂蘭盆)を終えたばかりですが、時に触れ、折に触れて先祖のことを思い出すこと(思いやり=「思い」を「遣る」)が何よりの供養であり、それが先祖から授けられた自らの命を愛しむということにもつながるのだろうと思います。そんな気持ちにさせてくれる音楽でした。
◆アレクサンドル・スクリャービン 交響曲第4番「法悦の詩」
調性音楽(具象絵画)から無調音楽(抽象絵画)へと向かう過渡期の時代に、スクリャービンが神秘和音(複合的な和声)を使って作曲した曲(印象主義~フォービズム)ですが、定番曲でもあり、紙片の都合から感想は割愛します。
▼サントリーホールサマーフェスティバル2023③
【演題】第33回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会
【演目】①第31回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞記念委嘱作品
・桑原ゆう「葉落月の段」(世界初演)
<尺八>黒田鈴尊
<三味線>本條秀慈郎
②第33回芥川也寸志サントリー作曲賞候補作品
・田中弘基「痕跡/螺旋(差延 II)」(2021年)
・向井航「ダンシング・クィア」(2022年)
・松本淳一「忘れかけの床、あるいは部屋」(2016年)
【演奏】<Con>石川征太郎
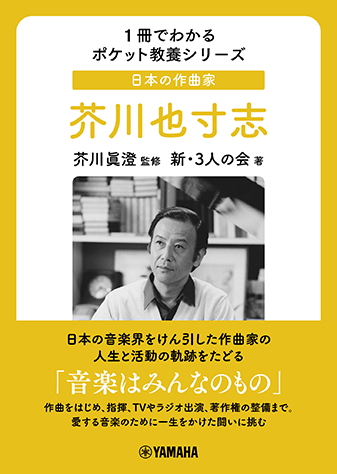


<Orc>新日本フィルハーモニー交響楽団
【司会】白石美雪
【審査】稲森安太己、小鍛冶邦隆、渡辺裕紀子
【場所】サントリーホール
【日時】2023年8月26日(土)15:00~
【一言感想】
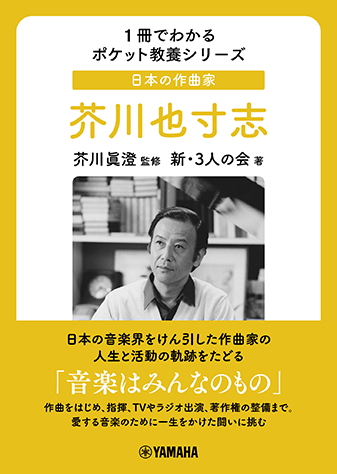
◆現代音楽の受容環境(課題感)
観客の立場から、最近、現代音楽の受容環境について課題感を持っていることは、殆どの曲が初聴であり一聴しただけではその魅力を十分に理解することが困難な複雑な曲が多いにも拘らず、クラシック音楽とは異なって参照できる音源などがリリースされておらず、また、その曲が再演される可能性も極めて低い状況にあるなか、せっかく現代音楽の演奏会に足を運んで某曲を見染めても、その某曲の魅力を十分に理解できないままに一夜限りの行きずりの関係で終わってしまうヒモジイ芸術体験しか期待できない憾みがあります。クラシック音楽であれば、演奏会で気に入った某曲と出会えれば、その某曲の音源を入手して何度でも繰り返して視聴しながら鑑賞を深め、その某曲の真価に触れて愛を育むという豊かな芸術体験が可能ですが、現在のところ、このような大人の関係は現代音楽では期待し得ないことだと諦めざるを得ません。このまま観客にとって現代音楽が夜鷹のような存在にしかなり得ないならば、益々、現代音楽の演奏会から客足は遠退いて、現代音楽のファンを増やすことは叶わないのではないかと危惧を覚えます。もし演奏会の模様を録画されているのであれば、例えば、演奏会のチケットを購入した観客に限って、一定期間、その録画をアーカイブ配信するなど豊かな芸術体験を可能にする工夫を真剣にご検討頂きたいと感じています。観客が現代音楽と愛を育むことは許されないのでしょうか。
▼現代音楽の演奏会で某曲を見染めた帰り道の観客の心中此の世の名残り、夜も名残り、死にに行く身を譬ふれば、あだしが原の道の霜、一足ずつに消えて行く、夢の夢こそ哀れなれ、あれ数ふれば、暁の、七つの時が六つ鳴りて、残る一つが今生の、鐘の響の聞き納め、寂滅為楽と響くなり。(曽根崎心中改め、観客心中、道行)
◆桑原ゆう「葉落月の段」(世界初演)
桑原ゆうさんは「タイム・アビス」で第31回芥川也寸志サントリー賞を受賞しましたが、その恩典として委嘱されたオーケストラ作品が初演されました。タイトルの「葉落月の段」(三味線と尺八のためのドッペル・コンチェルト)は武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」(琵琶と尺八のためのドッペル・コンチェルト)を意識したものだそうですが、ご案内のとおりノヴェンバー・ステップスは小澤征爾さんがニューヨーク・フィルハーモニックの音楽監督だったL.バーンスタインに武満徹を紹介し、L.バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニック創立125周年を記念する曲を武満徹に委嘱して誕生した曲で、1967年11月の初演予定から「ノヴェンバー」、邦楽の段構成から「ステップス」と命名されました。これを踏まえて、2023年8月の初演予定から旧歴8月を意味する「葉落月」と命名されたそうですが、桑原さんの野心と自信の程が窺える逸話です。武満徹が東西の音楽的な特徴について「洋楽の音は水平に歩行する。だが、尺八の音は垂直に樹のように起る。」と語っているとおりノヴェンバー・ステップスの作曲にあたって東西の音楽的な特徴の違いに着目されていましたが(西洋の音楽は西洋の絵画のように音(色)の連なり重なりで描く音世界、日本の音楽は水墨画のように一音(一線)で描き切る音世界などの音楽的な特徴の違いは、西洋の言語が連音、日本語が一音で感情表現する延音などの言語的な特徴の違いと通底するものがあります。)、桑原さんは東西の音楽的な特徴を「比べる」や「混ぜる」のではなく、東西の音楽的な特徴の背後にある音や音楽の本質に迫ることで東西の音楽的な特徴を活かしながら共生する「和える」(日本的な発想)という視点から新しい芸術表現を探求し、武満徹を嚆矢とする日本人のアイデンティティに根差した現代音楽の創作を次のステップ(ノヴェンバーから葉落月)へと進化させたいという並々ならぬ覚悟と意欲が感じられます(注:あくまでも僕なりの理解で意訳していますので、桑原さんの考え方はご本人の発言を直接参照して下さい)。現代は第三世界が台頭するポスト・アメリカニズムの時代と言われているとおり多極化、多文化及び多様化などを前提として世界の調和を志向する新しい世界観が模索され始めていますが、さながら桑原さんの作曲理念はそれを芸術表現の次元で探求するものであるように感じられ、これからの時代を表現する新しい芸術としてどのように進化して行くのか注目されます。今日はオーケストラ作品なので二階席で鑑賞することにしましたが、そのために三味線や尺八の細かいニュアンスまで十分に感じ取ることができず(国立劇場や能楽堂では前方の席を好みますので)、邦楽コンチェルトの席取りの難しさを感じました。また、僕のような素人の耳では新曲を一聴しただけで音楽の細部まで聴き取ることは難しいので、次回の再演の機会まで詳しい感想は留保することにし、いくつか印象的であった部分のみの簡単な感想を残しておきたいと思います。この曲の冒頭では三味線が撥弦楽器とは思えないような微弱音を奏で、これと掛け合う尺八も息の音から楽器の音へと徐々に変化して行く繊細な演奏が印象的でしたが、念や声、息から音が紡がれて音楽が奏でられる過程が表現されているようで、冒頭から三味線と尺八が奏でる世界に惹き込まれました。ソリストである三味線と尺八の掛け合いが音楽をリードしながら、これをオーケストラがサポートするというコンチェルト・スタイルで音楽が進行しましたが、東洋の音楽的な特徴と西洋の音楽的な特徴が活かされた新しい試みが随所に聴かれ、例えば、三味線が西洋的な叙情性を湛えた旋律を奏でるパートやフルートが東洋的な風情を湛えた虫の音を奏でるパートなど、東西の音をクロスオーバーさせながら東西の音の美意識の違いを聴かせる工夫などが面白く感じられました。現代音楽はノイズを効果的に採り入れて東西の音の美意識の違いを乗り越える試みが盛んですが、基本的に西洋音楽は清音を基調として耳で知覚できる音を連ね重ねて観客へ訴え掛ける音空間を作り上げるのに対し、邦楽は清音及び濁音(自然界の音に近い雑味を含む音)を巧みに操りながら耳で知覚できない間や余韻を聴かせることで観客を惹き込む音空間を作り上げるという特徴的な違いがあり、両者の魅力を並存させながら1つの世界観を表現するためには様々な工夫を尽くさなければならない難しさがあると思います。桑原さんによれば、「演奏家に多くの部分をまかせる」(=即興演奏 ≠ 偶然性・不確定性の音楽)という邦楽的な作曲手法を積極的に採り入れたいと仰っていましたが、例えば、尺八は首振り1つを取っても演奏者によって演奏日によって変化し得る振れ幅があると言われており、その音楽の揺らぎが邦楽の特徴的な魅力になっていますが、後半の三味線と尺八の掛け合い(カデンツァ)を含めてどのような指示が楽譜(五線譜?邦楽譜?ハイブリッド楽譜?又は図形楽譜のようなメタ楽譜?)に書き込まれているのか、即ち、東西の音楽的な特徴を活かしながら共生する音楽を創作するために邦楽器及び西洋楽器の演奏者との間でどのようなメディアを使ってどのようなコミュニケーションを試みられているのかという点にも興味があります。クラシック音楽はバロック音楽の時代から世代間で受け継がれてきた即興演奏の伝統がありましたが、戦後から本格化した楽譜至上主義に基づく演奏習慣(モダニズム)によって音楽の自由度が損なわれたことから、現代音楽では音楽の自由度(楽譜からの解放)を採り入れる試み(ポストモダン)が盛んです。この点、世界からは邦楽の特徴的な魅力を含む日本人のアイデンティティが感じられる独創性のある芸術作品が求められ、評価される傾向があるように思いますので、今後も桑原さんの作品から耳を離せません。
◆演奏会形式の公開審査(結果と概要)
若手作曲家の登竜門になっている音楽の芥川賞である第33回芥川也寸志サントリー作曲賞は(音楽の直木賞は武満徹作曲賞か?)、以下の作品に決定されました。これと併せて、SFA賞(聴衆賞)も、以下の作品に決定されました。向井航さん、ダブル受賞おめでとうございます🎉 僕のような軽輩にもSFA賞(聴衆賞)の投票権がありましたので(但し、会場には作曲家、演奏家、音大生、本格派を気取る聴衆などコアーな客層が多いように感じられましたので、さしずめ本屋大賞と言ったところでしょうか。)、以下の作品に投票させて頂きました。3作品共に三者三様の個性や面白さがあり甲乙を付けるのはナンセンスにも感じられましたが、P.ドラッカーの名言を借りれば、現代に求められている革新とは「どのように表現するのか」(方法)よりも「何を表現するのか」(世界観)が問われており、その観点から以下の作品が最も充実した実質を備えていると感じられたというのが投票理由です。なお、当日は公開審査会が開催され、各審査員が各作品について簡単に講評したうえで、審査員の合議で受賞作品が決定されましたが、その概要を簡単に残しておきたいと思います。
▼第33回芥川也寸志サントリー作曲賞受賞向井航「ダンシング・クィア」(2022年)
◆田中弘基「痕跡/螺旋(差延 II)」(2021年)
タイトルの「痕跡」は、J.デリダの「差延」(différance)の考え方を使った脱構築の試みを示すものと思われますが、パンフレットの解説を引用すると「音響や素材の「痕跡」(trace)を「辿る」(trace)」過程で「その「痕跡」を、時間的な隔たり(遅延)と共に、新しい文脈の中で他の音響や素材との「差異」(difference)によって新たに定義し続ける(差延/différance)」ことで「決して一定の「主題―展開」的機能を生じさせず、各音響・素材の意味性が時間を超越して流動的に変化して行く形式を模索」したとのことです。簡単に言えば、映画「燃えよドラゴン」の鏡の間の決闘シーンで鏡に映る無数のリーの姿(どれが本物か分からない状態)をイメージして頂くと分かり易い?のではないかと思います。なお、タイトルの「螺旋」の説明は、非常に技巧的な内容なので割愛します。審査員からはスペクトルによらない音響設計や楽器を色々な方法で組み合わせいる面白さがある一方で、一聴しただけでは分かり難い細々とした複雑さがある点などが指摘されていました。個人的には、ポスト構造主義を音楽的に志向されているのは分かるのですが、どのような世界観(目的)を表現したくて、このような手の込んだ「オーケストラ音響の設計方法」(手段)を考案されたのかについて言及がなかった点が残念に感じられました。この作品の作曲意図の形式面ではなく実質面を窺いたかったですが、そのイメージが伝わり難かったことがSFA賞(聴衆賞)の結果にも表れているような気がします。
◆向井航「ダンシング・クィア」(2022年)
パンフレットの「クィア・アクティビズムとしてのドキュメンタリー・ミュージック・シアター」というキャッチコピーが目を惹きますが、現代のアーティストにとってセルフプロデュース力も重要な資質であり、センスの良さを感じさせます。この曲は2022年にアンサンブル・フリーEASTが初演していますが、ヴォーギング(クィア・アクティビズムのダンス・ムーブメント)及びオーランド銃乱射事件(2016年に米国フロリダ州で起きたゲイクラブ銃乱射事件)をテーマにして、拡声器を持ったスピーカー(英語)をバンダに配し、世界最初のクィア・アクティビズムと言われるキャバレー・ソング「Das lila Lied」の歌詞からの引用及びヴォーギングやオーランド銃乱射事件に対するヴォーギング・ダンサー、著名人や政治家の発言からの引用等を読み上げ、これにオーケストラがヴォーギングから着想を得て作曲された曲を演奏して呼応するというスタイルで舞台が進行します。ドキュメンタリー映画の編集技術を参照して演出されており、非常に劇性のある舞台に固唾を呑みました。審査員からは作曲家の生き様が舞台に現れており非常に説得力があったとする一方で、演説のテンポを変えるなど更に劇性を増す工夫があったら更に良かったのではないかという点などが指摘されていました。個人的には、この曲には明確なメッセージ性が感じられ、また、そのドキュメンタリー性を表現するために非常に効果的な表現手法が用いられており(オーケストラ音響の設計方法などの形式が新しい必要はなく、その音楽が伝えようとしている世界観が現代人の教養を育むのに相応しい実質を備えたものなのか、また、その世界観を表現するために効果的なオーケストラ音響の設計方法などが選択又は開発されているのかが重要だと思いますが、その意味では非常に成功している面白い作品に感じられました。)、それがSFA賞(聴衆賞)の結果にも表れていると思います。
◆松本淳一「忘れかけの床、あるいは部屋」(2016年)
この曲ではスコルダトゥーラ(変則調弦)が使用されています。これまでもマーラーの交響曲第4番第2楽章のソロ・ヴァイオリンなどでスコルダトゥーラ(変則調弦)が使用される例はあり決して珍しいものではありませんが、これだけ大規模にスコルダトゥーラが使用されている演奏は初めて聴きました。人間は「楽曲前提」(知覚)と「体験前提」(記憶)とが組み合わされて音楽を聴取するという認知モデルをベースとして、オーケストラを「スコルダトゥーラ群が奏でる前提=「床」」(変則調律による5つの楽曲前提)と「床上でのオーケストラ体験=「部屋」」(標準調律442Hz(ISO16)による8つの体験前提)の2群に分け、「【床】のピッチと【部屋】すなわちオーケストラピッチの強固で微細なズレは、床面に絶えず差異、相克、対立、曖昧、混沌、同化などを浮かび上がらせますが、時間経過や音量バランス、反復や再現などの手法により、徐々に忘れ去られたり思い出したり」するという観客による音楽の認知体験そのものが音楽的に表現されています。審査員からはスコルダトゥーラ(変則調音)は開放弦による重音を使って短いフレーズが繰り返されるなど相対音感でも演奏が可能なように配慮されており美しい響きを持った音楽にまとめられているとする一方で、(詳しいことは分かりませんが)スコルダトゥーラ(変則調音)の大規模な使用については色々と物議になっていた点などが指摘されていました。個人的には、敢えて、エレクトロニクスではなくアコースティックなオーケストラサウンドを使った大規模なスコルダトゥーラ(変則調音)の音響が実に新鮮に感じられ、その豊かな表現可能性を感じさせる面白い作品でした。「床」と「部屋」のイメージを使った認知モデルの音楽的な表現もインスピレーションを掻き立てるもので興味深く感じられましたが、やや繰り返しが多く単調に感じられる部分もありました。SFA賞(聴衆賞)で向井さんと人気を二分する結果も頷けます。

SFA賞(聴衆賞)の発表現場
スタッフの温もりが伝わってくる手作り感💞

▼僕の頭を支配するもっと!(編集後記)
残念ながら都合が付かずに上記の3公演以外に参加することは困難ですが、サントリーホールサマーフェスティバル2023では小出稚子さんや宮内康乃さんなど若手作曲家の新作も初演される「Music in the Universe」、室内楽にも定評があるO.ノイヴィルトさんの「室内楽ポートレート(室内楽作品集)」、三輪眞弘さんがガムランのコスモロジーを表現した「プロジェクト型コンサートEn-gawa」などの魅力的な演奏会が予定されています。また、このフェスティバルとは別建ての公演になっていますが、このフェスティバルの期間中に開催される「湯浅譲二 作曲家のポートレート-アンテグラルから軌跡へ-」(サントリーホール主催)も聴き逃せない垂涎の企画になっており、このような贅沢な機会は滅多にないと思いますので、是非、ご都合の付く方はお運び頂き、その感想等をお聞かせ下さい。因みに、月刊誌「音楽の友」(8月号)で音楽評論家の白石美雪さんがサントリーホール国際作曲委嘱シリーズと紐付けて1990年代以降の現代音楽の潮流について分り易くまとめられており、大変に参考になります。なお、日本及び世界の舞台芸術を牽引するサントリーホール(サントリー芸術財団)の活動及び実績には傑出したものがあり、個人だけではなく団体(公益社団法人を含む)も対象としている地域文化功労者表彰を考えても良いのではないかと常々感じており、勝手ながら文化庁を外局とする文部科学省にリクエストしてみました。
◆シリーズ「現代を聴く」Vol.27
シリーズ「現代を聴く」では、1980年以降に生まれたミレニアル世代からZ世代にかけての若手の現代作曲家又は現代音楽と聴衆の橋渡しに貢献している若手の演奏家で、現在、最も注目されている俊英を期待を込めてご紹介します。
▼ディアナ・ロタルのピアノとエレクトロニクスのための「ベルベット・アリス」(2021年)
ルーマニア人作曲家のディアナ・ロタル(1981年~)は、入野賞(2004年)、ISCM-IAMIC若手作曲家賞(2008年)、ジョルジュ・エネスク賞(2010年)など数多くの音楽賞を受賞し、武生国際音楽祭から新作の作曲を委嘱されるなど最も注目されている若手作曲家の1人です。この曲は、ピアニストの山本純子と作曲家のオリバー・サッシャ・フリックに献呈された作品ですが、ルイス・キャロルの児童小説「不思議の国のアリス」とピピロッティ・リストの映像作品「不思議の国」から着想を得て作曲されていますが、おもちゃのピアノの音を同期することで現実世界と幻想世界のパラレルワールドが効果的に表現されている面白い作品です。
▼周久渝の弦楽四重奏曲第1番(2010年)
台湾人作曲家の周久渝(CHOU Chiu-Yu)(1981年~)は、国立台湾交響楽団管弦楽作曲コンクールで第1位(2010年)、ISCM-IAMIC若手作曲家賞(2011年)を受賞し、ブリテン・ピアーズ財団から助成金が支給されるなど現在最も注目されている若手作曲家の1人です。この曲は周久渝がISCM-IAMIC若手作曲家賞を受賞することになった出世作で、この動画は台北国立芸術大学でリディアン弦楽四重奏団が再演した模様を収録したものですが、再演されるだけあって繰り返しの受容に耐え得る構成力のある充実した内容を持った曲に感じられ、緩急や強弱を効果的に織り交ぜながらテンションの高い音楽を楽しめます。
▼宮内康乃のつむぎね公演「〇」(2017年)
日本人作曲家の宮内康乃(1980年~)は、実験的なミュージック、アート及びパフォーマンスフェスティバル最優秀賞(2008年)、アルスエレクトロニカ賞特別賞(2008年)、第6回JFC作曲賞(2011年)など数多くの音楽賞を受賞し、小出稚子と共にサントリーホールサマーフェスティバル2023で作品が採り上げられるなど最も注目されている若手作曲家の1人です。この動画は、宮内さんが主宰するパフォーマンスグループ「つむぎね」の公演の模様を収録したもので、宛らデュオニオス祭やアイヌ古式舞踊などシャーマニックな雰囲気が漂い、日頃とは別の感覚が覚醒されて新鮮な世界観が拓かれて行くような面白い体験型作品です。
