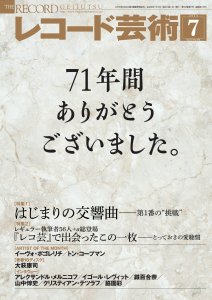▼世界のサカモトの世界(ブログの枕単編)
来る3月28日に一周忌を迎える坂本龍一さんですが、名前に「龍」の文字がつく人は辰年生まれの人が多く、坂本龍一さんのほかにも村上龍さんや芥川龍之介なども今年が年男の辰年生まれだそうです。因みに、坂本龍馬は辰年生まれではなく未年生まれですが、母・坂本幸が懐妊中に「麒麟」を受胎する夢を見たことに肖って、麒麟の頭=龍、麒麟の胴体=馬から「龍馬」と名付けたそうです。幕末、坂本龍馬のために奔走したイギリス人貿易商のT.クラバーは後に坂本龍馬の旧友・岩崎弥太郎の弟と協力してビール会社(現、キリンビール)を創立し、T.クラバーの提案で「麒麟」のエンブレムが採用されましたが、T.クラバーの手によって坂本龍馬はビールに生まれ変わり坂本龍一さんの音楽と共に現代人を酔わせ続けています。因みに、坂本龍一さんは自著「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」で自らのルーツに触れていますが、それによれば坂本龍馬との直接の関係はなさそうです。
さて、今回は坂本龍一さんの一周忌を迎えるにあたり、坂本さん(以下、「坂本さん」とは坂本龍一さんのこと)を追慕して供養したいという想いから世界のサカモトの世界と銘打って坂本さんについて書きたいと考えましたが、一応、巷に溢れる坂本さんに関する本(自著、他著)や音楽などには一通り触れてはいるものの、1ファンに過ぎない軽輩が坂本さんのことを無責任に書き散らかすことはできませんので、先日、NHKEテレで再放送された「SWITCHインタビュー達人達「坂本龍一X福岡伸一」」のEP1及びEP2で語られた内容に限り、その概要を簡単に採り上げてみたいと思います。この番組は、全く異なる分野の達人達の対談(エコトーン)により相互に共通するエッセンスなどを探る過程でどのようなスイッチ(シナプス可塑性)が生じるかというコンセプトによるクロスインタビュー番組で、坂本さんがアルバム「async」(坂本さんの命日2023年3月28日から6年前の2017年3月29日に発売)をリリースした年に予てから親交のあったロックフェラー大学客員教授(分子生物学)・福岡伸一さんと対談した模様を収録したものです。
▶ピュシスとロゴスの相克
芸術(音楽)と科学(生物学)の基本的な性質として、芸術(音楽)は一回性の表現(演奏は二度と同じ結果が得られないもの)であるのに対して、科学(生物学)は再現性の表現(実験は何度繰り返しても同じ結果が得られるもの)であるという意味で異なる営みのように見えますが、世界の成り立ちについてどのように表現するのかという意味では本質的な違いはないとも言えます。神の時代(神秘)から人間の時代(科学)へと移行したルネサンスを淵源とする20世紀型の思考は成果もありましたが、その弊害も見えてきています。本来、自然(ピュシス)はランダムなノイズに充たされた一回性の世界であり、科学はそのうちの再現性のあるシグナルのみを自然法則(ロゴス)として切り取ってきましたが、それによりノイズが見失われるようになったことでロゴスだけでは回収し切れない問題に対する新しいビジョンが必要になってきているという問題意識が示されました。この点、ドイツ人理論物理学者のJ.ユクスキュルは著書「生物から見た世界」で、人間以外の生物がどのように世界を知覚しているのかを説き表しましたが、過去のブログ記事でも触れたとおり、客観的に存在する「環境世界」に対し、それぞれの生物が知覚している主観的に存在する「環世界」(環境世界>環世界)があり、人間以外の生物はそれぞれの生存戦略として人間が捨象したノイズの一部を採り入れることを選択しているなど(例えば、可視域、可聴域や可嗅域など)、現代の科学はノイズを含めた総体として自然(古典物理学が記述するマクロの世界だけではなく、現代物理学が記述するミクロの世界を含む)を観察しなければ、この世界を正しく記述できないと認識されるようになっています。この点、前回のブログ記事でも触れたとおり、人間の脳は自らの生存可能性を高めるために偶然(ランダム)を嫌って理由(因果関係)を求める傾向があり、人間がコントロールし易いように偶然(ランダム)なものをロゴスで切り取って変形、加工しようとする認知特性(認識の監獄、即ち、言葉、分節や知識などによるロゴスの呪縛)から逃れられないというジレンマを抱えています。この背後には人間と自然は区分され(二元論的な世界観)、人間が自然の外側から自然を支配する者という認識がありますが、人間も自然の一部としてノイズを構成し(一元論的な世界観)、自然の内側から自然と共生する者であるという認識を持たなければならない時代状況にあり、過去のブログ記事(日本の耳が聞く蝉の声)でも触れた日本人が自然に対して持っていた鋭敏な感性を取り戻すところから始める必要があるかもしれません。このように芸術(音楽)や科学(生物学)が表現しようとする世界は、ロゴス(イデア、言語、論理、アルゴリズムなどで切り取られる人間中心主義的な世界)とピュシス(自然尊重主義的な世界観)の相克が絶え間なく交錯しているという問題意識が共有されました。
▶生命観(動的平衡)
生物は分子で構成されており、例えば、ネズミがチーズを食べるとネズミの分子の一部が分解されてチーズの分子に置き換えられますが、人間も約1年程度で体全体の分子が別の分子に置き換えられると言われています。科学は20世紀まで「作る」ことの研究が盛んでしたが、生命現象は「作る」ことよりも「壊す」ことの方が重要であることが認識されるようになると、20世紀末頃から「壊す」ことの研究が盛んになって、2016年に東京工業大学教授・大隅良典さんがオートファジー(自食作用)の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。福岡さんは著書「動的平衡」で、フランス人哲学者・H.ベルクソンが著書「創造的進化」で説いた「エラン・ヴィタール(生命の躍動)」やオーストリア人理論物理学者・E.シュレディンガーが著書「生命とは何か」で説いた「負のエントロピー」などの研究成果を参照しながら、生命現象とはエントロピー増大の法則(熱力学第二法則のことで、ここでは生命秩序の崩壊を意味しますが、これを簡単に言えば、分子がバラバラに分解していくイメージ)に抵抗して分子の分解と合成を繰り返しながら生命秩序の維持を図るためのバランス(動的平衡状態)を保とうとする作用ですが、常に分解のスピードが合成のスピードを上回っているので徐々に生命秩序の崩壊は進行してやがて消滅する運命にあり(ベリクソンの弧)、これが生命の有限性であると説いています。これを言い換えれば、ノイズから生命が合成されて、やがて生命はノイズに戻っていくとも言えます。(紙片の都合から詳細な内容は割愛しますが、ご興味がある方は引用書籍をご参照下さい。)
▶音楽観(async)
上述のとおり、人間はコントロールし易いように、本来、偶然的であるものをロゴスで切り取って変形、加工しようとする認知特性があり、自然(地)よりも自然法則(図)に意味を見出し、如何に自然法則(図)を美しいものに仕上げるのかということに価値を置いてきましたが、これはルネサンス以降の音楽についても同様のことが言えます。しかし、過去のブログ記事でも触れたとおり、禅や易学などの東洋思想の影響を受けたジョン・ケージは「ふつう〈音楽的〉と考えられているものに音が隷属させられている状態を拒否する」(著書「ジョン・ケージ 小鳥たちのために」)と宣言し、時間に従って音を構造化した図(音楽)ばかりではなく地(ノイズ)を聴くための偶然性(ランダム)を採り入れて、ロゴス(音楽的なもの)から音を解放しました。人間は時間や数字などに象徴される線形思考によりロゴスを使って世界を記述してきましたが、音楽も時間軸上に音符を並べて始点と終点がある線形的なものと考えられてきました。この点、現代音楽は分節ばかりに集中し、新たな連接の方法を見付け出せていないと言われてきましたが、坂本さんは直線的な時間の中で始点と終点を決める西洋音楽が一神教的な世界観であるとすると、もともと音楽はもっと多神教的、アニミズム的で始点や終点もなくタイムフレームからはみ出すようなものだったのではないかという考えから、線形ではない音楽、即ち、ピュシスとしての脳を持ち非線形的で時間軸がなく順序が管理されていない音楽を作れないものかと模索しているそうです。その意味では、坂本さんのアルバム「async」はベリクソンの弧のように音楽がノイズに戻りながらノイズから合成されるヒュシスの回復運動、本来音楽が持っている一回性のリズムなど、生命が発しているasync(非同期)を音楽的に表現したものと言えるかもしれません。人間が世界(ピュシス)を何らかの方法で表現しようとすれば、結局はロゴス化されることになりますが、坂本さんは「自然をできるだけありのままに記述する新しい言葉、より解像度の高い表現を求めることを諦めないこと、そのためにこそ音楽、科学、美術や哲学がある。文化と思想の多様性がある。」と看破されており、正しく慧眼です。坂本龍一さんが逝き、世の中が随分と味気ないものに感じられます。こんなことを口遊むのは、そろそろ僕も母なるノイズに戻って行くときが近いということかもしれません。なお、今月下旬に坂本さんが音楽監督を務めていた東北ユースオーケストラが坂本龍一監督追悼演奏会(既に東京公演は完売)を開催しますが、坂本さんが残した音楽文化のベリクソンの弧は次の世代へと受け継がれて音楽文化のヒュシスの回復運動として力強い歩みを続けています。
▼坂本龍一さんのアルバム「async」より「andata」この曲には坂本さんの音楽観や死生観が表現されているのではないかと感じます。冒頭はピアノソロの演奏だけが流れますが、約55秒頃からオルガンが奏でる音楽はノイズの中から顕れ、ノイズと共に息衝き、ノイズの中へと戻って行く様子が表現されているかのようです。上述のとおり物質には合成と分解を繰り返す不思議な性質がありますが、この現象に宇宙、天体や生命の生滅の摂理が隠されています。この点、生物学者・福岡伸一さんが開設しているWebページの動画がイメージとして非常に分かり易く、この動画を観ながらこの曲を聴いてみることをお勧めします。大きな音楽が聴こえてきます。
▼第41回読響アンサンブル・シリーズ
【演題】第41回読響アンサンブル・シリーズ
鈴木優人プロデュース
2つのチェンバロ協奏曲とG.トラークルの詩による3つの作品
【演目】①J.S.バッハ チェンバロ協奏曲へ短調(BWV1056)
②A.ウェーベルン 6つの歌(作品14)
③H.ヘンツェ アポロとヒュアキントス
④鈴木優人 浄められし秋
⑤P.グラス チェンバロ協奏曲
【演奏】<Cond、Cem、Pf>鈴木優人①②③④⑤
<Sop>松井亜希②④
<CT>藤木大地③
<Vn>戸原直①②③④⑤
對島哲男①③④⑤
赤池瑞枝④⑤
太田博子④⑤
寺井馨④
<Va>森口恭子①③④⑤
正田響子④⑤
<Vc>唐沢安岐奈①②③④⑤
林一公④⑤
<Cb>瀬泰幸①④⑤
<Fl>佐藤友美③⑤
<Ob>荒木奏美⑤
山本楓⑤
<Cl>金子平②
芳賀史徳②③
<Fg>井上俊次③⑤
<Hr>日橋辰朗③⑤
伴野涼介⑤
<Perc>金子泰子④
【場所】トッパンホール
【日時】2024年3月8日(金)19:00~
【一言感想】

読売日本交響楽団のクリエイティヴ・パートナーを務める鈴木優人さんが読響アンサンブル・シリーズでチェンバロ(古楽器)を使う現代音楽を採り上げるというので聴きに行きました。最近の顕著な傾向として、現代音楽を採り上げる演奏会で満席になる頻度が増えてきており、本日も満席の盛会になりましたが、徐々に、現代音楽を嗜む観客が増えてきている兆候ではないかと思われます。このような状況のなか、ストイックな響きやフットワークの軽さなどを特徴とする古楽器や古楽奏法を採り入れた現代音楽が注目されるようになってきていますが、昨年、BCJが霧島国際音楽祭で現代音楽を採り上げており、今後のBCJの動きからも目を離せません。人間の脳は飽きるように作られていますので、これからの時代の音楽家には定番曲を巧みに演奏するだけではなく世界中の新しい音楽の秀作(委嘱新作を含む)を発掘し、その魅力を観客に伝えてくれるような取組みにも期待したいと思っています。その意味で、鈴木優人さんのようにマルチな才能を発揮して多方面で活躍している逸材はいま旬の音楽家と言えるのではないかと思います。以下では、簡単に演奏の感想を残しておきたいと思います。
①J.S.バッハ チェンバロ協奏曲へ短調(BWV1056)
今日の演目はドイツ表現主義詩人ゲオルク・トラークルの詩を題材にした3つの声楽曲をJ.S.バッハとP.グラスのチェンバロ協奏曲(器楽曲)で挟むコンセプチャルな仕立てになっていましたが、チェンバロ(古楽器)とそれ以外の楽器(現代楽器)、J.S.バッハ(古楽曲)とP.グラス(現代曲)を対置して(十字架の縦棒「天の神」のメタファー?)、その間に麻薬中毒で現実と幻覚を彷徨ったトラークルの世界観を挟む(十字架の横棒「地の私」のメタファー?)というハイブリッドな演奏会になっていたのではないかと思います。上記のとおりチェンバロ(古楽器)以外は現代楽器が使用されていましたが、第二楽章がチェンバロの美観が際立つ好演でした。バッハの音楽は数多くの現代作曲家に影響を与え、その作曲にあたって参照され続けている文字通り天を仰ぎ見るような存在ですが、誤解を恐れずに言ってしまえば、P.グラスのチェンバロ協奏曲第一楽章を透かして見るとバッハの音楽の残照が浮かび上がってくるような肌触り感があります。(以下の囲み記事「チェンバロを使う現代音楽」で挙げているフランス人現代作曲家ジュール・マトンのチェンバロとオーケストラのためのバロック協奏曲第一楽章を聴いていても、音楽の父J.S.バッハの音脈を引く子が紡ぐ現代的なバロック(いびつ)であることが感じられて興味深いです。)
②A.ウェーベルン 6つの歌(作品14)
この曲は、A.ウェーベルンが様々な楽器編成で声楽曲を作曲していた時代の代表作ですが、G.トラークルの抒情詩集「夢の中のセバスチャン」から6篇の詩を選んで付曲したものです。セバスチャンとは、キリスト教徒を弾圧したディオクレティアヌス皇帝から処刑された近衛兵のことで、殉教後にキリスト教徒の夢の中に現れた聖人と言われています。G.トラークルは薬物中毒であったことが知られていますが、自然を題材にして独特な色彩、音韻や倒錯などを使って言葉(ロゴス)の意味を凌駕しながら夢(又は幻覚)の世界をイメージとして表現した詩人です。その一方、ウェーベルンはシェーンベルクの「1つの身振りで1編の小説を表し、1つの呼吸で1つの幸福を表す」という言葉に表されているとおりアフォリズム(物事の真実を簡素に表現する箴言警句を意味し、ヒポクラテスの「芸術は長く、人生は短し」という名言が代表例ですが、この言葉は坂本龍一さんのWebサイトでも引用されて話題になりました。因みに、世阿弥も「命には終りあり、能には果てあるべからず」(花鏡)という名言を残しています。)を音楽の特徴とし、無調音楽に傾倒しながら跳躍や緩急などを巧みに操って音楽に極度の緊張、凝縮を生む作風に魅力があり、それがG.トラークルの独特な詩の世界観と親和性があるように感じられます。この曲は、特殊な楽器編成(高音楽器:Vn又はCl、低音楽器:Vc又はBCl)で第1曲乃至第5曲は3つの楽器を多様に組合せた三重奏及び第6曲は4つの楽器の全奏で奏でられますが、全体的な印象としては閑寂とした趣きの中にも諧謔が入り混じる俳風に似た面白さが感じられました。読響メンバーの卓越したアンサンブル力により濃淡潤渇とした繊細さや奥深さを感じさせる集中力の高い演奏が聴かれ、これに呼応するソプラノの松井亜紀さんが高低強弱を淀みなく紡ぎながら、跳躍音の鋭さも感じられる研ぎ澄まされた清澄な歌唱には堂々とした風格や気品のようなものが感じられました。これまでのキャリアが一層と歌に磨きを掛けた印象があり、このアクのある難曲をすっきりとした後味良いものに感じさせてくれる好演でした。
③H.W.ヘンツェ アポロとヒュアキントス
ギリシャ神話に登場するアポロンとヒュアキントスの物語(古代ギリシャでは同性愛は一般的でしたが、音楽の神アポロと恋仲にあった美少年ヒュアキントスに横恋慕した西風の神ゼフィルスが嫉妬の末に西風を吹かせてアポロンの投げた円盤をヒュアキントスに命中させてしまい、これによりヒュアキントスはヒアシンスの花になったという物語)は、W.A.モーツァルトの最初のオペラの題材にもなっています。20世紀半ば同性愛に不寛容であったドイツからイタリアに移住した同性愛者のH.W.ヘンツェがアポロンとヒュアキントスの物語を題材に選び、妹との近親相姦に苦しんだG.トラークルの抒情詩集「夢の中のセバスチャン」から「公園で」と題する詩を引用した意図を感じさせます。H.W.ヘンツェはオペラ作曲家として知られ、先日もH.W.ヘンツェが三島由紀夫の小説「午後の曳航」を題材にした傑作オペラ「午後の曳航(裏切られた海)」を採り上げた東京二期会の公演を拝聴しましたが、モダニズムからポスト・モダンへの端境期にあたる時代を生きた作曲家です。当初は十二音技法に傾倒していましたが、その後、斬新さ(革新的な様式)と聴き易さ(伝統的な様式)をバランスよく折衷した作風へ変遷していきました。この曲は十二音技法を使いながら新古典主義的な特徴も備えているという意味で、その片鱗が窺われると言えるかもしれません。この曲は女性のアルトが歌うのが通例ですが、本日の演奏では男性のカウンターテナー(変声期後の男性がファルセット唱法でアルトやメゾ・ソプラノの音域を歌うもので、変声期前のボーイ・ソプラノや去勢により変声期後も変声期前の声を維持しているカストラートとは異なります。)に代えて演奏されたこと、即ち、性をニュートラルにすること(女性の声域を男性に歌わせることによる性の倒錯)により、H.W.ヘンツェの作曲意図を効果的に演出するだけではなく、カウンターテナーの藤木大全さんの純度の高い透徹な声質が「朽ちた大理石」に刻まれた因縁深い歴史までも透かして映し出すような音楽的な効果を生んでいたと思います。大理石の彫像を思わせる十二音技法の無機質な肌触り感がある一方で、オペラ作曲家としての経験を感じさせる音が持つドラマ性や豊かな着想による劇的な展開などに惹き込まれる曲ですが、チャンバロと他の楽器陣が緊密に呼応するスリリングで雄弁な演奏を楽しむことができました。H.W.ヘンツェの作品は現代音楽の中では比較的に演奏機会が多いと思いますが、その作品価値に比べて日本での認知度や演奏機会は未だに低い印象を否めませんので、今後、さらに日本での認知度が向上して演奏機会が増えることを期待したいです。今日は、そんなことを改めて実感させられる充実した演奏でした。
④鈴木優人 浄められし秋
鈴木さんは、BCJの首席指揮者のほか、読売交響楽団のクリエイティブ・パートナー、関西フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者を務めるなど飛ぶ鳥を落とす勢いの人気振りですが、東京藝術大学大学院古楽科及びハーグ王立音楽院オルガン科を卒業した古楽のエキスパートとして指揮者や鍵盤奏者の活動に留まらず、東京藝術大学作曲科も卒業した作曲家としても精力的に活動されており、そのバイタリティーには感心させられます。もともとバロック音楽(B)と現代音楽(C)は相性がよいと言われていますが、そのいずれにも精通している時代の寵児であり稀有な逸材です。この曲はG.トラークルの詩「輝く秋」を題材にしたものですが、パンフレットには「十二音音列的な旋律を描くソプラノ歌唱パートに対し、弦楽合奏はリズム・ユニゾンながらクラスター的な音響でそれを支え、コントラバス、ピアノとヴィブラフォンは、それらに体位的、対比的に絡まりながら進んで行く。」(音楽評論家・長木誠司さん)と楽曲解説が記されています。一聴した限りの感想になりますが、ユニゾンで力強く線(面)描する弦楽4部と、これに呼応して快活に点描するピアノ、ヴィブラフォン、コントラバスが対置されて音楽が展開されていきましたが、まるでジャズの編成のようなピアノ、ヴィブラフォン、コントラバスの組合せは非常に相性が良いもので、ジャズのグルーブ感を思わせる感興に乗じた面白い演奏を楽しめました。ソプラノの松井亜紀さんは詩情を湛えた優美な歌唱が出色で、上下に波打つような印象的な抑揚は「青い川を下る」又は「沈んでゆく」の様子を描写したものでしょうか、秋の憂いを帯びた美しい音風景を見ているようなヴィジュアルな印象を与える演奏を楽しめました。
⑤P.グラス チェンバロ協奏曲
この曲は、P.グラスが2002年にノースウェスト室内管弦楽団から委嘱されて作曲した作品で、漸く2020年になって日本でも初演されましたが、僕も実演を聴くのは初となる貴重な機会となりました(鈴木さんと読響に感謝)。P.グラスは、チェンバロは古楽オーケストラよりも現代オーケストラの方が「力強くふくよかな響き」を作ることが可能であるという考えを持っており、以前からチェンバロを使った音楽の作曲に関心があったそうです。上述のとおり第一楽章はJ.S.バッハへのオマージュが感じられる曲想ですが、チェンバロと他の楽器陣が当意即妙に振る舞う自在なアンサンブルでミニマル・ミュージックが織り成す豊かなグラデーションを楽しむことができました。第二楽章はチェンバロがメランコリックに旋律を紡ぎ出し、それをヴィオラ、フルート、オーボエが歌い継ぐ叙情豊かな演奏に魅了され、この曲が湛えているチャンバロ音楽の美観の極致を汲み尽くす秀演を楽しむことができました。ヴラヴィー!第三楽章はアニメソングのような快活にしてユーモラスな曲想ですが、その垢ぬけたノリははっきりと好みが分かれるものかもしれません。今日は、そんなモヤモヤとした気持ちも割り切れてしまうような熱量の高い快演を楽しめました。
▼チェンバロ(古楽器)を使う現代音楽チェンバロ(古楽器)を使う現代音楽は数多く作曲されていますが、Youtubeにアップされている音盤の一部を列挙しておきます。なお、日本人の現代作曲家もチェンバロ(古楽器)を使う現代音楽を数多く作曲していますが、Youtubeでチェンバロ(古楽器)を使っている音源が殆ど見当たりませんので列挙していません(今後、実演の機会が増えることを期待したいです)。・ウォルター・リー (~1942年) ハープシコードと弦楽合奏のための協奏曲・マヌエル・デ・ファリャ(~1946年)・フランシス・プーランク(~1963年) 田園のコンセール・クインシー・ポーター(~1966年) ハープシコード協奏曲・ダリユス・ミヨー(~1974年) クラヴサンとヴァイオリンのためのソナタ・フランク・マルタン(~1974年) 小協奏交響曲・武満徹(~1996年) Rain Dreaming・ヤニス・クセナキス(~2001年) ゴレ島にて・ヘンリク・グレツキ(~2010年) クラヴサンと管弦楽のための協奏曲・エリオット・カーター(~2012年)・藤井喬梓(~2018年) 奈良組曲〜クラヴサンによる古都の七つの幻影・クシシュトフ・ペンデレツキ(~2020年)・マイケル・ナイマン(1944年~) ハープシコードと弦楽のための協奏曲※日本公演・ジョン・ラター(1945年~)・クシシュトフ・クニッテル(1947年~)・ペテル・マハイジック(1961年~)・フランシスコ・コル(1985年~) ハープシコード協奏曲・ジュール・マトン(1988年~) チェンバロとオーケストラのためのバロック協奏曲・ベンジャミン・アタヒル(1989年~) オペラ「パストラール」
▼東京藝術大学芸術未来研究場アートDXプロジェクト
【演題】東京藝術大学芸術未来研究場アートDXプロジェクト
【演目】①フィリップ・マリヌ パルティータⅡ(2012年)
②青柿将大 Soli2(委嘱新作/2023年)
③エマニュエル・ニュネス アインシュピールングⅠ(2012年)
【演奏】<Vn>河村絢音
<Elc>佐原洸
【場所】東京藝術大学アーツ&サイエンスラボ
【日時】2024年3月17日(日)14:00~
【一言感想】

今日は、東京藝術大学が推進している「アートDXプロジェクト」の成果発表展として「ART DX EXPO#1」が開催され、ヴァイオリニストの河村絢音さんが「ヴァイオリンとライブ・エレクトロニクスのための作品委嘱と演奏発表」と題する研究成果の発表及び実演が行われるというので参加しました。今日の会場は、一昨年に竣工された国際交流棟(隈研吾設計)の隣にあるCOI活動の拠点であるアーツ&サイエンスラボ棟(音楽学部側)のドームシアターでしたが、東京藝大図書館の知的創生(エコトーン)の拠点であるラーニング・コモンズ棟(美術学部側)では3DCG、VRやメタバースなどのデジタル技術を使ったデジタルアーカイブ、コンセプチャルアートやゲームコンテンツなどの作品も展示されており、僅か10年前の東京藝大と比べてもその様変わりした革新的な姿に驚きを禁じ得ませんでした。何か新しいものを生み出そうと胎動しているエネルギーを感じます。因みに、これまで時代を拓いてきた東京藝大の正門は、僕にとっても奏楽堂や第6ホールへ足繫く通いながら夢を育んだ人生の1ページを飾る思い出の門ですが、先年、その再生プロジェクトに微力ながら協力した返礼として僕の名前が刻印されたレンガが埋め込まれています。これからも新しい時代を拓いて行く東京藝大の正門への「音楽の捧げもの」ならぬ「レンガの捧げもの」として。
河村さんはフランスやドイツに留学して研鑽を積んだ後に東京藝大博士課程に在籍してライブ・エレクトロニクスを研究しているそうです。具体的には、P.ブーレーズの「アンテームⅡ」、P.マヌリの「パルティータⅡ」、E.ニュネスの「アインシュピールングⅠ」などのヴァイオリンとライヴ・エレクトロニクスのための作品を題材にして「どのようにライブ・エレクトロニクスがヴァイオリン・パートに効果を与え、ヴァイオリン・ソロの手法と融合しているのか、両パートの双方向的干渉について研究」し、その研究成果を活かしてIRCAMで作曲研究を行っている現代作曲家・青柿将大さんにヴァイオリンとライブ・エレクトロニクスのための作品の作曲を委嘱したそうです。河村さんから説明された研究成果の詳細を公開することは控えますが、その概要の一部を簡単に紹介しておくと、P.ブーレーズの「アンテームⅡ」はヴァイオリン(アンテームⅠ)のパートの作曲後にエレクトロニクスのパートが作曲されているのに対して、P.マヌリの「パルティータⅡ」はエレクトロニクスのパートの作曲後にヴァイオリンのパートが作曲されているという違いがあり、それを踏まえて①ライヴ・エレクトロニクスがヴァイオリンの特性を増幅する効果と②ヴァイオリンとライブ・エレクトロニクスが双方向的に干渉(対話)する効果を解析及び比較すると、P.ブーレーズの「アンテームⅡ」は①の効果が高く、P.マヌリの「パルティータⅡ」は②の効果が高いことが判明したそうです。そこで、①の効果及び②の効果を両立させながらヴァイリンとライブ・エレクトロニクスを融合する作品を創作する試みとして、青柿さんにライブ・エレクトロニクスのパートを作曲することを前提にしてヴァイオリンのパートを作曲して貰い(Soli1)、それをベースにしてライヴ・エレクトロニクスのパートを追加(R.D.レインの詩集「結ぼれ」(1973年)にある文字と音をリンクして加工した音素材を使用してシュミレーション)して貰ったそうです(Soli2)。以上の研究成果の発表の後に実演が披露されましたが、P.マリヌの「パルティータⅡ」では、ヴァイオリンのパートとエレクトロニクスのパートが独立し、それぞれの世界観が対置、呼応するようなイメージの音楽に感じられました。これに対し、青柿将大さんの「Soli2」ではヴァイオリンが音楽を主導しながら、その世界観がエレクトロニクスによって拡張されて行くようなイメージの音楽に感じられ、この印象はE.ニュネスの「アインシュピールングⅠ」で更に強まり、ヴァイオリンの響きが拡張されてヴァイオリンの音とライブ・エレクトロニクスの音の境界が曖昧になって行く(アコースティック楽器の存在意義が希釈化されている)ようなイメージの音楽に感じられました。この点、青柿さんの「Soli2」は、Pマリヌの「パルティータⅡ」とE.ニュネスの「アインシュピールングⅠ」の中間にバランスしている印象を受けましたが、アコースティック楽器の存在感を残しながら、その世界観がライブ・エレクトロニクスによって拡張されていると共に、ライヴ・エレクトロニクスが独自にも振る舞うことでそれぞれの世界観が対置、呼応もしているようにも感じられ、ヴァイオリンとライブ・エレクトロニクスのための作品の表現可能性が拡げられている効果が感じられる面白い芸術体現になりました。河村さんと電子音響デザイン・作曲家の佐原洸さんはヴァイオリンとライブ・エレクトロニクスのユニット「Kasane(かさね)」を結成して新しい音楽の表現可能性を探求されているそうなので、今後の活躍に注目して行きたいと思っています。
▼東京・春・音楽祭2024
【演題】東京・春・音楽祭2024
ミュージアム・コンサート:東博でバッハ 成田達輝
【演目】①J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調
②J.S.バッハ
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ長調
③J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第2番イ短調
④山根明季子 黒いリボンをつけたブーレ
⑤山根明季子 リボン集積
⑥山根明季子 リボンの血肉と蒸気
⑦山根明季子 パニエ、美学
⑧梅本佑利 Melt Me!
⑨梅本佑利 Embellish Me!
⑩J.S.バッハ シャコンヌ
【演奏】<Vn>成田達輝
【日時】2024年3月21日~オンライン配信
【一言感想】

今年も東京・春・音楽祭が開催されていますが、①現代音楽の公演及び②ストリーミング配信の公演が非常に充実しており未来志向の姿勢が感じられる点が他の音楽祭と比べて優れていると思います。コロナ禍後もストリーミング配信の公演を継続していますが、様々な事情で会場へ赴くことが難しい人々への配慮にもなり(SDGs:誰一人取り残さない社会の体現)、また、デジタル田園都市構想を見据えた新しい芸術受容のあり方を模索する意味でも必要的な取組みではないかと思います。これまでのように音楽を楽しむのに「正座」(殆ど教義化している演奏会マナーなるドクトリン)を強要されるような音楽受容のあり方は如何にも権威主義的で古めかしく、家飲みしながら気軽に現代音楽の生演奏を鑑賞できてしまうのは本当に贅沢な気分に浸れて満足度も高いです。非常に演目数が多いので、以下では各曲毎に一言感想を残しておきたいと思います。
①無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調
まるでバッハの自筆譜を見ているような端正にして淀みなく流れる一筆書きの演奏が楽しめました。Adagio:気負いや衒いなどはなく滑らかなボーイングによる丁寧なフレージングで楚々と歌うナチュラルテイストの演奏、Fuga:1音1音を丁寧に鳴らす外連味や雑味のない演奏、Siciliana:このピースも1音1音を慈しむように慎重な足取りで紡いで行く演奏、Presto:春風を思わせる爽やかな軽快さが感じられ、デュナーミクを巧みに操りながら奥行きのある演奏を堪能できました。
②無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ長調
1音1音をゆるがせにしないしっかりとした足取りのリズム感がある演奏を楽しめました。Preludio:軽やかに飛翔するようなステップ感で、しかし1音1音が緻密に織り上げられていくような演奏、Loure:ゆっくりと慎重な足取りで繊細に歌わせる清潔感のある演奏、Gavotte en Rondeau:歌心があり、外連味のようなものがない誠実な印象を与える演奏、Menuett:華道に「花一輪に飼いならされる」という言葉がありますが、音楽に飼いならされて楽器を素直に鳴らす直向きな演奏、menuettⅡ:重音のバランスが良く、繊細なフレージングでポリフォニーの綾が美しく描かれる演奏、Bourree:生き生きとしたリズム感で澱みなくステップを運ぶ演奏、Gigue:誠実なアプローチですが、どこか小粋な遊び心も感じられる演奏を堪能できました。
③無伴奏てヴァイオリンのためのソナタ第2番イ短調
東京国立博物館法隆寺宝物館エントランスホールの残響を上手く捕まえて、清澄な響きで深淵にして広がりのある無伴奏ヴァイオリン曲の醍醐味が感じられる演奏を楽しめました。Grave:1音1音が丁寧に紡がれ、情緒に流され過ぎない節度を保った品位ある演奏、Fuga:理知的に音を積み重ねて行く端正な造形美が感じられる演奏、Andante:低声部のリズムが遠景にコダマし、優しい歌い口にまどろんでいるような夢心地の演奏、Allegro:速いテンポながら細部の彫琢まで明晰に響かせる精緻な演奏を堪能できました。
④山根明季子 黒いリボンをつけたブーレ
⑤山根明季子 リボン集積
⑥山根明季子 リボンの血肉と蒸気
⑦山根明季子 パニエ、美学
⑧梅本佑利 Melt Me!
⑨梅本佑利 Embellish Me!
拙ブログの「現代を聴く」シリーズでもご紹介したことがある現代作曲家の山根明季子さんと梅本佑利さんはサブカル系現代音楽(少女性、日本のポップ、サブカルチャーというテーマを扱う現代音楽)の第一人者で、成田さんと共に現代音楽ユニット「mumyo」(合同会社無名)を結成して活動していますが(この名前は坂本龍一さんが枕草子に登場する琵琶の名前に因んで命名)、本日の演目は現代音楽ユニット「mumyo」の公演「ゴシック・アンド・ロリータ」で発表されたバッハの音楽を素材にした作品になります。「ゴシック」(バッハ)と「ロリータ」(少女性、日本のポップ、サブカルチャー)という水と油のような素材を容赦なく融合し、ゲルマン民族の四角い骨格をゆるふわっと換骨奪胎してしまう異次元の作風にシナプス可塑性が活発化し、その差分でドーパミンが大量放出してしまう面白さがあります。昨年末、山根さんの二管の笙のための「Showgirls」(因みに、showは笙の掛詞)という作品を拝聴する機会もありましたが、これもエルドリッチ風バッハという風趣で大変に面白い作品でした。楷書体で四角い感想を書いてしまうと興が削がれるので、草書体で丸い感想をゆるふわっと書いておきたいと思います。先ず、山根さんの作品から演奏されました。「⿊いリボンをつけたブーレ」は「無伴奏パルティータ第1番のプーレをもとに⻄洋の伝統と現代⽇本のストリートを重ね合わせて反復装飾を施した」曲ですが、バッハの音楽が拡張高く奏でられ始めたかと思うと、直ぐに調子が狂い出して無手勝流のダンスが展開されることを繰り返しながら変奏されて行きました。バッハの堅牢な彫琢を借りて、どこかたどたどしい多様性の時代が紡がれていく面白い作品で、現代にバッハが生きていればどんな曲を書いていただろうなと空想を膨らませながら愉しみました。「リボン集積」は「リボンという少⼥的アイコンを通して⻄洋⾳楽の崇⾼さの裏側を暴き出した」曲ですが、リボンのモチーフが音程や音型などを変えながら繰り返されて集積されていくリボンだらけの音楽になりました。成田さんが内股で演奏していたのは作曲家からの指定なのか又はこの曲が演奏者をそんな気分にさせるということなのか、新しい響きが心をハッキングして行くような面白い音楽を楽しみました。「リボンの⾎⾁と蒸気」は「加速する資本主義時代の⾁体の記憶をテーマに無伴奏ソナタ第2番のアレグロをコラージュした」曲ですが、オスティナートによる変奏を得意としたバッハの作風をデフォルメするようにモチーフが執拗に繰り返され、大胆なデュナーミクが施されていきました。さながら連写撮影するプリクラ風バッハと言った風情の音楽を楽しめました。「パニエ、美学」は「建築物のようなフーガを解体してストリートファッション⾵に裁断した」曲ですが、モチーフを転調や変奏によって裁断しながら音楽が展開し、バロック(いびつ)からヴァリアント(フォルクスワーゲンの造語で、たよう)を特徴とするコンテンポラリーが生まれる様子(B→C)を見ているようで楽しめました。突然、モチーフの途中で終曲しますが、地柄が途中で切断されて「ないものを描くデザイン」が体現されているようで興味深かったです。現代のデザインを見ると、四角が正義であった時代から角を丸めて容易なことでは正体を現さない流体が好まれるようになりましたが、時代は固定(古典物理学、クラシック音楽)から流動(現代物理学、コンテンポラリー音楽)へと移り変っていることを感じさせます。これに続いて、梅本さんが「ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」で使用されている⾔い回しからインスピレーションを受けた世界観をもとに「装飾(⾳)」について再考」した作品が演奏されました。「Melt Me!」は「溶けるケーキ=バッハのイメージで微分⾳的「装飾」を施した」曲ですが、どことなくバッハの風味を感じさせる曲調の音楽が奏でられ、溶けるケーキを表現したものでしょうか下行形のモチーフが音域を変えながら繰り返されました。梅本さんは2002年に生まれたZ世代ですが、ミレニアル世代よりも前に生まれた老輩には思いも付かない斬新な着想が非常に新鮮に感じられ、これからの時代を表現する新しい音楽を作ってくれる逸材であると大変に注目しています。「Embellish Me!」は「装飾⾳符が被装飾⾳の原型を留めないほど過剰に扱われる」曲ですが、今度は上行形のモチーフを細かいトリル(あまりに細かいトリルなのでグリッサンドに近い印象を受けますが、こちらも微分音が使われていたのでしょうか)を使って装飾音がデフォルメされていきましたが、メインカルチャーとサブカルチャーなど様々なものが越境して主客の別がなくなっていく現代の時代性を映すような面白い作品でした。人生の線路を走るエリートとそこから脱線した不良の2種類の人間しかいなかった昭和時代とは異なり、山根さんや梅本さんの斬新な音楽に触れてバッハの音楽に対する冒涜だと騒ぎだす三角定規のような角張った人間はいなくなりましたので、バッハの音楽で軽やかに遊ぶ奇抜な才気や感性に脱帽すると共に、今後も大胆な挑戦に期待したいと思っています。
⑩シャコンヌ
ヴラヴォー!この演奏が出色でして、この曲に真正面から真摯に取り組んでいることが実感できる充実した熱演に圧倒されました。演奏者の人生を思わせ振りに物語る芝居掛かったシャコンヌという印象はなく、成田さんの冴え映えとした技巧に支えられて、この曲が舞曲であることを思い出させてくれるステップ感のある演奏が展開されました。しっかりと音楽のドラマも伝わってくる1本筋の通った骨太の演奏を楽しむことができました。
▼シアターピース「TIME」
【演目】シアターピース「TIME」(日本初演)
【音楽】坂本龍一
【映像】高谷史郎
【主演】<Dans>田中泯、石原淋
<笙>宮田まゆみ
【能管】藤田流十一世宗家 藤田六郎兵衛(2018年6月録音)
【照明】吉本有輝子
【PG】古舘健、濱哲史、白木良
【衣装】ソニア・パーク
【MG】サイモン・マッコール
【監督】大鹿展明
【技術】ZAK
【撮影】新明就太
【GF】南琢也
【音響】アレック・フェルマン、竹内真里亜、近藤真
【制作】湯田麻衣
【翻訳】サム・ベット(夏目漱石「夢十夜(第一夜)」「邯鄲」英訳)
原瑠璃彦(「邯鄲」現代語訳)
空音央(「胡蝶の夢」英訳)
【協力】福岡伸一
【場所】新国立劇場 中劇場
【日時】2024年3月30日(土)14:00~
【一言感想】ネタバレ注意!

他日公演がありますが、全公演が終わるまで待てませんので簡単に感想(注意:一部にネタバレあり)を残しておきたいと思います。もはやヴラヴィー!というスラングが陳腐に感じられてしまうほど含蓄のある作品でした。色即是空の世界観とでも言えば良いのでしょうか、言葉(ロゴス)で捉えようとすると掌から滑り落ちてしまうような、形なく相(すがた)を変え、色なく彩を放つ、さながら「水」のような作品でして、高谷さんが述べられているとおり、これから鑑賞を重ねる度に(さながら能面のように)違った表情を見せてくれる懐の広さや深さを持っている作品に感じられました。坂本さんは「パフォーマンスとインスタレーションの境目なく存在するような舞台芸術を作ろうと考え、「TIME」というタイトルを掲げ、あえて時間の否定に挑戦してみました。」と語られていますが、ここでの「時間の否定」とは時間芸術に象徴される過去から未来へと一方向に進む直線的な時間の流れ(時間感覚)の否定を試みたということだと思われます。過去のブログ記事で触れたとおり、人間の脳は物質の変化(エントロピーの増大)を知覚することで過去から未来へと一方向に進む直線的な時間の流れ(時間感覚)を認知しますが、相対性理論では時間が逆行する可能性(反物質)が指摘され、また、量子物理学では時間が離散的である可能性(クローノン)が指摘されており、現在では、過去から未来へと一方向に進む直線的な時間の流れ(時間感覚)は人間の脳が作り出す虚構であると考えられています(クオンタムネイティヴ)。この点、人間は1日周期で細胞のタンパク質の増減を繰り返すことで生体機能を管理する体内時計(身体性を前提とする因縁生)が備っており、その生命現象(ベリクソンの弧)が過去から未来へと一方向に進む直線的な時間の流れ(時間感覚:環世界)を生み出していると考えられていますが、上述のとおり「自然をできるだけありのままに記述」するために「環世界」(ロゴス)の呪縛から芸術を解放して「環境世界」(ピュシス)を描くための「より解像度の高い表現を求めることを諦めない」という創作的な試みが見事に結実している作品ではないかと思われます。上述のとおり懐の広さや深さを持った作品なので、この作品を見て何を感じるのかは人それぞれであり、そのような創造的鑑賞を許容する味わい深い作品と言えますが、僕はこの作品を能に擬えながら鑑賞しました。舞台上には、仏教が説く万物を生み出す五大元素(又は六大元素)、即ち、①石(墓石で表現される「地」又は冥界の入口)、②「水」、③④光(朱色の照明で表現される「火」、黒闇で表現される「空」(くう))、⑤スクリーンに映し出される画像(レースのカーテンで表現される「風」、雲で表現される「水」(の循環)など)が設えられ、⑥これに<土>から作られたレンガ(「職」のメタファー)と<木>から伐採された小枝(「職」のメタファー)が付け加えられているように感じましたが、さながら①石は此岸と彼岸の境界を画する能舞台の揚幕(地の底にある黄泉の国の神イザナミや地の底にある冥界を彷徨う森の木の妖精エウリディーチェに象徴される母なる大地は自然の循環により死(分散)から生(合成)へ輪廻する場所)、②水は此岸と彼岸をつなぐ能舞台の橋掛かり又はそれを介して顕在する本舞台(現実世界と夢幻世界又はロゴスとピュシスが交錯するハイブリッドな世界)、田中泯さんは現実世界と夢幻世界のあわひを旅するワキ、スクリーンに映し出される映像はワキが見る夢幻世界に顕在するシテのように感じられました。時間を分節する舞台幕はなく、いつ始まったのかどこからともなく雨の音(ロゴスで切り取ることができないピュシスとしての水の音)が緩やかに意識を捉え、また、いつ終わったのかどこからともなく風鈴の音(1920年にE.サティーが「家具の音楽」で聴かれない音楽を志向するよりも遥か昔の奈良時代から日本に存在していた風の音に戯れるアソビエント)が優しく意識を現実世界へと呼び覚ましましたが、一方向に進む直線的な時間の流れ(時間感覚)を画する「始まり」や「終わり」を感じさせない、即ち、人間が「環世界」としてロゴスで切り取る前から人間のタイムフレーム(時間感覚)を越えて存在している「環境世界」の存在を意識させる演出になっていました。宮田まゆみさんが「曲の方向性はジョン・ケージの音楽にも共通するものがあると思います。人間の感覚や情緒を表すのではなく、もっと大きな宇宙や自然の秩序を映している。そして人間もその宇宙の一部であることを感じさせる。」と書かれていますが、雨の音、石の音や鐘の音などのサウンドスケープと共にエレクトロニクスで「宇宙の音」(NASAが惑星や衛星が発する電磁波などを採取して人間の可聴音域に変換した音)を想起させる音響が奏でられました。J.ケージが語っているとおり、(西洋の)アコースティック楽器は調性音楽(ロゴス)を奏でるために改良されてきた歴史があり、そのために調性音楽以外の音楽(ピュシス)を奏でることには不向きであるという特徴がありますが、「環世界」(ロゴス)の呪縛から解放されて「環境世界」(ピュシス)を表現するための音楽にはエレクトロニクスを含む新しい楽器又は奏法による表現可能性の大幅な拡張が必要であると思われます。月夜のような淡い照明の中を宮田さんが宇宙を体現する笙の音を奏でながらゆっくりと水場を歩みましたが、「水清ければ月宿る」という言葉が持つ透明感をイメージさせる幻想的で美しい舞台に心を奪われました。幽光に浮かぶ宮田さんのシルエットがゆっくりとした足取りで歩みを進めると水場に「波紋」が広がるのが分かりましたが、ロゴスが象徴する直線的な時間(音)ではなくピュシスが象徴する離散的な時間(音)が表現されているようであり、正しく「音を視る、時を聴く」という風趣を湛えている舞台に魅了されました。宮田さんは「今は音楽にしても、映像にしても、空間にしても、とてもエモーショナルであったり、エンタテイメントとして刺激の多いものであったりすることが多いですよね。でも、この作品ではそういうものから離れて、もっと自然の中にある人間の存在を俯瞰で見ることを意識しました。その感覚は雅楽にも共通しています。」と語られていますが、ショパンの言葉を翻案すれば、バッハは「神」を表現するための音楽、ベートーヴェンは「人間(理性)」を表現するための音楽、ショパンは「人間(本能)」を表現するための音楽(いずれも環世界を表現するための音楽)を創作したのだとすれば、現代は人間中心主義に対する猛烈な反省から「自然(その一部としての人間を含む)」を表現するための音楽(環境世界を表現するための音楽)などが求められている時代であると言え、宮田さんが奏でる宇宙を体現する笙の音による神の栄光や人間の葛藤、渇望などのロゴスとは無縁の深い静寂が織り成す無為自然な世界観に心が澄まされるような感覚を覚えました。この舞台では、宮田さんがピュシスを体現し、田中さんがロゴスを体現していましたが、田中さんが水(ピュシス)を畏怖する様子を表現することで、かつて自然に畏敬の念を持ち自然と共生していた時代の人間の姿(レンガを並べるシーンの伏線)が象徴的に描かれているように感じられました。その後、夏目漱石の「夢十夜」(第一夜)を朗読する田中さんの声の録音が流れ出し(夢十夜のあらすじは割愛)、それに合わせて石(此岸と彼岸の境界)の近くの水場に横たわる女性(石原さん)と田中さんによるパフォーマンスが静かに展開されました。やがて自ら予告したとおり女性が死ぬと、スクリーンにはオルフェウスよろしく冥界の入口を探して石垣を彷徨うような田中さんの姿の映像(夢幻世界)が映し出されて、それを後追いするように水場を歩く田中さんの姿(現実世界)が(確率的に)共存し、やがてこれらの姿が重なるとスクリーンに映し出された田中さんの姿の映像は消えて水場を歩く田中さんの姿だけが残りましたが(波の収縮)、宛ら「シュレディンガーの猫」ならぬ「シュレディンガーの泯」が描く多世界解釈(量子物理学の世界観)を表現するコンセプチャルなアートのように感じられ、大変に興味深いシーンでした。その後、「夢十夜」(第一夜)の夢の途中で「邯鄲の枕」の夢が挿入され(邯鄲の枕のあらすじは割愛)、田中さんが水場に設えられた長椅子(邯鄲の枕)に伏せると、スクリーンには邯鄲の枕の夢として森林の映像が映し出され、木から作られた紙をめくる音、木から作られたピアノの内部奏法の音が聴こえてきましたが、本やピアノ(ロゴス)に価値を置くのではなく、本やピアノに使われている素材そのもの(ピュシス)に価値を置くことでロゴスとピュシスの価値の倒置を示唆すると共に、スクリーンには廃屋の映像、釜戸の映像、皇居の歴史的な建造物と丸の内の近代的な高層ビルの映像が映し出され、いくつもの異なる時間が重なり合う離散的な世界の中で物質が合成と離散を繰り返しながら万物が流転する世界観が象徴的に表現されているように感じられましたが、田中さんはそれらの邯鄲の枕の夢(離散的な時間の中に刹那的に顕れるロゴスとピュシスの相克)から目覚めて人生(ロゴス)の儚さを悟ります。再び、夢十夜(第一夜)の夢に戻り、田中さんは死んだ女性を土(地)に埋葬しますが、スクリーンには人間の営みを記録した沢山の画像が走馬灯のように過ぎ去った後、一輪の百合の花(中国では葉が何枚も重ね合わさる姿から「百合」(ヒャクゴウ)と書き、日本では花が風に揺れる姿から「揺り花」(ユリバナ)と言ったことから、日本語の「百合」(ユリ)という言葉になりましたが、ユリという言葉には「後で」という意味もあることから「何度でも逢える」という比喩表現として和歌などで使われるようになり、現代でも故人の枕辺に供える枕花として愛用されています。)が映し出され、田中さんは「百年はもう来ていたんだな」と人生(ロゴス)の儚さを悟ります。夢十夜(第一夜)では100年の「現実」を一瞬と捉える夢幻世界の中に生きる男と邯鄲の枕では50年の「夢幻」を一瞬と捉える現実世界の中に生きる男が対置されていましたが、夢幻世界の中に生きる男が見ている現実と現実世界の中に生きる男が見ている夢幻はいずれも脳が見せている虚構の世界とも言え、そのいずれが真実なのか又はそのいずれも真実ではないのか人間の知性では計り知れず、人間のタイムフレーム(時間感覚)では捉え切れない世界のあり様について取り留めもなく思いを巡らせました。田中さんは道具箱の中から土で作られたレンガと木から伐採した小枝を取り出し、これらを水場の向こう側へ渡るために直線的に並べる様子がパフォーマンスされました。高谷さんが「ロゴスとは物事をレンガのように分割して整理していく考え方、論理や言語ですね、そしてピュシスとは自然そのものです。つまり人間はピュシスをロゴスによって理解しよいうとするわけです。この作品はロゴスとピュシスの話が反映されていて、ピュシスをロゴスで制御しようとする人間を、田中泯さんがレンガを作った水の中の道を通って向こう側へ渡ろうとする姿で表現し、宮田まゆみさんの笙、そして水がピュシスの象徴になっています。」と書かれていますが、田中さんは冒頭での水(ピュシス)を畏怖する様子とは対照的に、レンガと小枝(いずれもロゴスのメタファー)を水場に直線的に並べて水(ピュシス)をコントロールしようと腐心する姿が象徴的に描かれていました(濁流が発生するシーンの伏線)。その後、スクリーンには荘子「胡蝶の夢」の原文(ロゴス)が水(ピュシス)に溶けて行く様子が映し出されました。ここで胡蝶の夢のあらすじには触れませんが、荘子「胡蝶の夢」では「現実の自分と夢で蝶になった自分のどちらが真実なのかを決めることなどせず、両方をあるがままに受け入れることが重要である。その境地に達することで真に自由な人間になれる」と説かれており、人生(ロゴス)の儚さを悟りその呪縛から解放されて自然(ピュシス)としての自分を回復する無為自然な生き方の有難さが身に染みてくるようです。その後、能楽笛方藤田流十一世宗家(現在は観世宗家預かりの空席)の藤田六郎兵衛さんが生前最後に吹いた笛の音の録音が流されましたが、笛の音はユリによる揺らぎを特徴として謂わば音の「揺り花」といった風情を湛えており、「芸術は長く、命は短し」を体現する感慨深い演出になっていました。やがて水滴の音が聴こえ出して、スクリーンには濁流(ピュシス)の映像が映し出されて田中さん(ロゴス)が飲み込まれましたが、坂本さんが生前に心を尽くされていた東日本大震災の記憶も影響しているシーンと言えるかもしれません。再び、雨の音、石の音や鐘の音などのサウンドスケープと共にエレクトロニクスで「宇宙の音」を想起させる音響が奏でられ、月夜のような淡い照明の中を宮田さんが宇宙を体現する笙の音を奏でながらゆっくりと水場を歩みましたが、上述のとおりどこからともなく風鈴の音(終わりを予定しない風の音)が聴こえ出しました。おそらく観客が風鈴の音の中を三々五々に退場することを企図したものではないかと思われましたが(粋)、今日の公演では風鈴の音の途中で「時間を分節する拍手」(ロゴスの音)が巻き起こってしまい(野暮)、大変に興を削がれてしまったのが残念でした。このようなことはクラシック音楽の演奏会などでも何度か経験していますが、(演目によっては)能の鑑賞と同様に拍手や歓声はご遠慮頂いても良いかもしれません。冒頭でも述べたとおり、この作品に何か見通しの良いナラティブを発見しようとすることはロゴスの呪縛に囚われることを意味し、この作品の本質から遠のいてしまうような気がします。ロゴスでは捉え切れない曖昧模糊としたものを残しながら、この作品を何度も繰り返し鑑賞するうちにロゴスから解放されてピュシスの境地を幻想する瞬間を体感することできるような気がしており、そのことでしかこの作品の本質に迫ることは難しいのかもしれません。これまでのクラシック音楽や前衛音楽とは全く異なる地平、高みにある新しい表現であると感じられ、文化的限界点という言葉を軽々しく口にしたがるチープな風潮とは異なって「芸術は長く、命は短し」という言葉の持つ重みが実感できる貴重な芸術体験になりました。「世界のサカモト」と言われる所以の一端に触れる作品に圧倒され、余人を持って代え難い本当に惜しい人を亡くしてしまったという喪失感が募ります。坂本さんと共に更なる新しい地平、高みを見てみたかったという思いを一層と強くしていますが、きっと、その志はこれからも高谷さんが育んで行ってくれるものと期待しています。
▼オペラ「ナターシャ」(委嘱新作/世界初演)先月、新国立劇場が2024/2025シーズンを発表し、日本を代表する現代作曲家・細川俊夫さんのオペラ「ナターシャ」(委嘱新作)が世界初演されます。果たして、チケットが取れるのか分かりませんが、いまから大変に楽しみです。もしチケットが完売し、採算性や権利処理などの問題もクリアできれば、全世界に発信する新国ライブビューイング(オンライン配信)もご検討頂けないものかと夢が膨らみます。すでに脳内のお花畑は満開です🌸▼映画「Ryuichi Sakamoto | Opus」来月、坂本龍一さんが最後に開催したピアノソロ・コンサート(NHK509スタジオ)の模様を収録したコンサート映画が公開されます。坂本さんが長年愛用してきたカスタムメイドのヤマハ製グランドピアノを使用して、自ら選曲した20曲を演奏したもので、文字通り坂本さんの「白鳥の歌」と言って過言ではない貴重なコンサート映画です。僕が坂本さんのピアノ演奏を最後に聴いたのは赤坂ARTシアターで開催された「ロハスクラシック・コンサート2008」(坂本さんのプロデュース)でしたが、未だ無名だったピアニストの小菅優さんを紹介されていたのを印象深く覚えています。坂本さんが小泉文夫さんに触れながらアメリカのクロスカルチャーの潮流について熱く語っておられ、大変に触発されたことを思い出します。昔から「バカの長生き」という耳の痛い言葉がありますが、時代に必要とされている人物から他界していってしまいます。










































































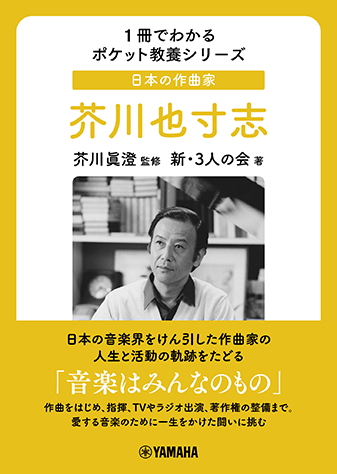








![カイエ・ソバージュ[完全版] 人類最古の哲学 熊から王へ 愛と経済のロゴス 神の発明 対称性人類学 (講談社選書メチエ) カイエ・ソバージュ[完全版] 人類最古の哲学 熊から王へ 愛と経済のロゴス 神の発明 対称性人類学 (講談社選書メチエ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51xA4EPdjkL._SL500_.jpg)

![『近代能楽集』ノ内「卒塔婆小町」 三島由紀夫 [DVD] 『近代能楽集』ノ内「卒塔婆小町」 三島由紀夫 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/319PIID-aPL._SL500_.jpg)