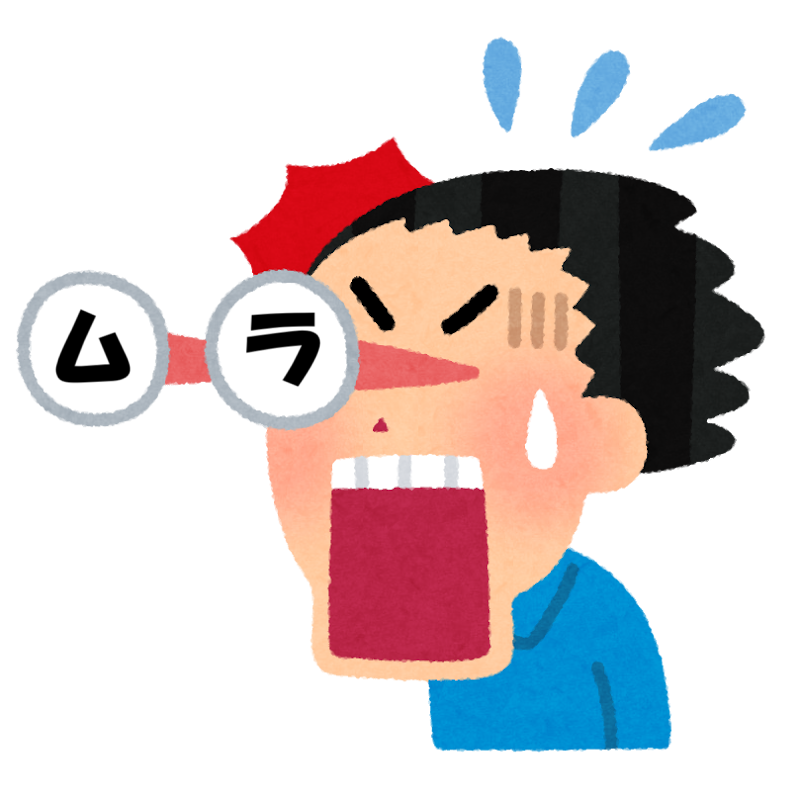
▼ブログの枕「この世界のムラを演出する」
前三回のブログ記事では「ムラ」をキーワードにして「宇宙誕生の物語」、「対称性の破れ」及び「行動遺伝学」についてごく簡単に触れましたが、今回は、この世界の「ムラ」を演出するという視点から、何故、人間は「ムラ」にムラムラと惹かれてしまうのかについてごく簡単に触れてみたいと思います。この点、人間が「ムラ」にムラムラと惹かれてしまう「プロセス」を科学的に解明するものとして、①インターネットが普及する前の20世紀の時代性を前提とする古典的モデル(AIDMAなど)と②インターネットが普及した後の21世紀の時代性を前提とする現代的モデル(AISASなど)の2種類のマーケティング・モデルが存在し、消費者の認知(注意、興味)から消費(行動)や評価(共有)までの一連の消費行動を時系列に沿ったプロセスとして段階的に捉えるフレームワークであるのに対して、人間が「ムラ」にムラムラと惹かれてしまう「心理的要因」を科学的に解明するものとして行動経済学が注目されており、一連のプロセスの各段階における消費行動の理由を分析するための心理学的な知見であると整理することができるのではないかと思います。即ち、マーケティング・モデルは「消費行動の外面」(流れ)を分析し、行動経済学は「消費行動の内面」(心理)を分析するという形で相互に補完し合いながら、何故、人間が「ムラ」にムラムラと惹かれるのかを解明し、その成果を人間がムラムラと惹かれるように「ムラ」の演出に活かす観点から社会経済活動に応用されていますが、現代は多彩に演出された多様な「ムラ」に心をハッキングされながら踊り狂っている時代と言えるかもしれません。
▼人が「ムラ」に惹かれるメカニズム(経済学+心理学)
マーケティング
モデル行動経済学 AIDMA
古典AISAS
現代認知 感情 状況 注意
Attentionシステム1対2
非流動性
身体的認知
概念メタファー
ホットハンド効果アフェクト
ポジティブ・アフェクト
ネガティブ・アフェクトフレーミング効果
フライミング効果
系列位置効果
単純存在効果興味
Interest快樂適応
計画の誤謬
真理の誤謬効果
自制バイアス拡張・形成理論
不確定性理論
境界効果おとり効果
アンカリング効果
感情移入ギャップ
バンドワゴン効果欲求
Dsire- 自制バイアス
メンタル・アカウンティング
真理の誤謬効果心理的所有感
目標助効効果
負の感情の利用ナッジ理論
フライミング効果- 検索
Search確認バイアス
解釈レベル理論
メンタル・アカウンティング
選択パラドックス
決定疲れ心理的コントロール
不確定性理論
目標助効効果情報オーバーロード
ビコーズ効果
社会的証明記憶
Memory- 確認バイアス
快樂適応
解釈レベル理論ピークエンドの法則
感情記憶効果系列位置効果
ビコーズ効果行動
Action計画の誤謬
自制バイアス
メンタル・アカウンティング
快樂適応
時間割引
先延ばしバイアスキャッシュレス効果
心理的所有感
目標助効効果
現在バイアスナッジ理論
ビコーズ効果
情報オーバーロード
選択アーキテクチャ- 共有
Share解釈レベル理論
真理の誤謬効果
ホットハンド効果
自己正当化バイアスポジティブ・アフェクト
心理的所有感
ピークエンドの法則
感情伝染ナッジ理論
フレーミング効果
SNS同調性
ステータス・シグナリング※紙片の都合から表中の行動経済学の知見(理論)について詳しくは解説しませんので、ご興味がある方は概説書などでお調べのうえ、ご活用下さい。※行動経済学の分野から2002年にダニエル・カールマン博士がプロスペクト理論(人間が不確実性のある状況下でどのような意思決定をするのかという研究)で、2013年にロバート・シラー博士がアノマリー理論(人間の非合理な意思決定の研究)で、2017年にリチャード・セイラーがナッジ理論(人間を強制することなく主体的に望ましい行動をとらせる研究)で、それぞれでノーベル経済学賞を受賞しています。※企業による行動経済学の応用例の一部として以下のものが挙げられます。・アマゾン:タイムセール(アンカリング効果、損失回避バイアス)・ネットフリックス:レコメンド機能(デフォルト効果、情報オーバーロード、選択オーバーロード)・グーグル:人材採用プロセス(確証バイアス)・TIKTOK:自動生成機能(現状維持バイアス)・スターバックス:ポイント制度(目標勾配効果、ゲーミフィケーション)

前三回のブログ記事ではマクロの世界を記述する古典物理学とミクロの世界を記述する現代物理学についてごく簡単に触れましたが、これは経済学や音楽学などの諸分野でも同様の傾向が見られます。古典的な経済学では人間は常に自己利益の最大化を図る合理的な経済人(ホモ・エコノミスク)であることを前提にして市場メカニズム(神の見えざる手)により社会全体として最適な資源配分が達成されるというマクロの視点を基調としていますが、現代的な経済学(行動経済学)では人間は必ずしも自己利益の最大化を図るために合理的に振る舞うとは限らない非合理的な経済人(限定合理性)であることを前提にして感情や認知バイアスなどの心理に左右されながら社会経済活動が営まれているというミクロの視点を基調としています。さながらクラシック音楽が半音(マクロ)を単位として構成される機能和声による予定調和な音楽(合理性)であるという特徴があるのに対して、現代音楽が微分音やスペクトル、ノイズなど(ミクロ)から構成される不確定的な音楽(非合理性)であるという特徴があることに相似していると言えるかもしれません。上述のとおり紙片の都合から行動経済学の知見(理論)について詳しくは触れませんが、人間の認知はシステム1(ヒューリスティック:経験則や直感に基づいて問題を迅速に解決するための思考プロセスで、効率的に判断できるというメリットがある一方でバイアスなどにより認知の歪みが生じ易いというデメリットがあると言われています。)とシステム2(システマティック:エビデンスや熟考に基づいて問題を慎重に解決するための思考プロセスで、バイアスなどにより認知の歪みが生じ難いというメリットがある一方で効率的に判断できないというデメリットがあると言われています。)という2つの認知プロセスが無意識下で連動していますが、システム1(ヒューリスティック)の働きが優位になると認知の歪み(不合理な判断)が生じ易くなり「ムラ」にムラムラと惹かれ易くなると考えられています。この点、過去のブログ記事で認知のメカニズムについて簡単に触れましたが、脳の機能としてデフォルト・モード・ネットワーク(直感)が働いているときはシステム1(ヒューリスティック)という認知プロセスが優位になり易く、セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク(論理)が働いているときはシステム2(システマティック)という認知プロセスが優位になり易いことが分かっており、元来、その人間が持っている認知のクセに加え、その人を取り囲む状況やその時々の感情が認知に大きく影響しています。また、過去のブログ記事では文化(認知)が環境(状況)にチューニングされていること、さらに、過去のブログ記事では人類が狩猟採集に相応しい特性を備えた「心」を備えており仲間が言うことを信じ易い傾向を持っていることなどに簡単に触れましたが、このように人間は自ら主体的に判断しているだけではなくその人を取り囲む状況やその時々の感情に影響されて非合理的な判断を選択させられていることも多く(選択アーキテクチャ)、このような認知の歪みを利用して非合理的な消費行動へと誘導するための手法(「ムラ」の演出)が研究、開発されており、ネット通販やテレビ通販などで購入させられた必要のないものが家に溢れてしまうという状況が生まれています。この点、芸術系の大学などでは劇場や美術館などの集客方法(「ムラ」の演出)について専門のカリキュラムが設けられていると思いますが、行動経済学の視点から現代音楽の演奏会の集客方法についてごく簡単に考えてみると、現代音楽は世界的な評価が定まっているごく一部の著名な現代作曲家を除いてクラシック音楽のように時代に淘汰された傑作揃いであるという「信頼感」(のれん)が十分に醸成されておらず、また、現代音楽の中には上述のシステム1及びシステム2が共に起動し難い「難解」なもの(あまり「面白さ」が感じられないものを含む)も少なくなく、さらに、現代の多様な娯楽との兼ね合いで「優先度」が相対的に低くなる傾向があることは否めず、これらを行動経済学に引き直して言えば、①社会的証明の欠如、②不確実性の回避、③損失回避バイアスなどが強く働いて、現代音楽の演奏会に足を運ぶハードルは決して低くない状況があるように感じられます。これらの課題感から様々な集客の工夫を試みている公演も増えてきましたが、残念ながら状況を一変させる特効薬のようなものはなく、(集客に関心がないタイプの現代作曲家を除いて)少しづつ状況を改善して行くための集客の工夫を継続する取組み(マーケットの醸成)は欠かせないのではないかと思います。例えば、①社会的証明の不足を補う手立てとして「過去に〇〇回再演されている人気曲」(バンドワゴン効果)や「〇〇〇〇(有名作曲家)へオマージュを捧げた新曲」(アンカリング効果)などのキャッチコピー、②不確実性の回避を補う手立てとして「コンセプチャルな演目構成」(フレーミング効果、ナラティブバイアス)や「プレ・レクチャーなどのイヴェント」(アンビギュイティ回避)、③損失回避バイアスを補う手立てとして「2001年以降に作曲された現代音楽の中で最も再演回数が多い曲」(発見バイアス)や「東京都交響楽団第1020回定期演奏会Aシリーズ」(知的探求ナッジ)などの多様な「ムラ」の演出が試されており、その他にも「前回と同じ席をプレリザーブ」(ナッジ理論)や「前回の来場者への特別割引」(サンクコスト)など集客の工夫を複合的に組み合わせることも「ムラ」の演出としては有効ではないかと思います。現代は日常的に情報オーバーロードや選択オーバーロードなどに晒されている常態にあり、どんなにクオリティーが良いもの(ムラ)でもその演出に失敗すればムラムラとさせることは困難になっていますが、誰に対して何を訴求したいのか(ターゲティング)を明確にしたうえで行動経済学の知見を応用しながら「ムラ」の演出を効果的に行うことができるのか否かも実力のうちという時代状況になっていると言えるかもしれません。
▼マクロな世界のムラからミクロな世界のムラへ(物理学+経済学+音楽学)
分類 物理学 経済学 音楽学 マクロな世界
対称性の破れ
確定的・人工的古典物理学
ニュートン力学
熱力学
因果律
確定性等古典経済学
ホモ・エコノミクス
神の見えざる手等古典音楽
機能和声
半音
十二平均律等ミクロな世界
高い対称性
不確定的・自然的現代物理学
量子力学
確率的
不確定性等現代経済学
限定合理性
行動経済学等現代音楽
無調音楽
微分音
スペクトル音楽
偶然性音楽等※マクロな世界はムラの演出が比較的に単純でしたが、ミクロな世界はムラの演出が複雑になる傾向があると言えるかもしれません。<▼人が「ムラ」に惹かれるメカニズム(脳科学+心理学)
分類 脳科学
(脳神経ネットワーク)心理学
(認知プロセス)特徴 システム1 デフォルト・モード・ネットワーク ヒューリスティック 直感的 システム2 セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク システマティック 論理的
▼東京藝術大学奏楽堂モーニングコンサート2025(第6回)
【演題】東京藝術大学奏楽堂モーニングコンサート2025(第6回)
【演目】①越川廉 夜露の絶え間ない反射と煌めき(2025)
②A.ハチャトゥリアン ピアノ協奏曲(1935)
<Pf>今井菜名子
【演奏】<Cond>現田茂夫
<Orch>藝大フィルハーモニア管弦楽団
【日時】2025年7月3日(木)11:00~
【会場】東京藝術大学奏楽堂
【一言感想】
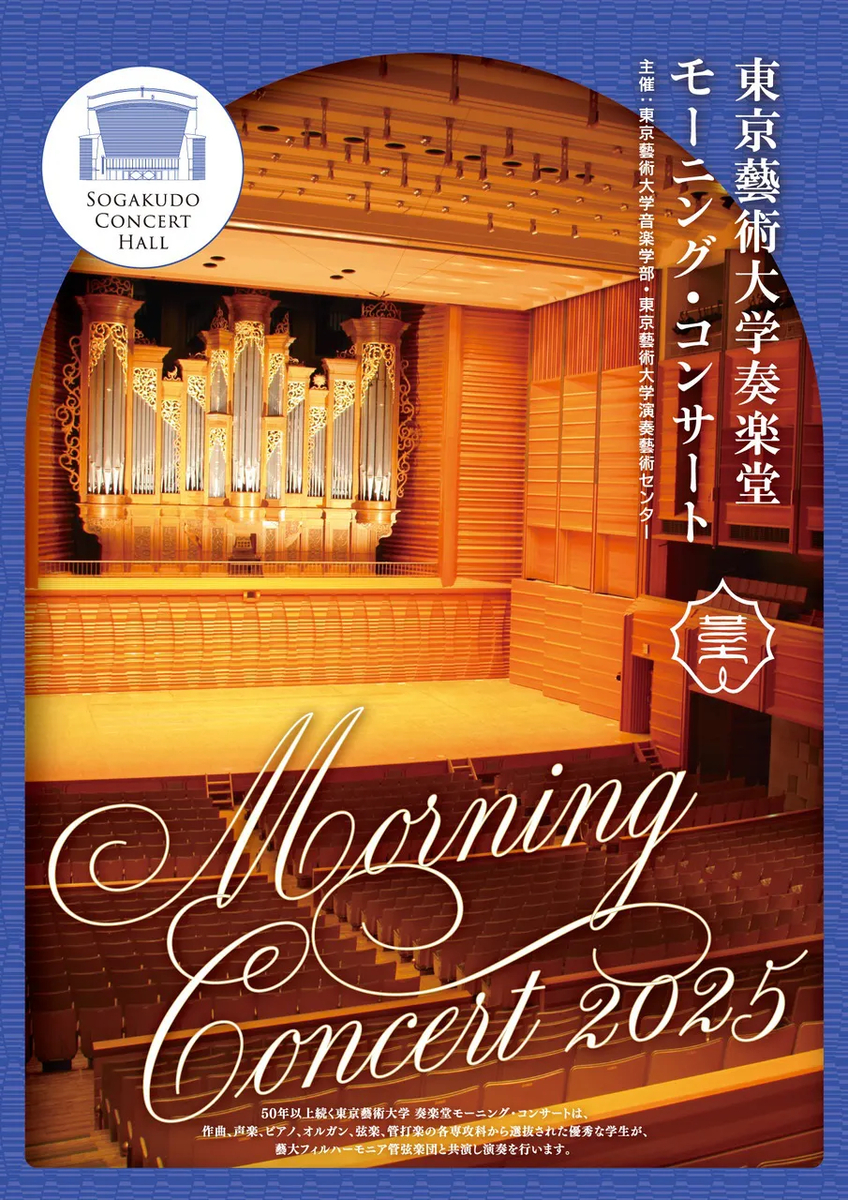
前回のブログ記事で東京藝術大学奏楽堂モーニングコンサート第3回の感想を簡単に書き残しましたが、今回は作曲科の学生の新作初演とピアノ科の学生の現代音楽(凡そ、第一次世界大戦以前の音楽=クラシック音楽、第一次世界大戦後の音楽=現代音楽)が採り上げられるというので聴きに行くことにしました。社会人にとって平日に開催される演奏会を聴きに行くことはハードルが高く、とりわけモニコンは木曜日午前中の開催ということで客層は自ずと高齢者や学生に限られますが、かなりコスパが高い演奏会に満足できました。因みに、過去のモニコンのアーカイブ配信が公開されているようなので、時間や地理の制約からモニコンを聴きに行くことが難しい方はオンラインでお楽しみ下さい。アーカイブ配信を聴いてみるとライブ演奏では聴き逃している点が多いことに気付きますので、どちらの受容方法が優れているという問題ではなく、それぞれに一長一短があって、それを踏まえた楽しみ方がそれぞれにあるのではないかと思います。
①越川廉 夜露の絶え間ない反射と煌めき
パンフレットには「冷え込んだ夜に、水蒸気が水滴となって地物の表面に凝結する。だんだんと水滴は大きくなって、今まさに地面に落ちなんとす。その水滴は月明かりに照らされて、一瞬の絶え間ない煌めきと共に地球に還元されて行く」様子に着想を得て、「この曲の大部分では12個以上の音名が輝いている。それこそがこの曲のオスティナーとであり、根幹を成す。木管、金管、弦と明確に分けられた集団それぞれが、群を形成しながら曲が展開していく」と記載されています。過去のブログ記事で水分子を例にしてエントロピー増大の原則に簡単に触れましたが、気体は熱の放射効率が低い傾向があるのに対し、個体は熱の放射効率が高い傾向があり、空気中の水蒸気が熱の放射効率が高い傾向がある葉や地面などに触れることで冷やされ、その水分子の熱運動が低下することで水素結合が起こり易くなり結露します。また、夜露が月光に煌めく現象は、光子が持つ電磁波が水分子の電子と相互作用することで生じますので、それらのイメージを音にプロジェクションしながら鑑賞しました。ピアノと打楽器の硬質な音は夜露が月光に煌めく様子を、また、弦楽器のグリッサンドやトリル、木管楽器の持続音は空中に立ち込める水蒸気を表現したものでしょうか、これにハープ、管楽器と打楽器のトリルが加わってオーケストラの響きが多層多彩に重なり合いながらカオスな音場が生まれ、それらが微細に変化しながら移ろって行く様子は水と光が織り成す音の万華鏡とも言うべき幻想的なものでした。それが収束や盛上りを繰り返しながら、やがてピアノ、ハープ、打楽器が奏でる音粒が交錯しながら月光に煌めく様子が表現されているように感じられました。やがて音楽はテンションを高めながら、夜露が月光に反射する様子を表現したものでしょうか、管楽器と打楽器が音響の残像を奏で出し、やがてオーケストラがクライマックスを築いた後に、最後に夜露が地面に落ちる様子でしょうか、舞台袖のバンダ隊による足踏みと指鳴らしで余韻深い終曲になりました。ビジュアルアートと組み合わせると、よりイメージが広がって面白いかもしれません。演奏前に作曲科の学生によるMCで、観客が音響に身を浸しながらそれぞれのプロジェクションを投射して自由に鑑賞して貰いたいと挨拶されていました。現代作曲家の中には解説を厭う人もいますが、音楽のような抽象表現を何らの手掛りもなく鑑賞することは聴衆にとって難解、苦痛な体験にしかならないことが多く、(仮に聴衆による受容を前提とするものであれば)少なくとも鑑賞の手掛りとなる解説は必要不可欠であると痛感しており、その意味でも創作の着想やコンセプトなどを第三者(聴衆や演奏家など)に説明するためのMCは有用ではないかと思います。
②A.ハチャトゥリアン ピアノ協奏曲
ヴラヴァー!ピアニストの今井菜名子さんの演奏を初めて聴きましたが、先日の松田華音さんと同様に、若い世代のピアニストに稀有な逸材が多いことを印象付けられる好演でした。ロシアビアニズム芬々たる堅牢で華々しいヴィルトゥオージーはもとより、指揮者の現田茂夫さんの老練巧みなリードが奏功したこともあり、この曲の特徴でもあるオリエンタリズムや民族色をバランスよく薫らせながら、この曲の魅力を組み尽くす満足度の高い演奏を楽しめました。第一楽章ではオーケストラによるインパクトのある開始で舞台のテンションが一気に高まり、その張り詰めた空気を切り裂くように独奏ピアノが鋭角な響きによる活舌の良い演奏による華々しい登場感に惹き込まれました。強靭で質感のある打鍵、リズムの生命力、幅白い音域を縦横無尽に駆け巡る疾走感、軽快に冴え渡る超絶技巧などで魅了し、重厚感のある低音から光沢感のある高音までコンサート・グランドを豊かに鳴らし切りながら、民族色から諧謔性、メカ二カルな曲調などを表情豊かに弾き分けるダイナミックにして繊細な構築感のある演奏を堪能できました。パワー志向のマッチョな演奏というよりも、オーケストラが表情豊かに歌うパートでは独奏ピアノは伴奏に徹してアンサンブルに彩りを添える好サポート、独奏ピアノが華々しく歌うパートではオーケストラが絶妙な呼吸感で緊密に呼応するバランスの良い極上のアンサンブルが出色でして、非常に完成度の高い演奏を楽しめました。オリエンタリズムを湛えたオーボエなどが聴き所になる好演で、最後は独奏ピアノとオーケストラが一体になってクライマックスを築く高揚感のある演奏を楽しめました。第二楽章ではメランコリーに揺蕩うバスクラが好演で、これに続く寂び寂びとした詩情を湛えた独創ピアノによる背筋が凍り付くような美しさに魅了されました。独創ピアノとオーケストラの洗練されたアンサンブルに隙はなく、現田さんがたっぷりとオーケストラを歌わせながら民族色を豊かに薫らせる好演が白眉でした。第三楽章ではオーケストラと独創ピアノによるリズミカルで軽快な開始でティンパニーに挑発されるかのように民族色を巻き散らしながら野趣漲るダイナミックな演奏を楽しめたが、非常に慎重かつ繊細なアンサンブルも展開されるなど知情意のバランスがとれた表情豊かな演奏に好感しました。最後は金管の咆哮に誘われてオーケストラと独奏ピアノによる絢爛たるクライマックスが築かれる大団円になりました。
▼歌舞伎「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」
【演目】歌舞伎「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」
大喜利所作事 舞競花刀剣男士
【原案】「刀剣乱舞 ONLINE」より
【脚本】松岡亮
【演出】尾上菊之丞 尾上松也
【出演】<三日月宗近/羅刹微塵>尾上松也
<陸奥守吉行/源実朝>中村歌昇
<同田貫正国/公暁>中村鷹之資
<髭切>中村莟玉
<加州清光/実朝御台倩子姫>尾上左近
<異界の翁/三浦義村>澤村精四郎
<膝丸>上村吉太朗
<異界の媼/源仲章>市川蔦之助
<小烏丸/北條政子>河合雪之丞
<大江入道>大谷桂三
<鬼丸国綱>中村獅童 ほか多数
【演奏】<箏>中井智弥(二十五絃)
中島裕康(十七絃)
細川喬弘、清原晏、木下富博(十三絃)
<琵琶・尺八>長須与佳
<笛>藤舎推峰
<長唄>杵屋勝四郎、杵屋正一郎、杵屋巳之助、
杵屋和三郎、杵屋彌六郎、杵屋正則、
杵屋勝四助、杵屋巳三寿郎
<三味線>和歌山富之、柏要吉、杵屋巳佐
高橋智久(東音)、杵屋六治郎、杵屋勝国穀
杵屋浅吉、杵屋五助、杵屋直光
杵屋三禄
<囃子>望月太左久、望月太喜十朗、望月徹
堅田喜三郎、堅田新一郎、梅屋喜三郎、望月左喜十郎
住田福十郎、福原百七、望月太喜之助
<竹中連中>(浄瑠璃)竹本蔵太夫、竹本真太夫、竹本和太夫
(三味線)豊澤勝二郎、鶴澤卯太吉、豊澤一二三
<テーマ曲>「風になれ花になれ」
(歌)城南海
(作詞・作曲)中井智弥
【録音】<筝>中井智弥(十三絃、二十五絃、低二十五絃)
中島裕康(十七絃)
<琵琶・尺八>長須与佳
<笛>藤舎推峰
<津軽三味線>浅野祥
<太鼓>山部泰嗣
<打物>住田福十郎
<Key>大迫杏子
<Perc>相川瞳
<Vo>日高悠里
【美術】前田剛
【照明】高山晴彦
【作曲】中井智弥、杵屋巳太郎(長唄)、豊澤勝二郎(竹本)
【音響】土屋美沙
【立師】中村獅一、尾上まつ虫
【衣装】黒崎充宏
【日時】2025年7月5日(日)~2025年7月27日(日)
【会場】新橋演舞場
【一言感想】

今日は歌舞伎「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」を鑑賞するために新橋演舞場に足を運びました。新橋演舞場に隣接する料亭「金田中」の向かい側にある新橋の髭切ことヘアーサロン「マツモト」で髭を当たって身を清め、演舞場稲荷大明神のお祓い(鉄砲洲稲荷神社の宮司さんでしょうか?)に推参して新橋演舞場のスタッフの末席で心も清めました。因みに、新橋演舞場は加賀藩支藩の下屋敷跡にありますが、加賀藩の御家騒動を題材にした歌舞伎「鏡(加賀見)山旧錦絵」に登場する主君の仇討ちを果たした女中のお初に因んで、演舞場稲荷大明神は通称「お初稲荷」と呼ばれるようになり、「お初」と「初日」を掛けて舞台初日にお祓いが行われる習わし(江戸の粋)になっています。さて、過去のブログ記事で歌舞伎シネマ「刀剣乱舞 月刀剣縁桐」の感想を簡単に書き残しましたが、歌舞伎「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」はその第二作に位置付けられます。「東鑑」(吾妻鏡)とは鎌倉幕府が編纂した歴史書で、その中から鎌倉幕府三代将軍・源実朝(鎌倉幕府最後の源氏将軍であり、その後は執権・北条氏が鎌倉幕府を実行支配)が鶴岡八幡宮で斬殺された事件に取材し、その歴史改変を目論む時間遡行軍の野望を刀剣男子が阻止するというプロットです。今回は最後に刀剣男子が大喜利所作事「舞競花刀剣男士」で春夏秋冬をテーマにした舞踊を披露する華麗な舞台が用意されており、歌舞伎的なエンターテイメント性の高い趣向になっていました。この舞台全体を通しての印象としては、鎌倉時代(過去)と刀剣男子の時代(未来)という物語設定を利用して、科白、演技、演出、音楽及び美術などの舞台の諸要素も歌舞伎の伝統(古典)と革新(現代)を交錯させながら、それらが最後には融合して行くような構成の舞台に感じられ、日頃、歌舞伎に馴染みのない若い世代もアニメの世界観から歌舞伎の世界観へと自然に入って行けるような舞台上の工夫が随所にあり、その目論見が成功していたように感じられました。また、そのような構成にしたことでアニメの世界観と歌舞伎の世界観のそれぞれの良さが際立つ効果も生んでいたように感じられました。第一作と共通している登場人物は歌舞伎版としてのキャラクターが確立し、それだけ第二作では共感度が高まっている印象を受けましたが、是非、次回作以降に向けて歌舞伎版のキャラクターを磨き上げて行って欲しいと期待しています。舞台公演が始まったばかりなのでネタバレしないように簡単に感想を残しておきたいと思いますが、そうは言っても、多少のネタバレは避けられませんので、これから観劇される予定の方はお気を付け下さい。開幕前のホスピタリティーとして時間遡行軍に扮した歌舞伎役者が一階席を歩き回り観客との記念撮影に応じるサプライズ特典が用意されており、また、開幕前の予鈴も発端第二場における審神者の登場シーンで使われている笙の演奏が代用されており、観客を神様扱いする心尽くしの演出に好感しました。
〇発端(第一場、第二場):現代的な演出
観客の意識を物語の世界観に惹き込むように重厚な筝の演奏と共に照明が落とされて開幕しましたが、第一作の歌舞伎「刀剣乱舞 月刀剣縁桐」で刀剣男子に撃退された異界の翁と媼が現われ、鎌倉幕府の悪政に虐げられた庶民の苦しみの呪い込められている千年檜の精霊に刀剣男子への復讐を懇願すると、妖気漂う筝の演奏と共に「不思議やな 千歳の檜 鳴動し 焔に浮かぶ 人影は この地の主と 覚えたり」という地謡に誘われて千年檜の精霊が羅刹微塵に化して顕現しました。そこへ時間遡行軍も現われ、筝の激しい演奏と共に鎌倉時代へとタイムスリップする緊迫感のある幕開けになりました。鎌倉幕府の悪政に虐げられていた庶民の苦しみを救うために顕現した羅刹微塵(不遇な者の正義)とそれを歴史改変という間違った手段で達成しようとする羅刹微塵(正義に奢る者の不義)という二面性は現代社会が抱える諸問題(国際紛争やSNS問題など)にも通底するもので、現代人にも共感し易いテーマ性を持っているように感じられました。時間遡行軍が鎌倉時代(鎌倉幕府三代将軍・源実朝の時代)に出撃したという報せを受けた審神者は刀剣男子(刀剣の付喪神)を招集して、第一作にも登場した三日月宗近、髭切、膝丸と第二作が初登場となる加州清光(沖田総司の刀剣)、陸奥守吉行(坂本龍馬の刀剣)、鬼丸国綱(大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で坂東彌十郎さんが演じていた北条時政の刀剣)の六振りに出陣を命じ、第一作にも登場した小烏丸と同田貫正国の二振りには後方支援を命じました。邦楽アンサンブルの派手な演奏に乗せて、鎌倉時代に出陣する刀剣男子六振りが白波五人男よろしく名乗りを挙げると、「東鑑雪魔縁」と書かれた赤い中割幕が下ろされ、城南海さんが歌う主題歌「風になれ花になれ」が流れるなか花道から鎌倉時代へ出陣しました。さながらアニメのオープニングを見ているような、江戸の粋(意気)とは一味異なる令和の粋へとバージョンアップされた華々しい舞台演出に感じられました。能舞台の橋掛りは彼岸(鏡の間=神の世界)に連結してシテに霊が憑依する幽玄の世界(鎌倉時代の武士の美意識)を体現する舞台装置ですが、それから転じて、歌舞伎舞台の花道は此岸(客席=庶民の世界)に連結して役者を魅せる情粋の世界(江戸時代の庶民の美意識)を体現する舞台装置であり、それらの起源は同一のものであっても、それぞれは全く異なる美意識や演出意図に基づく重要な役割を担うものであることがよく分かります。
〇序幕(第一場):古典的な演出
三味線や鳴物の情緒的な演奏と共に、鎌倉幕府三代将軍・源実朝の名代として源実朝の御台・倩子姫、源実朝の甥・公暁、源実朝の側近・源仲章が源実朝の母・北条政子の病気見舞いに梅花と源実朝の和歌「春くれば、まづ咲く宿の 梅の花 香をなつかしみ 鶯ぞ鳴く」(金槐和歌集)(山上憶良の和歌「春されば まづ咲く屋戸の 梅の花 独り見つつや 春日暮らさむ」(万葉集)の本歌取りで、山上憶良の和歌は政を司る官人として孤独な春を慈しむ心情を詠んだものにも感じられる一方で、源実朝の和歌は政を疎んじて花鳥風月に慰めを求める心情を詠んだものに感じられます。)を北条政子に贈りますが、北条政子は後鳥羽院(大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では尾上松也さんの配役)から次期将軍と目されながら遊興に耽る源実朝を憂いている様子が印象的に描かれていました。そこへ時間遡行軍が来襲しますが、太鼓や附け打ちが激しく鳴らされるなか、北条政子の警護として潜り込んでいた三日月宗近と鬼丸国綱が立ち回る華々しい舞台になりました。第一作では審神者の声のみの出演だった中村獅童さん(大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では梶原景時の配役)ですが、やはり尾上松也さんと同様に華のある役者なので、その存在感(吸引力)に舞台が引き締まります。
〇序幕(第二場、第三場):現代的な演出
筝の軽妙洒脱な演奏と共に、一階席から加州清光(沖田総司の刀剣)と陸奥守吉行(坂本龍馬の刀剣)が犬猿の仲よろしく漫談風にいがみ合いながら登場し、髭切と膝丸は源氏代々の宝刀であると素性由来を語りましたが、刀剣男子は未来人という設定なので科白回しは現代語調で現代劇を観ているような印象を受ける舞台になっていました。近年、ブルーノート東京でも他のジャンルからビックネームの出演を招聘することで客層の拡大を図っていますが、丁度、映画「国宝」がヒットして歌舞伎に関心が集まっているなか、歌舞伎を見慣れていない若い世代にも無理なく歌舞伎の世界に入って行けるように配慮されたタイムリーな舞台ではないかと思います。未だチケットが取れるのか分かりませんが、夏休みに子供を連れて歌舞伎鑑賞はいかがでしょうか。尺八の渋味深い演奏と共に、北条政子の侍女・桔梗が人目を忍んで源仲章に密書を届けますが、それを公暁の守役である三浦義村に見咎められ、権謀術数が渦巻く鎌倉幕府の闇が印象的に描かれていました。そこへ羅刹微塵が来襲しましたが、筝と附け打ちが激しく囃し立てるなか、加州清光、陸奥守吉行、髭切、膝丸が三浦義村に加勢して羅刹微塵は消え失せました。筝のリリカルな伴奏と共に、刀剣男子六振り(尾上松也さんが羅刹微塵から三日月宗近へと早変わり)が揃って「東鑑」(吾妻鏡)を引用しながら刀剣男子が守るべき歴史と人物の相関関係(源頼朝の子が源頼家(嫡男)と源実朝(次男)、源頼家の子が公暁)をお浚いし、羅刹微塵の正体やその目論み(歴史改変は手段でしかなく、本当の目的は庶民の怨みを晴らすこと)、時間遡行軍との関係(歴史改変の目的のために羅刹微塵を利用していること)などの物語設定が一通り整理して説明されました。演劇作品の中にはプロットが複雑で舞台展開もめまぐるしく観客が物語展開を十分にキャッチアップできない(又は没入できない)ものもありますが、十分な配慮が感じられて好感しました。膝丸は源実朝が政を疎んじて遊興に耽る真意を量り兼ねていますが、これに対して髭切は情に溺れて刀剣男子の使命(時間遡行軍による歴史改変を阻止すること)を忘れてはならないと戒め、筝や尺八のミニマル風の演奏と共に髭切と膝丸の複雑に揺れ動く心情が印象深く描かれていました。
〇序幕(第四場、第五場):古典的な演出
序幕(第二場、第三場)では刀剣男子を主体とする現代的な演出でしたが、序幕(第四場、第五場)では鎌倉人を主体とする古典的な演出の舞台で、笛の情緒的な演奏と共に源実朝と御台・倩子姫が睦み合っているところに、膝丸が登場して源実朝の和歌「身に積もる、罪や如何なる罪ならん、今日降る雪と、共に消えなん」(金槐和歌集)を引用して源実朝の真意を問い質しますが、源実朝は兄・源頼家が外祖父・北条時政に殺害されてからは母・北条政子とも疎遠になっているが、父・源頼朝や兄・源頼家による武力の政治とは異なり慈悲で天下を治めたいという志を打ち明けて退席します。御台・倩子姫は膝丸が未来人であることに気付いて源実朝の運命を聞き出しますが、これを源実朝が立ち聞きしており自らの運命を受け入れるという印象的な場面になっていました。寂び寂びした笛の音と共に、権謀術数が渦巻く鎌倉幕府で悲しい運命に翻弄される源実朝と御台・倩子姫の情感が溢れる歌舞伎の魅力を湛えた舞台になっていました。北条政子、源仲章、公暁、大江入道、三浦義村、北条義時らが源実朝を右大臣に補任する後鳥羽院の院宣の取扱いについて協議した後、源仲章と公暁だけが残り、源仲章に唆された公暁は源実朝と北条義時を討つ決意をします。公暁の情念の焔を感じさせるような三味線の激しい演奏が出色でした。
〇序幕(第六場、第七場):現代的な演出
羅刹微塵が鎌倉幕府に渦巻く醜い権謀術数により庶民が苦しめられている怨みを晴らすために立ち上がる迫力の舞台になっていましたが、筝の激しい演奏が羅刹微塵の妖気を帯びた情念の焔を感じさせるもので出色でした。第一作でも感じましたが、中井智弥さんの音楽はピアノやハープに双璧する筝の豊かな表現力、多彩な音色や奏法などを存分に活かし、ジャンルレス、ボーダレスに着想豊かな音楽が繰り広げられていきますが、歌舞伎の舞台表現を拡張して現代的にアップデートして行くにあたり、その多彩な音楽性は欠かせないものになっていると感じますし、それとの対比で伝統的な歌舞伎音楽が彩る情趣を引き立て、その魅力を際立たせる効果も生んでいるようにも感じますので、音楽の面からも歌舞伎の伝統と革新を融合する試みに期待したいと思っています。筝のリリカルな演奏と共に、髭切と膝丸は源実朝への思慕の情に流されずに歴史を守るという刀剣男子の使命を果たすことを確認し、他の刀剣男子達も油断なく羅刹微塵や時間遡行軍を阻止することを決意し、邦楽アンサンブルによる華々しい演奏で序幕が閉じました。
〇第二幕(第一場、第二場):現代的な演出
筝の妖気漂う演奏と共に、まるでオペラのセットを彷彿とさせる暗闇の舞台で第二幕が開け、公暁は守役の三浦義村に対して右大臣拝賀の式で謀反を企てる北条義時と源実朝を討つことを持ち掛けますが、三浦義村は公暁に自重するように促して断ります。そこへ羅刹微塵が来襲して庶民の苦しみに目もくれず醜い野心に囚われる公暁を斬殺して歴史改変を行ってしまいますが、筝と附け打ちがフラメンコ風のドラマチックな伴奏を奏でるなか、鬼丸国綱と髭切が三浦義村に加勢して羅刹微塵は花道から逃げ去ります。回り舞台で場面が展開し、尺八の渋味深い演奏と共に、源実朝が右大臣拝賀の式へ向うところですが、笛と筝の寂寥感漂うリリカルな演奏と共に、(序幕第四場で)運命を知っている源実朝と御台・倩子姫は言葉にはならない惜別の情を交わしますが、前場の公暁の心に宿る深い闇と後場の源実朝の心に宿る清い光とが対照される印象的な場面になってました。
〇大詰(第一場から第三場):古典的な演出と現代的な演出の融合
大詰(第一場から第三場)は古典的な演出と現代的な演出が違和感なく融合して1つの世界観を体現しているように感じられました。鎌倉山の情景と源実朝の心情を重ねた情緒纏綿とした長唄に乗せて右大臣拝賀の式に向かう源実朝一行が花道から入場する場面は源実朝の道行とも言える歌舞伎的な美観が際立つ印象深い場面になっていました。その後、中割幕が開くと、鶴岡八幡宮の階段が登場し、太鼓で降りしきる雪を表現するなか、髭切と膝丸は(第二幕第一場で)改変された歴史を元に戻すために公暁に代わって源実朝を斬り、笛と筝の寂寥感漂う演奏のなか、髭切と膝丸は源実朝の最後を看取って刀剣男子の使命を果たす中締めになりました。丁度、大詰第二場は開幕から十三場目になりますが、源実朝は鶴岡八幡宮の大石段の十三段目で斬殺されたと言われており、この場面割りも舞台演出の1つかもしれません。その後、邦楽アンサンブルがフラメンコ風のドラマチックな伴奏を奏でるなか、髭切、膝丸、鬼丸国綱と羅刹微塵、時間遡行軍とのアクロバティックな立ち回りが展開され、羅刹微塵が花道を附け打ちに合わせて引っ込む見所になっていました。三味線と太鼓が激しく打ち鳴らすなか、北条義時は羅刹微塵と時間遡行軍に襲撃されますが、そこへ鬼丸国綱が割って入り、羅刹微塵と鬼丸国綱の所作タテを経て、これに小烏丸、同田貫正国を含む他の刀剣男子が加わって羅刹微塵、時間遡行軍とのアクロバティックな立ち回りになりました。最後に羅刹微塵(尾上松也さんの代役?)と三日月宗近の立ち回りが挟まれた後、邦楽アンサンブルの快活な演奏と共に羅刹微塵は消え失せました。笛、三味線、筝がリリカルな調べを奏でるなか、北条政子は舞台袖、刀剣男子は客席から退場して終幕になりました。
間狂言を挟んで、
〇大喜利所作事「舞競花刀剣男子」(第一景から第六景):古典的な演出と現代的な演出の融合
第一景「序-三番叟」は義太夫節と三味線に乗せて髭切と膝丸が足拍子で邪気を払いながら勇壮で華麗な剣舞を披露、第二景「春-伊達男」は長唄と三味線に乗せて三日月宗近が三日月をあしらった唐傘と下駄を使って伊達男の色香漂う舞踊を披露、第三景「夏-祭り」は筝、笛、長唄、三味線に乗せて扇子を持った粋な浴衣姿で陸奥守吉行がよこい節(高知)、同田貫正国がおてもやん(熊本)、加州清光は加賀はいや節(金沢)などのお国自慢の舞踊を披露、第四景「秋-玉虫悲恋」は平家琵琶(女声の艶)と三味線、義太夫節(男声の艶)の語り芸の極致を言うべき名演に乗せて那須与一に扮した三日月宗近(青)と玉虫に扮した小烏丸(赤)が情熱的で優美な所作舞を披露、第五景「冬-獅子の曲」は長唄、三味線、筝に乗せて鬼丸国綱が白頭獅子、異界の翁と媼が赤頭獅子に扮し、時間遡行軍を撃退する勇壮な舞踊を披露、第六景「フィナーレ-時をこえて」では合唱、邦楽囃子に乗せて刀剣男子が一人づつ剣舞を披露した後、桜吹雪が散るなか扇子を持った群舞を披露し、主題歌「風になれ花になれ」が流れるなかを刀剣男子が舞台の華になって鮮やかに散って行く大団円となりました。
▼読売交響楽団第650回定期演奏会
【演題】読売交響楽団第650回定期演奏会
【演目】F.メンデルスゾーン 付随音楽「真夏の夜の夢」序曲(1826)
細川俊夫 月夜の蓮 -モーツァルトへのオマージュ-(2006)
※アンコール:C.シューマン ピアノ曲「蓮の花」
(原曲:R.シューマン 歌曲「蓮の花」)
<Pf>北村朋幹
H.ツェンダー シューマン幻想曲(1997/日本初演)
【演奏】<Cond>シルヴァン・カンブルラン
<Orch>読売交響楽団
【日時】2025年7月8日(火)19:00~
【一言感想】

スペインのBBVA財団が主催し、ノーベル賞の補完的な存在とも言われる世界的に権威があるフロンティアズ・オブ・ナレッジ賞音楽・オペラ部門を現代作曲家の細川俊夫さんが受賞されたことに伴い、去る6月18日に開催されたガラ・コンサートでヴァイオリニストの諏訪内晶子さんをソリストに迎えて細川さんのヴァイオリン協奏曲「ゲネシス」(2020)が演奏され、翌6月19日に開催された授賞式では同賞と共に賞金40万ユーロ(約6,800万円!)が授与されました。ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行を資金母胎とするだけあって、ノーベル賞に双璧する賞金額が目を引きます。細川さんは「その作品の並外れた国際的影響力」が評価され、「日本の音楽の伝統と現代西洋の美学の間に橋を架けた」として受賞に到っていますが、近年の受賞者を見ても、J.ベンジャミン(藤倉大さんの師匠)、T.アデス、P.グラス、A.ペルト、J.アダムズ、K.サーリアホと歴史に名前を残すであろう世界的に著名な作曲家が並んでおり、この列に音楽・オペラ部門として初めて東洋人が名前を連ねることになったことは大変に喜ばしく誇らしいものを感じます。細川さんが「日本の音楽の伝統と現代西洋の美学の間に橋を架けた」と思われる代表作の1つを現代音楽のスペシャリティーである指揮者のS.カンブルランさんが古巣の読響を率いて演奏するというので聴きに行くことにしました。1曲目の感想は割愛し、現代音楽2曲の感想を簡単に残しておきたいと思いますが、東洋と西洋のファンタジーが交錯する次代に残る名曲2曲に非常に満足度の高い演奏を楽しめました。ヴラヴィー!
②月夜の蓮-モーツァルトへのオマージュ-
パンフレットには「2006年、モーツアルト生誕250年を記念して、北ドイツ放送は世界の4人の作曲家に新作を委嘱した。条件は作曲家ごとに異なるカテゴリーを指定し、カップリングするモーツァルトの曲を選ばせ、それと同じ楽器編成で新作を書くこと。細川俊夫はピアノ協奏曲第23番イ長調を選んだ。」と解説されています。ピアニストの北村朋幹さんはコンテンポラリー弾きとして頭角を現わしていますが、その研ぎ澄まされたデリケートなタッチにより静寂から生まれた音粒が空間へと澄み渡り静寂へと回収されて行く静謐にして深淵な演奏に息を呑みました。水墨画の余白が描く世界観のように、音粒の先に広がる静寂を聴かせる音楽であり、それは標題の「月夜の蓮」の佇まいをイメージさせる詩的な幻想美を湛えていました。S.カンブルランさんと読響も細部まで配慮の行き届いた息を呑む好演で幽けき持続音とトリルが精妙に移ろい、それらが幾重にも重なり合いながら生成(沼の水面上=生のメタファー)と消滅(沼の水面下=死のメタファー)を繰り返す生滅流転の世界観を体現しているように感じられ、その深淵な精神性と共に大きな音楽が聴こえてきました。蓮は、沼底の地下茎から発芽して水面に葉を広げ、花托を伸ばして蕾(未敷蓮華)を結びますが、その張り詰めた静寂の中に息衝く生命力の気配のようなものが感じられる音楽で、フランス人俳優のジャン・ルイ・バローさんが観世寿夫さんの演能を鑑賞された際の言葉「能の静止は息衝いている」という言葉を思い出しましたが、沼の水面下を橋掛り、沼の水面上を本舞台、蓮の蕾をシテに見立て音楽にプロジェクションして鑑賞していましたが、西洋音楽を使いながら日本の伝統的な美意識の深淵に迫る作品に圧倒されました。最後に、北村さんが爪に灯を灯すような繊細なタッチでモーツァルトのピアノ協奏曲第23番第二楽章の残照を薫らせていましたが、月夜(モーツァルト又はピアノ協奏曲第23番第二楽章のメタファー?)に誘われて蓮の蕾が頭を擡げて開花しようとしているイメージと重なってこの世の「儚さ」が募る極上の音楽に心酔しました。この曲の余韻は休憩を挟んで次の曲の演奏が開始されても続いていたことを告白しますが、次の世代にも聴き継がれるであろう稀代の名曲を(当日は細川さんも会場に見えられていましたが)作曲家と同じ空間で受容できた幸運に心から感謝したい気持ちです。さながらモーツァルトと一緒にピアノ協奏曲第23番を受容してしまったような得難い体験です。ヴラヴィー!!アンコールは、C.シューマンのピアノ曲「蓮の花」(原曲:R.シューマンの歌曲「蓮の花」)が演奏されましたが、左手の幻想、右手の憧憬が繊細に絡み合う夢見心地の演奏を楽しめました。因みに、来る7月12日から七十二候「蓮始開」(蓮の花が咲きはじめる季節)なので、この曲を聴きながら蓮見の宴で夕涼みと洒落てみるのも良いかもしれません。
③シューマン・ファンタジー(日本初演)
パンフレットには「音響や作曲技法の新しさに価値を置くモダニズムの時代には既存作品の編曲はあまり好まれなかったが、1990年ごろから原曲の解釈を加えた「創造的編曲」(又は「作曲された解釈」)はよく行われている。」としたうえで、「1997年の「シューマン・ファンタジー」は、ツェンダー自ら「作曲された解釈」と呼ぶ作品群の一つである。「作曲された解釈」とは一種の編曲なのだが、単に異なる楽器編成にするだけではなく、独自の解釈を加えて音を増減する。」と解説されています。この曲はR,シューマンのピアノのための「幻想曲」ハ長調作品17が原曲になっており、原曲のフラグメントが随所に使われていましたが、某TV番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」よろしく、原曲の面影は残しながら原曲の基礎や間取りから徹底的に手を入れてインテリアも一新してしまうなど、原曲を換骨奪胎して全く新しい作品へと生まれ変わらせたうえで、原曲を凌駕し又は原曲にはなかった魅力まで追加することに成功している新作と見紛うばかりの出来映えです。これだけの傑作が日本で初演されていなかった事実に愕然とさせられます。その意味では、この曲を日本に紹介してくれたS.カンブルランさんと読響に心から感謝しなければなりません。P席後方のバンダ(弦)、舞台裏のバンダ(金管)がソリスト、本舞台のオーケストラがトッティーという位置付けで対置され、バンダが前奏曲と間奏曲を微分音、不協和、ノイズなど現代的な響きで演奏し、オーケストラが原曲を素材とした3曲を演奏しましたが、単に原曲にオーケストレーションを施した編曲とは異なり、上述のとおり原曲の美観は残しながらも原曲を大胆にスクラップ&ビルドし、斬新かつ独創的にデフォルメしてユーモアまで塗布してしまうなど匠の技とセンスが冴え渡る作品に生まれ変わっており、その結果として原曲とは全く別の地平を切り拓く傑作へと昇華してしまう辣腕に感服しました。芸術に進歩主義的な考え方は馴染みませんが、現代作曲家の才能が歴史上の偉大な作曲家と比べて劣らないばかりか、これを凌駕し得ることを証明してみせるような作品に嬉しくなりました。ドーパミンが大量に分泌されていることが分かる面白さが随所に散りばめられ、まるで微睡んでいるような多彩なファンタジー(西洋的な幻想美)に魅了される至福の演奏を堪能できました。ヴラヴィー!!
▼エンタメ大国 日本日経新聞電子版(2025年6月30日)に「時価総額、エンタメが自動車抜く 上位9社で見えた日本株高の原動力」というタイトルの記事が掲載されましたが、日本の産業構造が大きな転換期を迎えているようです。この点、日本は20世紀までは製造業を中心にして大量かつ均質な「モノ」(所有の対象)を作ることが重視されていた時代であり「技術大国 日本」と評されてきましたが、バブル崩壊によるショックから過去の成功体験にしがみ付いてきた「失われた30年」の間に凋落を招きました(WIPOが公表している世界イノベーション指数で世界第13位)。しかし、このままでは終わらず、2010年からのクールジャパン戦略が奏功したものなのか、現在ではエンタメ業を中心にして斬新かつ独創的な「コト」(共有の対象)を体験することが重視されている時代であり「エンタメ大国 日本」として世界から注目され(METIが公表している世界コンテンツ市場の規模で世界第3位)、その兆候を裏付ける1つのインシデントとして上記の新聞記事を捉えることができるかもしれませんし、また、前回のブログ記事で触れた新作オペラ・ブームも、このような時代の価値観の変遷が生んだ潮流と捉えることができるかもしれません。20世紀の「どう作るか」(方法)から、21世紀の「どう楽しませるか」(世界観)という発想の転換が必要です。▼21世紀の新しいアウラ(その2)過去のブログ記事で21世紀の新しいアウラ(その1)として音楽生成AIや画像生成AIの創作物が人間の能力を凌駕しつつあることに触れましたが、今回は動画生成AIを採り上げてみたいと思います。2025年7月18日(金)から映画「鬼滅の刃 無限城編」第一章が全国公開されますが、そのシリーズのAI実写の試作が数多くアップされており、アニメの世界観を損なうことなく新しい魅力を創出することに成功していると思われるものが多いので、適正に権利処理されているものと信用してご紹介します。AIアートと同様に人間の能力を凌駕したところに成立している再現性の低いリアルなヴィジュアルに息を呑みます。このアニメが体現している日本の伝統美という古いものと現代物理学の世界観という新しいものを共存させながら、バーチャルとリアリティーの境界を無効にしてしまう異次元の表現力に21世紀の新しいアウラが顕在し始めています。